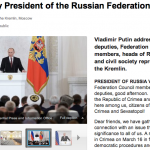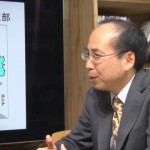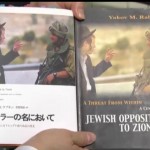- 日時 2014年3月23日(日)
- 場所 大阪大学豊中キャンパス ドイツ文学研究室(大阪府豊中市)
離散する民、ユダヤ人
「離散した民」というユダヤ人のアイデンティティ形成について赤尾氏は、「そもそもユダヤ人が自分たちをユダヤ人と意識をした時点で既にディアスポラ(離散)をしていたとも言える」と語った。
紀元前11世紀頃に成立したと言われるユダヤの国(イスラエル王国)は、ソロモン王の死後に南北に分裂した。紀元前722年に北のイスラエル王国はアッシリアに攻められ滅亡。「(ユダヤ人が)北に散っていった流れ」が一つある。さらに南のユダ王国は紀元前586年にバビロニアに攻められ、バビロン捕囚を経験する。「バビロニアにとらわれの身になった。いわゆるディアスポラ、民族離散の歴史的起こりです」。
その後ふたたびユダヤの国が再建されるが、ローマ帝国の拡大により、ユダ王国は属国的な立場に置かれることになった。紀元70年にはエルサレムがローマ軍の攻撃により陥落し、神殿が破壊される。死海西岸に位置するマサダ(ヘブライ語で「要塞」)に立て籠り徹底抗戦を試みる一派があったものの、ローマの攻勢に耐えきることはできず、集団自決の道を選んだ。
「エルサレム陥落後には現在のイラク付近に位置するバビロニアで重要なユダヤ教の聖典・タルムードが成立し、ユダヤ人の中心地となった」。その一方、離散するユダヤ人の歴史は続く。「北アフリカに渡る経路や、小アジア(アナトリア半島)、あるいはイタリアを通ってヨーロッパに向かう経路もあった」。
世界各地に散り散りとなっても同一の「ユダヤ人意識」が消え去ることがなかった理由について、赤尾氏は聖書とタルムードを挙げた。特にタルムードは、ユダヤ教の戒律を世代間で継承し、日々実践していく「システム」として働いてきたと解説した。また、実践のかたちとして儀礼の重要性を強調。一例として週ごとの安息日を挙げた。「ユダヤ人が安息日を守ってきた以上に、安息日がユダヤ人を守ってきたと言われることがある。つまり、儀式を通してユダヤ人意識が保たれてきた」。
ハザール王国とユダヤ人
9世紀後半から、ロシアとウクライナの起源とされるキエフ・ルーシが興隆する。その東にはハザール王国があった。
ハザール王国に関しては「ユダヤ教に改宗した国」という俗説が広まっているが、赤尾氏はこれに疑問を呈する。「最近の研究では、ハザール王国内にユダヤ教徒がいたことは確実に分かっていますが、国を挙げて改宗したというのは、まず考えにくい」。
また、支配層の貴族だけが改宗したという説も、信憑性が疑問視されているという。「ハザールについての記述がヘブライ語の文献と、その影響があると考えられるアラビア語の文献に出てきますが、そこには、ユダヤ人は国を失ったが遠い地でユダヤ教が国教になった、という希望が多分に膨らんでいる。文学的な創造という可能性も否定できない」。
文献からは「ヨーロッパ系のアシュケナージ・ユダヤ人の多くが(ユダヤ教へ改宗した)ハザールの末裔であるという説」を立証することはできないと赤尾氏は強調し、そもそも東欧ユダヤ人の母語であったイディッシュ語にチュルク語起源の単語が皆無であることから、この説は「歴史的にはまったく支持されない」と断言した。
ウクライナは「狭間で揉まれる」
キエフ・ルーシは東方正教を受容し、そこから独自のロシア正教を発展させた。一方、キエフ・ルーシの西に隣接し勃興してくるポーランドはカトリックの国となった。「ウクライナでは、正教世界とカトリック世界の狭間で揉まれる状態が千年近く続いている」のだと赤尾氏は話す。
16世紀には、ポーランド・リトアニア王国が現在のウクライナ地域へ領土を拡大。その際にウクライナ地域をカトリック化させる方策として、カトリックと正教とを合同させる「ユニエイト」と呼ばれる宗教の折衷策が採られた。後に自身をウクライナ人と意識する人びとに、ユニエイト信仰が広まっていくと赤尾氏は解説した。
ポーランドとの関係:重用されるユダヤ人、搾取される農民とコサック
<ここから特別公開中>
領土拡大とともに、ポーランド貴族は当時のポーランド東部(現在のウクライナ中・西部に当たる)に私有地を獲得していく。私有地から利益を上げるために重用されたのがユダヤ人。赤尾氏によれば、自分たちを毛嫌いするカトリック教会の影響下にないポーランド貴族の私有地での生活は、ユダヤ人にとっては比較的居心地がよかったという。
一方、ポーランド人はウクライナの農民と非正規コサックに対して不当な賦役労働を課した。この経験がウクライナ人意識の形成に重要な影響を及ぼしたと赤尾氏は説明し、このようなポーランド貴族に支配された地域で、後々民族意識が高まってくると語った。
ユダヤ人はポーランド貴族の「便利屋」として、不動産の管理、経営、徴税請負をはじめ、余剰生産物の売却、資材調達、土地売買の仲介など、さまざまな業務を請け負った。「便利屋」としての活動の中には、賦役労働に服する農民やコサックからの税金の取りたてもあり、ユダヤ人に対する否定的なイメージの形成を助長する面があったと赤尾氏は指摘した。
シュテットル:「失われた王国のミニチュア」
ポーランドにおいて、16世紀から17世紀を通じユダヤ人人口とその居住地は急増する。赤尾氏の示した統計によれば、1569年の時点では24の町におよそ4000人のユダヤ人が居住していたのに対し、1648年には115の町におよそ40000人が居住していた。「中南部のウクライナの町のほとんどが、この時期にポーランド貴族とユダヤ人の賦役労働によって作られた町」。
このユダヤ人が多く居住する町のことを、イディッシュ語で「シュテットル」と呼ぶ。「ゲットーとシュテットルというのは、ユダヤ人が集住しているという点で同じですが、まったく別世界」と赤尾氏は話す。「移動の自由があり、壁もない。そして、何よりかなり少なからぬ町でユダヤ人が人口比的にマジョリティを占めていた」。
町の中心部の市場の周辺に広がったシュテットルでは、ユダヤ人の間で「われわれの町」という共同意識が育まれることとなる。この共同意識は、イディッシュ文学の中に息づき、シャガールの絵画作品にも反映されていると赤尾氏は話す。
シュテットルでは、ユダヤ人と村落の農民との関係も、必ずしも険悪なものではなかった。
「周辺のウクライナの農民たちと接するのは週に2回ほどあった。市場で接触する。みんな顔なじみで、それどころか、(ユダヤ人が)町のマジョリティでイディッシュ語が中心の言語なので、ウクライナの農民たちでさえも、知らない間にある程度イディッシュ語を理解するようになる。
ユダヤ人は西側から流れてくる色々なものを売る。また、珍しいものや情報、そういったものをウクライナの農民たちに伝える。一方、農民たちは穀物などをユダヤ人に売るという関係で、経済的な互恵関係があった」。
自分たちの生きる場所を失った「離散の民」というアイデンティティを背負うユダヤ人とって、シュテットルとは「失われた王国のひとつのミニチュア」だったと赤尾氏は語る。「シュテットルにはシナゴーグ、お祈りの場所、沐浴の場所、そして墓地が備わっていた。だから、宗教的なユダヤ人も世俗的なユダヤ人も、ある種ユダヤ文化の真髄として、シュテットル文化を考えていた」。
しかし、やがてユダヤ人はシュテットルからも再び「離散」していく。「近代化が起きて、シュテットルがどんどん没落して都市部に流れる。さらに国をロシアから移民する。最終的にはポグロム、ホロコーストでユダヤ人がその町から消えていく」。
自分たちの文化が根付いた町を捨て、移民となることを余儀なくされたユダヤ人。「シュテットル的な空間に対するものすごいノスタルジーがある」と赤尾氏。「アメリカのユダヤ人には、ウクライナは自分の先祖がいた場所という意味で非常に思い入れがあると考えられます」。
民族勃興の父は「ヒトラーに次ぐ極悪非道の人物」
17世紀にはポーランド支配に対する反発から、コサックと農民による暴動が頻発するようになる。
なかでも1648年のフメリニツキーの乱では、武装蜂起がポーランド全域にわたって行われた。ウクライナ人にとって、民衆の不満を代弁し、支配層に抗したフメリニツキーは民族勃興の象徴だ。後世には、町の中心部に銅像が建てられ、紙幣には肖像画が描かれた。「最初のウクライナの国家形成の大きな英雄」としてフメリニツキーの姿はウクライナ人に映る、と赤尾氏は言う。
ただ、ウクライナ・ナショナリストのフメリニツキーに対する評価には微妙なものがある。フメリニツキーが1654年にペレヤスーラウでロシア(ロシア・ツァーリ国)と結んだ協定により、ウクライナはロシアから保護を受ける立場となる。結果、「ある種の属国と宗主国」のような関係となったことから、フメリニツキーに対して「不満を持っている極右もナショナリストもいる」のだという。
他方、ユダヤ人はフメリニツキーを、「ヒトラーに次ぐ二番目にひどい極悪非道の人物」として認識してきた。なぜなら、彼が起こした反乱は、ユダヤ人に対する残虐な虐殺行為をともなってのものだったからだ。ヘブライ語年代記の中では「民族滅亡の危機」として後の世代へ継承され、忘れようとしても忘れることのできない災厄の一つとしてユダヤ人の間で記憶されてきた。
極右がユダヤの聖地でデモ
ウクライナ中央部チェルカースィ州にあるウマニという、イスラエル国外では最大のユダヤ教の聖地として知られる都市では、現代でも反ユダヤ主義とウクライナ・ナショナリズムが交錯する。
ウマニには、ユダヤ教敬虔派ハシディズムの一流派であるブレスラフ・ハシディズムを開いたラビ・ナフマンの墓地があり、世界各地から巡礼に訪れるユダヤ人をひきつけてきた。
一方、ウマニでは1768年に反ポーランド蜂起が起こり、これにともないおよそ2000人のユダヤ人が虐殺された。したがって、ナショナリズムの高揚と反ユダヤ的感情がウマニで連結されることは避けられない。ウクライナ史におけるウマニは民族解放のシンボルであるのと同時に、近年では「極右の聖地」化しつつあるのだと赤尾氏は話す。
2000年代前半頃に赤尾氏が耳にした話によると、まるでユダヤ教徒に当てつけるように巡礼の期間を選び、極右たちが反ポーランド蜂起を記念するデモを開催しようとしたという。ただ、ウマニ市当局は双方の接触を嫌い、巡礼期間中のデモ開催を許可しなかった。
ウマニから巡礼のユダヤ人たちがほぼ去った一月ほど後にデモ開催が許可されたが、そこには「黒と赤のネオナチのような旗」を持つ数十人から100人ほどの極右が無言で行進する姿があったという。また、巡礼期間中にやってきた極右もいたとも言われている。
当局の慎重な判断の背景には、極右勢力の伸張を好ましく思わない欧米の有力ユダヤ人たちの存在がある。欧米諸国は、イスラエルを除けば世界最大のユダヤ教の聖地であるウマニでの出来事に関しても目を光らせ、ウクライナ当局は神経を尖らせる。