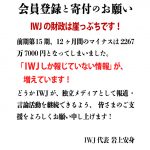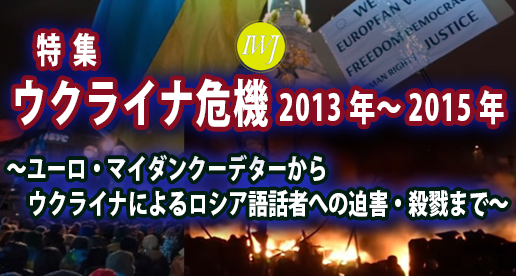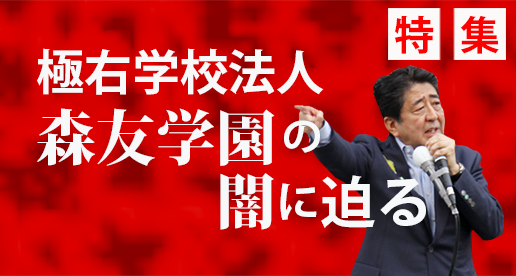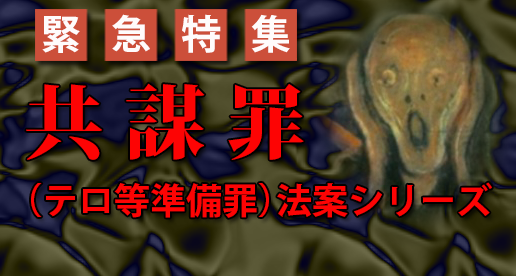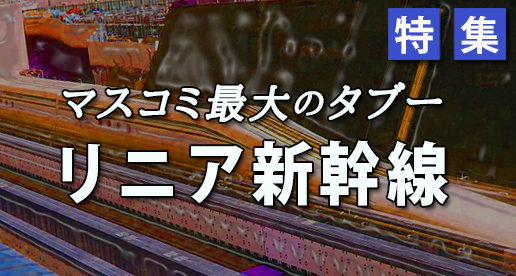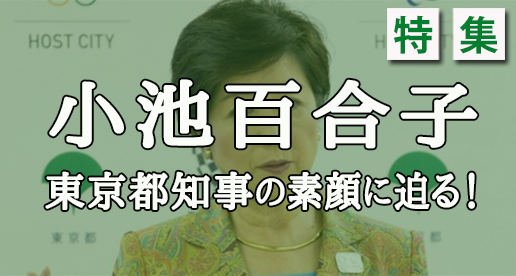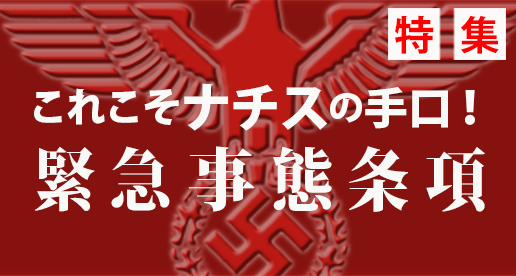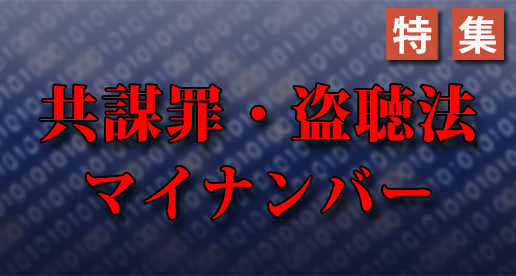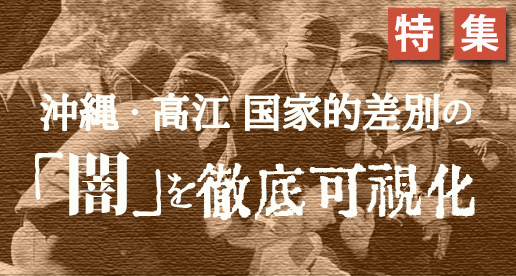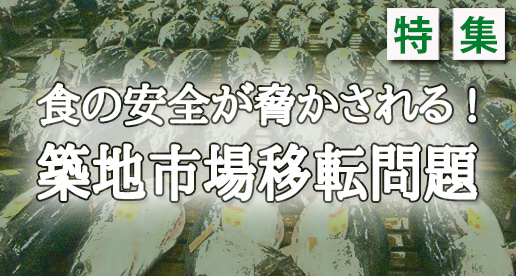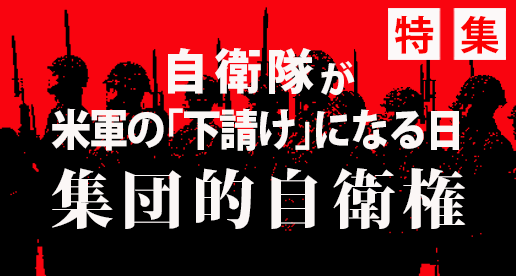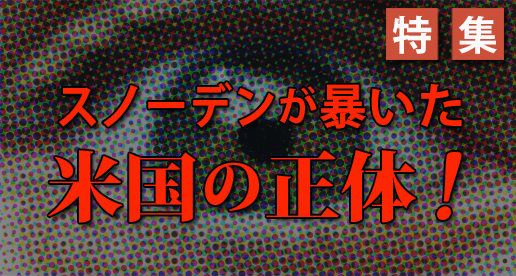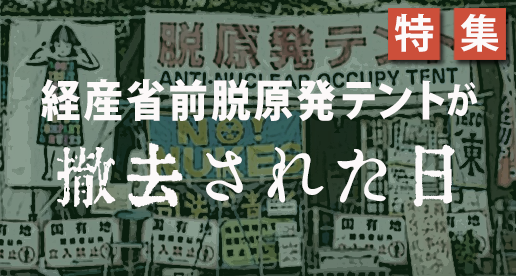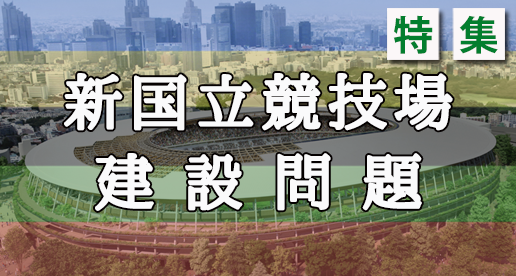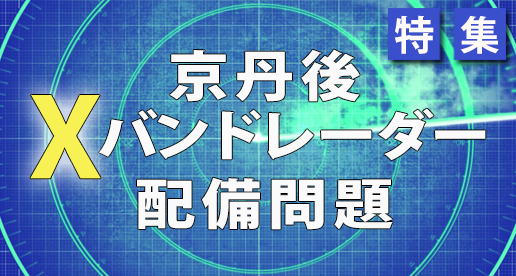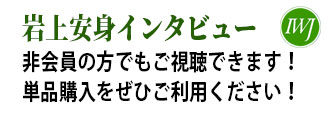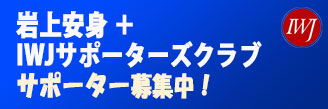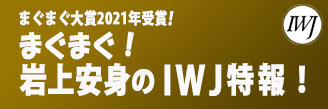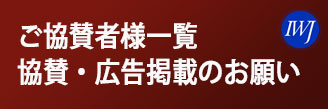- 日時 2024年6月3日(金)17:00~
- 場所 IWJ事務所(東京都港区)
田代氏「(事業をやっていく以上、資金を借りるのは当たり前だが)今のように、実質的に景気後退が起きてると、本業での利益から利払いができない。つまり、それ利払いしちゃうと、他の賃金が払えないとか、そういうことが起きる。
そういう企業のことを、『ゾンビ企業』という、と。言い方が悪いですけどね。そういう企業が、さらに追加で借りなきゃいけない」
岩上「だから、借金が膨らんでいく。低金利だったから、頑張ろうで、(利子で膨らんでいくことを)考えなくてもよかった」
田代氏「ほとんど0%の金利だったから。
おっしゃる通り、元本の返済だけ考えればよかった。銀行からしてもね。それを考えると、一気に(貸した資金を)回収して、倒産させてしまうよりも、存続してもらった方がいいから。追加の融資に応じる場合も少なくないわけですよ。
その構造が、今ここで(崩れていく)。銀行自身が慌てるわけです。前提が完全に狂ってるわけですよね。0%だった長期金利が、1%(に上昇)。しかも、わずか2ヶ月間ですよね」
岩上「そうですね。超低金利時代が長く続いてきました。
17年というと、ある程度高齢の人にとっては単なる『ひと昔』ですけれども、若い人にとっては、かなり大きな生活体験を伴った年月なわけですよね。
(「金利のある世界」の経験がない若い世代の人々が)、単純な『単利』で考えると、『100万円借りたら、毎月1万円ずつ返せばいいんでしょう』みたいな感覚。そうじゃないんですね。『複利』になるんです。
『複利』というものを、金利が複利で膨れ上がっていくことを、本当に実感しながら、元本を削って削って削って。なんとか、氷塊を崩すようにして削って、返し切るということの苦しさを、実感として理解できていない人たちは、少なくないんじゃないかなと思うんですね。(中略)
例えば、これから結婚して、住宅を買おうかなと思っている人。25、6歳から30歳ぐらいまでの人は、ざらにいるわけですよ。そういう人たちは、(複利で膨れ上がっていく借金を、身を削るようにして返していくという)経験がないんですよね」
岩上安身は、身内が不動産を買うというので、金利がつく中で返済するのは、本当に大変なことだと説得している、というエピソードを紹介した。
岩上「日銀による円買い介入。4月と5月に大きく、円安の傾向から円高へ戻したことが2度ありました。
この時には、おそらく介入したんだろうということで、(神田財務官)テレビカメラに囲まれながら、『申し訳ないですが、今申し上げることはできません』と言っていたんですけど。
実際には、4月と5月に2度あった円買い介入は、財務省が5月31日に、4月26日から5月29日の為替介入実績を公表したと。介入総額は9兆7885億円。これがどれぐらいすごいかというと、過去最大だった。
過去最大なんですが、どのぐらいそれで効果が出たのかというと…。
5月29日に、国内債券市場で長期金利の指標となる新発の10年物国債の利回りが、1.07%まで上がってきたんですね。
債券価格が下落したけど、さらに30日には、1.1%に上昇。
2%という数字をひとつ、田代さんは掲げておられる。ある意味の『レッドライン』『イエローライン』だよと言っておられるわけですよ。
多くの人は中小企業で働き、そして自営業をやり、そして住宅ローンを抱えていたりすると。そういう人たちは『2%』という数字を意識しなさいね、と。僕は、田代さんの警告だと思っているんです。意識しておくべきだと。気がつくと、あ、じわじわ金利が上がってきているじゃないか、迫ってきているじゃないか、と(なってからでは遅い)。
すでに、『2011年12月以来、約12年半ぶりとなる高水準』に上がってきている」
田代氏「これね。1日で、要するに0.03ポイント上昇してるわけでしょう。これは、もう驚くべきことですよね。この上昇スピード」
岩上「これはどういうことなんでしょうか。
例えば、日銀が『ゼロ金利政策を解除する』と言いましたよね。解除すると言って、いろいろな政策を、『やめました』といったりしました。『国債の購入だけはやめるわけにいかない』ということではありましたけれども。
でもその後は、フリーになったと言いますか、市場原理でもう動き出しちゃったということですか?」
田代氏「まず『金利って何か』というのを、よく考えなきゃいけなくて。
長期金利とは要するに、『新規発行の10年満期日本国債の利回り』なんですね。これは、ちょっと詳しい話は、経済学や金融論の本で確認していただきたいのですけど、国債でも社債でも、債券の利回りというのは、その債券の価格・取引される価格と、逆向きに動くんです。
つまり、金利がついて利回りが上昇している時は、その債券・国債を含む債券の取引価格は、下落してるんです」
岩上「価格。価値ではなく、価格ですね?」
田代氏「価値というのは、経済や金融の世界では、『価格×数量』のことを、VALUE(価値)と言うんですね。そこにはよく社会学などで考えるような、形而上的な意味は与えてないんです。本当にその『金額』ということなんです。(中略)
そうするとね。これは恐ろしいことを言ってる訳ですよ。つまり、長期金利、『新規発行10年物の日本国債の利回り』が上昇しているということは、国債の取引価格が下落してるわけですね。
つまり、日本銀行は長く、長期金利を0%に抑えたということは、いわば、日本国債の価格をマックスのところまで引き上げたわけです。
そのゼロ金利を解除するということは、金利は上がっていくわけですね。上がってくるということは、マックスまで上げた国債価格が下落することです。それを認めてるってことなんですよ」
岩上「安売りと」
田代氏「安売り。『今よりも、国債は、安い価格で取引されるようにします』と、言ってるわけですよね。『えっ』と思うわけです。
国債というのは、国の借金の証文ですよね。これを買っているのは銀行だけど、銀行がどうやって買っているかというと、預金から買うわけです。(銀行には)預金者がいるわけですよね。だから、預金者は自分は日本国債なんて1枚持ってないといっても、実は、間接的に御自分の銀行預金は国債に化けているわけですね。
その(自分の銀行預金が)化けている国債の取引価格が、下落し始めているんです」
岩上「恐ろしいですね」
田代氏「そのことが、『金利が上昇する』という意味なんですね。しかも、これが『日銀の想定を超えて止まらない』ということは、国債の取引価格が想定よりも早く下落しているんですよ。
下落することは覚悟しているから、ゼロ金利は解除したんですけど。それが『思ったよりも早く下落してる』ということは、端的に言って『日本国債の売り圧力が高まってる』わけです。
日本国債を持っている人が、売りたいと(思っている)。一番思ってるのは、日本銀行なんです、実は。だって、存在している国債の半分ぐらいは、日本銀行が持っているんだけど、それ以外にも持ってるところはある。
そこが、『国債を、まだ高いうちに売り抜け抜けよう』と考えたら?
売り出す量が変わりますよね。そうすると、国債を売る側、つまり国ですよね。それが国債の発行のペースを変えない限り、それは国債価格を押し下げますよね。
そんなに早く国債金利が上がっていくということは、国債価格が下落するわけですよね。だったら『早く売らなくちゃ』。
まあ、大きな資産だから、例えば計画があって。『今年は何100億円。来年は何100億円売っていく』と考えていたのが、『いや、来年の分も今、売っちゃいましょう』となると、ますます早く価格は下落しますよね。それは、現象としては、ますます早く金利が上昇していくわけです。
ただ、『金利が上昇する』と聞くと、『それで銀行の預金金利は増えて、ウハウハになる』と」
岩上「預金者にとっては、どうなんです?」
田代氏「だけど、預金者も、預金してる預金の入った先のかなりの部分は国債なんです。
だから日本銀行だって、どうして国債を買っているかといったら、それはたどっていけば、預金なんですよ。銀行にあった預金が、さらに日本銀行に預金されていて、それを担保に(国債を)買ってるわけですよね。その重要な入った先の国債の価格が今、『日本銀行の想定を超えて下落してる』と。
しかも、2011年12月ですよ。『あっ』と、思うわけですよね。いわゆる『アベノミクス』、いわゆる『異次元金融緩和』。日銀の言葉を使えば、『量的質的金融緩和』は、2013年4月4日から始まったでしょう。その前の数字まで、来てるんです、もう」
岩上「自民が『デフレデフレ』と、民主党の政権を批判していた時代に戻っているっていう」
田代氏「本当に人類の経済史上に残る、破天荒な金融緩和によって、長期金利をゼロまで押し込んだわけですよ。で、それが、全部、今、キャンセルされたということですね」
岩上「なるほど。やってきたことがすべて無駄になった、と」
田代氏「その当否は別として。現状は、おっしゃる通り、世界に見られない(日銀のゼロ金利政策が、キャンセルされた)。
通常、中央銀行は短期の金利、いわゆる『翌日物』とか、短期の金利を操作することで、間接的に長期金利に影響を及ぼそうとするわけだけど、日本銀行はダイレクトに長期金利そのものを、ゼロに引き下げたわけです。
それを今、解除したわけですよね。それは上がるんだけど、その上がり方が、想定を、多分超えたんだろうと思うんですね。
まさかそんなことは、言いませんよ、植田総裁も。言った瞬間に、日本国債を持っている人は、みんな売りますから。そうすれば、国債大暴落ですよね。
だから、冷静な顔をして、冷静にお話しになってるんだけど、大変なことですよね」