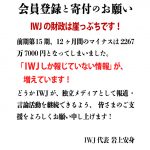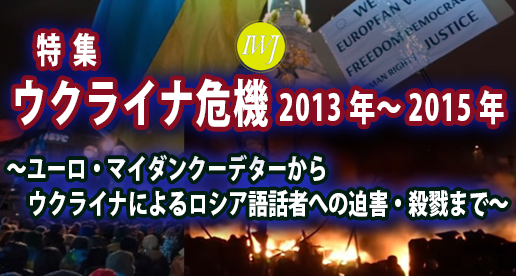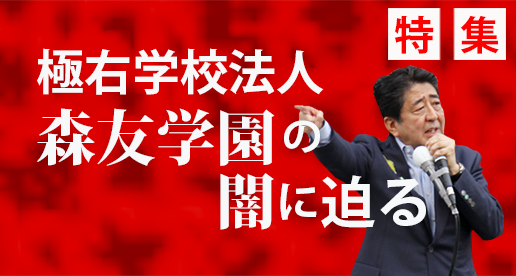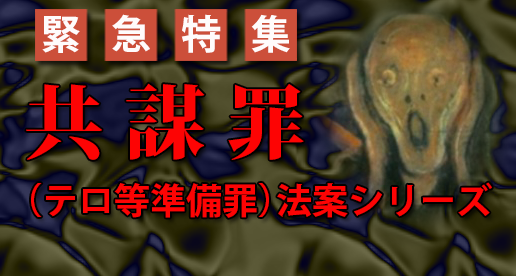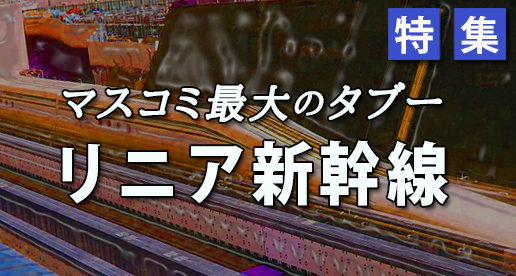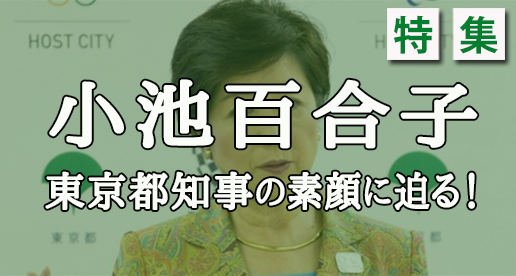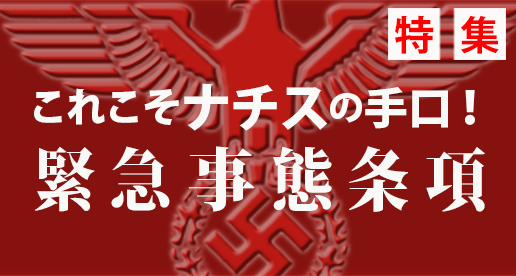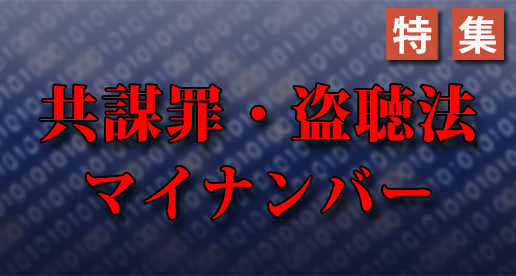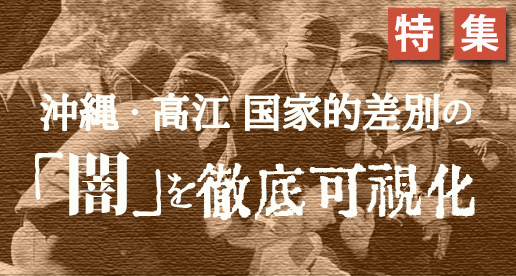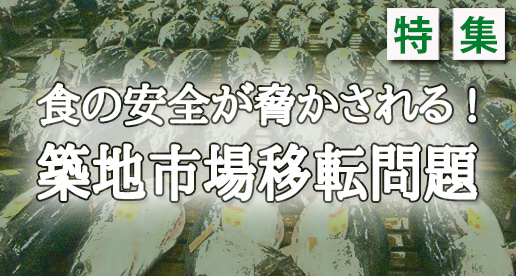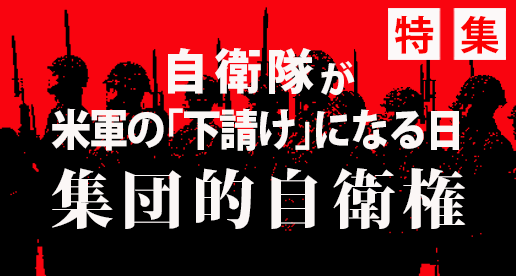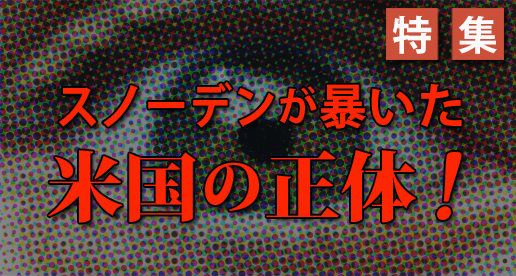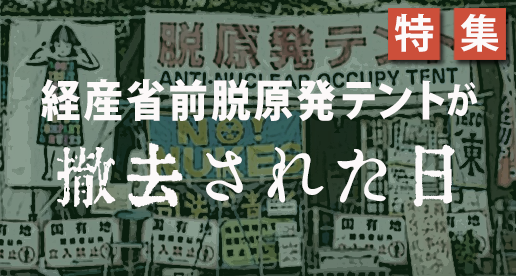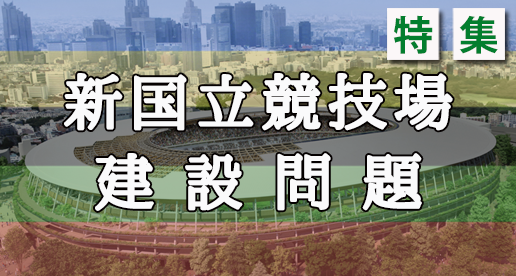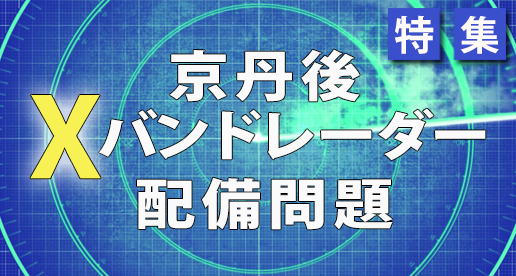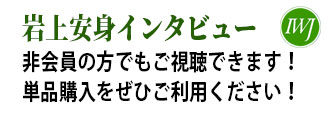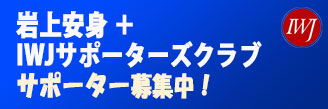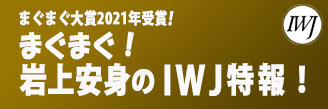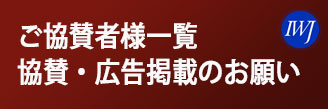2025年6月10日、「岩上安身によるインタビュー第1195回ゲスト エコノミスト・田代秀敏氏 第2弾 前編」を撮りおろし初配信した。
米カリフォルニア州ロサンゼルスでは、トランプ政権による不法移民の取り締まりに対する住民の抗議をめぐり、トランプ大統領は、カリフォルニア州のニューサム知事や、ロサンゼルスのバス市長(ともに民主党)を「職務を遂行できない」と、無能呼ばわりして、非難し、州知事の権限である州兵の動員を、州の要請なしに行い、暴動の鎮圧にあてた。
これに対してカリフォルニア州は、トランプ大統領による州兵の動員を違法だとして、裁判所に提訴した。
しかし、米軍は、ロサンゼルスへ海兵隊も派遣し、トランプ大統領は、ニューサム知事の逮捕も示唆した。
こうした米国社会の崩壊について、田代氏は、「アメリカの現状を考えると、権力の側が、こういう非常事態に打って出るというのは、わからないでもない。それくらい、非常に状況が切迫してます」と、指摘した。
田代氏は、「アメリカの財政は、もう赤信号が点灯している」と述べ、米連邦議会連邦予算局が公表した、米国の債務残高が、GDPの何パーセントにあたるか、ということを予測したデータから作ったグラフを、パワーポイントで示した。
第2次世界大戦の翌年(1946年)にピークで、106%だった米国の債務は、削減に努めた結果、20%台まで減り続けたが、1980年の石油危機に対する財政出動の結果、増加に転じた。
その後、クリントン政権時代には、経済が好調だったことと、財政引き締めにより、いったん下がり始めたが、2000年のITバブル崩壊で、再び増加に転じた。
そして、2008年の米国発の世界金融危機からは、急激に上昇した。
田代氏は、「アメリカの金融機関の不良債権を、どんどん買い取っていくとことをやった結果、連邦政府の債務になっていった」「これが(GDPの)80%までいったところで、次にパンデミック対応で、一気に100%(99%)になった」と解説した。
その上で田代氏は、今後の見通しについて、次のように述べた。
「トランプは、減税すると言っているんです。社会福祉はカットすると言ってるけれど、軍事予算を増やすと言ってますよね。
いろんなことを考えると、ずっと上がっていて、2054年には166%に達するでしょう、というのが、連邦議会の連邦予算局(バジェットオフィス)の公式予測です。
でもこれ、実は今から見たら、楽観的。今、トランプが言ってることは、もっとめちゃくちゃだから、それからすれば、おそらくもっと、こう(急激に)増えます」。
その理由について、田代氏は、「トランプは、関税で財政を増やした分、減税するというシナリオだったけど、『トランプ関税』自体が、今、止まっている(90日間の猶予期間を設けた)」と指摘し、次のように続けた。
「だけど、これだけ債務があると、利払いの問題がある。
増税をしないで利払いをするためには、新たに利子を払うためだけに、国債を発行しなければならなくなる。
トランプは、『増税はしない』と言っているのだから、必然的に、もっと速いスピードで、これ(GDPに対する債務残高の割合)が増える」。
さらに田代氏は、米国の債務利払い費と防衛費の増加をグラフで示し、以下のように続けた。
「驚くべきことに、今、あの巨大なアメリカ軍を維持している防衛費よりも、すでに2022年時点で、(元本ではなく)債務の利払い費の方が大きいんですよね。
これは、グラフの形状を見てわかるように、(データがまだない)2023年以降も、どんどん開いていきます。(中略)
アメリカは、特に2022年以降、ものすごいインフレーション圧力に抗するために、どんどん金利を引き上げましたよね。
当然、それは、国債の利払いの金利も増やしているわけです。(中略)
やすやすと、金利は引き下げられない。でも、金利を高止まりさせる限り、債務の利払いは、どんどん増えていく」。
田代氏は、「これだけの利子を払っていても、元本が減っているわけではない。むしろ、利子を払うために、新たな国債を発行することで、元本が増えている」と指摘した上で、「ここまで元本が大きくなってしまうと、少々金利を下げたからといって、債務の利払いは減らない」と解説した。
田代氏は、「日本は、ほぼゼロ金利政策をとったにもかかわらず、それでも債務の利払いは増えてるんです。それは、元本が大きすぎるからです」と述べ、「アメリカは、それに輪をかけているような状態」だと、認識を示した。
田代氏は、米国の2022年時点の防衛費が7300億ドル(約105兆円)であることを指し示し、「これで戦争をやったら、たちまち1兆ドル(約145兆円)を超える」と述べ、「それが国家債務として、新たな元本を増やし、利払いを増やす。その利払いが1日でも遅れ、1ドルでも足りなければ、デフォルトなんです」と、深刻さを訴えた。
さらに田代氏は、米連邦準備制度(FRS)が発表した、米国債の10年満期の市場利回りのグラフを示した。
それによると、1970年代から1980年代初頭にかけてインフレが起きた米国では、15%を超える高金利で、インフレを抑え込んだ。これをピークに、その後は2020年まで金利が下がり続け、それに伴って米国債の市場価格は、上昇し続けた。
しかし、2020年にパンデミックが発生すると、米国は膨大な国債を発行し、それをパンデミック対策にあてた。このため、2020年から、米国債の10年満期の市場利回りは、急激に上昇に転じている。
これに対して岩上安身は、「上がったといっても、5%ほど。素朴な疑問として、1980年代当初の15%ぐらいまで上げればいいんじゃないかと思う人もいるんじゃないか。当時のアメリカと、今のアメリカは、何が違うのでしょうか?」と質問した。
それに対して田代氏は、次のように解説した。
「まず、世界経済における、アメリカの地位が、全然違います。
この時(1980年頃)は、アメリカは、圧倒的な経済超大国だし、アメリカの製造業も、極めて活発だったわけですよね。
(先程の米国債務の対GDP比率を予測したグラフでは)ボトムなんです。だから、超高金利政策が打てたんです。
今、あれをやったら、その瞬間に、もう即日、アメリカ国債はデフォルトします」。
田代氏は、「米国発の世界金融危機(2008年の、いわゆるリーマンショック)が起きた時でさえ、(米国債務の対GDP比率は)39%です。それが2020年で99%、現状はもっと悪くなっているわけです」と述べ、「しかも、トランプは、減税すると言っている」と強調した。
2020年から米国債の金利が上昇しているということは、債券自体の価格は下がってることを示している。米国債を世界一大量に保有している日本は、すでに「含み損が発生している」と指摘した田代氏は、「アメリカの10年国債、長期国債は、40年間続いていた価格上昇から、価格下落へと、トレンドが変わった」のだと解説し、「アメリカの、世界に対する覇権を支えている財政システムが、大変動を起こしているということです」との見方を示した。
日本は少しずつ国債を売ってはいるものの、いきなり大量に売れば、それこそ米国債の暴落を引き起こしてしまう。米国とともに「心中」しかねない状況に、日本もあるというのである。
国債は、すでに大量に発行されている。これ以上、発行していけば、インフレとなり、その際は、流動性を回避するために増税すればいいと、MMTの教祖の一人、ステファニー・ケルトン氏は述べている。
しかし、「増税するという候補は選挙で落ちてしまう」と田代氏は述べ、日本も米国も、財政状況は危険水域にあることを指摘した。
米国から自立する、ということは、安全保障面だけでなく、経済面も同じである。
急激な変化によって、クラッシュしないように、ゆっくり、慎重に、しかし、確実に、米国からの自立をしてゆく必要がある。