「パリ連続テロ事件と『イスラム国』の衝撃 その後の中東と日本」と題した公開研究会が2015年3月28日、東京都千代田区の中央大学駿河台記念館620号室において、中央大学人文科学研究所研究会チーム「批判的比較文化研究」の主催で行われた。
講師として、立教大学大学院特任教授の西谷修氏(フランス思想・哲学)が「シャルリ・エブド事件はフランスの9・11か」、千葉大学教授の酒井啓子氏(中東・イラク政治学)が「イラク戦争後の中東、アルカイダから『イスラム国』へ」、日本女子大学教授の臼杵陽(うすき・あきら)氏(現代中東・ユダヤ研究)が「背後にあるイスラエル・パレスチナ問題」を、それぞれのテーマで複眼的視点から、中東・ヨーロッパ情勢を語った。
司会を務めた中央大学研究員の三浦信孝氏(フランス文学・思想)が、まず、「フランス知識人界の思想地図」と題して、フランスから見た世界史的事件は、1991年の湾岸戦争へのフランス軍派兵から12年ごとに起こっているとし、2003年のイラク戦争、2015年のシャルリ・エブド襲撃事件を数えた。フランスでは、9.11も3.11も単なる他国の「tragédie(悲劇)」以上でも以下でもなかった、とした上で、「Je suis Charlie(私はシャルリ)」とは「 Nous sommes Français(私たちはフランス人)」、つまりは共和制理念の再確認行為でしかなかった、と指摘した。
西谷氏は、「私はシャルリ」を、操作されたキャッチフレーズであるとし、表現の自由の仮面の下には、イスラームを反ユダヤ主義と等号で結ぼうとする隠れた意図が働いている、と指摘。シャルリ・エブド襲撃とモンルージュでの女性警官射殺、ユダヤ系スーパーへの立てこもりは、一般にそう信じられているほどには連動しておらず、それらの事件の容疑者であるクアシ兄弟とアメディ・クリバリの背景までも含めて、まるで「ひとつの出来事」のようにモンタージュされているのではないかという疑念を、フランス思想界や政界の動きと照応させながら語った。
また、犠牲者追悼の1.11大行進に参加したイスラエルのネタニヤフ首相の真意が、フランスのユダヤ系住民のイスラエル大移住を勧誘する目的にあったことも示唆した。
中東政治学を専門とする酒井氏は、同じく1.11のシャルリ大行進と表現の自由とは無関係と確認しつつ、「自由」が切実だった人々の存在も指摘。一方、中東でのメルクマールはモスル陥落の「2014.6.9」であり、それ以降、中東は本質的に分極化して、誰も手を付けられない戦争状態に陥ったとし、それを世界の底が抜けた「メルトダウン」と表現した。
また、アメリカの無謀な介入と無責任な撤退がこの事態を招いた、と見ることは状況の単純化に過ぎず、同時に、もともと宗派対立があったからとする説は結果論であり、宗派対立という見方自体が政治ツールであるとした。その上で、9.11よりもはるか以前の1979年に、イラン革命、ソ連のアフガン侵攻、単独和平合意によるエジプトの孤立などによって一斉に作られた火種に、「『イスラム国』がスイッチを入れまくっている」現状を多岐にわたって解説した。
イスラエルの選挙視察から帰国したばかりの臼杵氏は、ほぼ敗北が予想されていたネタニヤフ首相(右派政党リクード)の予想外の勝利は、選挙当日、「アラブの連中が投票所に駆け付けている」という、ネタニヤフ首相の流したネット情報が右派票を吸い上げた結果とし、イスラエルでの人口比20パーセントのアラブ人の存在を逆手に利用したネタニヤフ首相が、ほぼ、フリーハンドを得てしまった現状を憂慮した。
アラブ世界の混乱は、イスラエルには必要不可欠であり、ネタニヤフ首相の人種主義は、「パレスチナ人は皆、親ナチだという暗黙の規定」をパレスチナの大ムフティーだったアル=フサイニーの、第二次世界大戦中の行動から敷衍した図式だ、と臼杵氏は解説。「アラブ諸国がユダヤ人を追い出したので、われわれは『交換に』パレスチナ人を追い出す」という主張を正当化している背景を詳述した。
質疑では、1. イスラームの中にテロリズムを正当化する教義は存在しているのか、2. テロリズムの定義とは何か、3. この状況下で、今の日本をどう考えたらよいのか、という3点が主に会場から問われた。
1. に関して酒井氏は、イスラームに限らず、あらゆる宗教の聖典は暴力を容認する記述を含む点を指摘、真の問題はテキストからそれを引き出してくる人々の存在である、とした。臼杵氏は補足する形で、恣意的な聖典解釈がパンドラの箱を開けてしまったのが今の中東だ、と述べた。
2. に関して西谷氏は、定義が曖昧な観念であるほど、政治的なレッテル貼りには好都合であること、したがって、積極的には定義しない流れの中で濫用されていることを指摘し、酒井氏は、「党派主義」など、他にも多くの言葉が無自覚に広範な殲滅を正当化している現実に、注意喚起した。
3. に関しては、西谷氏が、このタイミングでの安倍総理の中東歴訪を「確信犯的なトンチンカン」と位置づけ、戦争とは、今やメルトダウンに身を沈めることをしか意味しないとし、酒井氏が、現実に自衛隊のイラク派兵以降、「何かあったらどうするんだ」のメカニズムが、日本と中東の民間交流を止めていたことを、その背景として解説した。
また、三浦氏は、戦争行為の自己正当化の図式が「文明対野蛮」の構図で語られる中、「野蛮」側から「文明」側への脱出の悲願を、この「テロとの闘い」に手を挙げることで果たしたい、現政権のもくろみを論難した。
- 講演 西谷修氏(立教大学特任教授、元東京外国語大学教授)「シャルリ・エブド事件はフランスの9・11か」
- 講演 酒井啓子氏(千葉大学教授)「イラク戦争後の中東、アルカイダから『イスラム国』へ」
- 講演 臼杵陽氏(日本女子大学教授)「背後にあるイスラエル・パレスチナ問題」
- 司会 三浦信孝氏(中央大学名誉教授)「フランス知識人界の思想地図」
- 日時 2015年3月28日(土)13:00〜16:00
- 場所 中央大学駿河台記念館(東京都千代田区)
- 主催 中央大学人文科学研究所 研究会チーム「批判的比較文化研究」(詳細)
フランスから見た3.11は「tragédie Japonaise(日本型の悲劇)」に過ぎない
※以下、発言要旨を掲載します ※内容の重要性に鑑み、ほぼ文字起こしに近い読みやすくしたテキストを掲載しました!
三浦信孝氏(以下、三浦・敬称略)「1月のシャルリ・エブド襲撃事件の後、雑誌『ふらんす』と『現代思想』が特集を組んでいるが、前者は、もっぱらフランス視点で論じているのに対し、後者では、約3割が中東論である。私自身、フィールドが現代フランス研究で中東には暗いが、比較文化論の視点からシャルリと中東は切り離せないものと感じ、この公開研究会を企画した。
1989年の冷戦崩壊後、あくまでフランス視線から見ると、1991年のミッテラン政権による湾岸戦争への参戦ということが、世界史的な出来事として刻まれている。次いで2003年のイラク戦争、その前に2001年の9.11があり、ブッシュ米大統領がテロとの戦いを謳い上げてはいるが、右派のシラク政権はこの戦争に正面から反対し、いわゆる『米仏対立』の引き金になった。この間が12年、空いている。
1996年にサミュエル・ハンチントンの『文明の衝突』が出て、米欧は一括りにされていたが、この米仏対立、あるいはヨーロッパ内部での、古いヨーロッパと新しいヨーロッパの対立は、ハンチントンの前提への明白な反証になった。ここでロバート・ケーガンは、『弱さ/ヴィーナス/カントのヨーロッパ vs 力/マルス/ホッブスのアメリカ』という図式を作ってみせたが、エチエンヌ・バリバールは『媒介としてのヨーロッパ』や『哲学的市民権』といった視座から、このネオコン思想にもっとも強力な反論を展開した。
9.11の直後、2002年に、エマニュエル・トッドの『アメリカ帝国の終わり』Après l’empire(邦訳題『帝国以後』)の刊行をうけて、西谷氏、板垣雄三氏、最上俊樹氏とトッドを囲む討論会を企画したが、トッドの都合で実現できず、今回の公開研究会はその延長線上でとらえている。
シャルリ事件は、フランスにとって奇しくもまた、イラク戦争から12年後の今年(2015年)に起こったわけだが、日本では、その前に3.11があった。しかし、フランスの視線で、これは世界史的事件とは見られず、前年のハイチ大地震を『malédiction Haïtienne(ハイチ型の呪い)』と呼んだように、単に、『tragédie Japonaise(日本型の悲劇)』でしかない。3.11直後のサルコジ大統領の訪日でも、2013年のオランド大統領訪日も、『この事故はフランスでは起きない』ことを大前提にして来ている。右も左も原発推進を向いているフランスにとって、日本は単に原発同盟国なのだ。安倍首相はそのことを、原発再稼働へのテコとして使った。
シャルリ事件に際して、『Je suis Charlie(私はシャルリ)』または『 Nous sommes Charlie(私たちはシャルリ)』を全世界的に掲げたフランスは、3.11では誰も『Je suis Japonais(私は日本人)』とは言わず、9.11ではル・モンド紙が唯一、『Nous sommes tous américains(われわれは皆アメリカ人である)』という社説を出しはした。ただ、その大元は、1963年にケネディ米大統領がベルリン訪問の際に、『Ich bin ein Berliner(私はベルリンの一市民だ)』と言ったところまで、政治的標語のタイプとして遡れるだろうと思われる。
しかし私には、『l’esprit de onze Janvier(1.11の精神)』とまで標語化された『Je suis Charlie』の背後には、『Nous sommes Français(私たちはフランス人)』という形での『Union Nationale(国家的統一)』、つまり共和国的価値、『laïcité(宗教上の無所属性、政教分離)』、表現の自由といった諸々の価値観の再確認を通じた『Union Nationale』がもくろまれていることが見え透いて、とても、その輪に加わる気にはなれなかった」
出来事のモンタージュの先にある「イスラーム=反ユダヤ主義」の図式
西谷修氏(以下、西谷・敬称略)「シャルリ・エブド事件が、ひとつの集約点となったにはせよ、今の問題は、ほんのここ四半世紀ほどの問題である。実は2001年11月30日、すべての報道が『愛子様ご誕生』一色に染まっている裏で、『アメリカは何故狙われたのか』という討論番組を、深夜のNHK-BSで放送するための収録をしていたのが、今日呼ばれたこの3人だった。同じ顔ぶれで、今日は『次の段階に入ったテロとの戦争』を語ることになる。
『私はシャルリ』とは、メディアの中で使い回されるキャッチフレーズでしかなく、だから、しばしば『これはフランスの9.11か』という言い方と組み合わされるが、この組み合わせ自体が罠であり、実際に起こったことから離れて、単に反イスラームの運動、たとえばドイツのPEGIDA(西洋のイスラーム化に反対する欧州愛国者)などと直結してしまう。フランスでは国民戦線が、こういう動きを吸収してしまっている。
私は、そもそもテロリズムを『テロ』と呼ぶような、日本語での簡略化の仕方自体を、下卑た用語法であり、日本語崩壊の徴候と感じるので、『テロとの戦い』と言われ始めた当初から使わないようにし、だから、今度の事件も『パリ連続襲撃事件』と呼んでいる。では、その『パリ連続襲撃事件』とは実際、何だったか。
まず、シャルリ・エブドの襲撃があった。次に、ユダヤ系のスーパーでの立てこもり事件が起きた。この2つは、明らかにまったく違う意味合いの事件であるのに、これらが『私はシャルリ』に吸収された。ここが、すでに疑問である。
『私はシャルリ』というスローガン自体は自然発生的なものだったとしても、フランス全土で370万人もの人を、実際に動かしたのは間違いなくオランド側近のPR担当者だろう。テロリストと名指しされたのは特別な人間ではなく、移民の2世、3世の『そこいらのお兄ちゃん』であり、フランス人は皆、いつかはこういうことが起こるかも知れないという漠然とした恐怖感を持っていた。それが現実化し、暴力への漠然とした恐怖が、このスローガンに操作的に吸収されたと見てよい。本音の声は『こんなことが起こる社会は嫌だ』のはずだった。
クアシ兄弟の犯行は、ただ、イスラーム攻撃に対する復讐でしかない。この野蛮な行為を『私はシャルリ』によって、表現の自由に対する攻撃にすり替えたのは、あまりにもフランス的なやり方だった。本質を隠しながら感情を活用し、文明的な共和制原理の下で『フランス人』である自分を高みに置く。オランドは、文明の代表として、世界中の要人と共に堂々と野蛮を非難する。野蛮vs文明。
アメディ・クリバリのほうは、まず、モンルージュで女性警官を射殺する。それから東へ移動して、パリ郊外のユダヤ人商店に立てこもる。クアシ兄弟に加担する陽動策でもあっただろうが、まず『治安』を攻撃した人間が『反ユダヤ主義』だという、もう一方の図式ができ上がる。クリバリは『イスラム国』と関係があるとされ、『イスラム国』はイスラエルとの関係も、また取り沙汰されている。
クアシ兄弟とクリバリの犯行を一括りにすれば、『野蛮なイスラーム過激派+反ユダヤ vs 文明的な西洋+ユダヤ』、つまり、アウシュビッツ以後、イスラエル建国以後の図式が出てくる。多少の共通性や互いの連絡程度はあっても、背景の違う2つの犯行を、誰かが電話1本でモンタージュした可能性もあるし、そもそも、『私はシャルリ』によって、この一連の犯罪を回収すること自体がモンタージュでもある。
こういう事件を理解する上で、犯人はどのように生み出され、かつ、それはどのような論理へと回収されていくのか、この双方を見逃してはならない。
ロベスピエールが最初のテロリストだった、と見るべきではなくて、彼は恐怖政治を敷きはしたが、彼が断頭台へ送られた後から、残党狩りをした側が、その虐殺を正当化するために、『ジャコバンはテロリスト』というレッテルを初めて使ったのだ。『テロリスト』の呼称は、事の初めからレッテルだった。
今回の1.11大行進に参加すると最初に言ったのは、実は、極右のリーバーマンだった。『パレスチナを根絶やしにするには、まず女子供を殺せ』と平然と主張しているような者が、文明側イスラエルの代表ではまずいと見て、ネタニヤフ自らが出向いた。
ただ、ネタニヤフは、オランドをシナゴーグへ連れて行って、キッパー(ユダヤ教徒の帽子)を被らせ、フランスのユダヤ化を印象付けた上で、フランス国内のユダヤ人たちに、イスラエルへの移住を大いに推奨して帰っていった」
「中東はメルトダウンを起こし、われわれの知っていた中東は、もうそこにない」






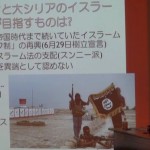























「中東はメルトダウンを起こし、われわれの知っていた中東は、もうそこにない」――中東・フランスの研究者らが警告、日本は「スターリンもヒットラーもうらやむ『自粛』体制の国」 http://iwj.co.jp/wj/open/archives/240787 … @iwakamiyasumi
事実上、言論の自由がない国である。
https://twitter.com/55kurosuke/status/606747595910742016