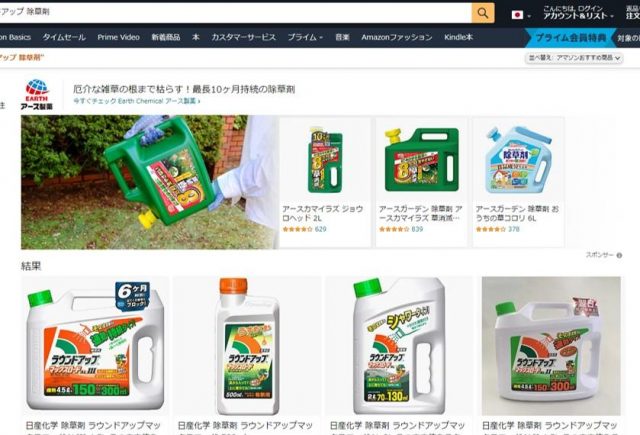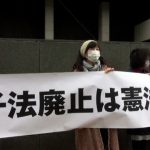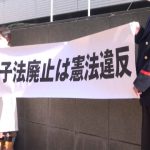2022年6月3日、「種子法廃止等に関する違憲確認訴訟」第7回口頭弁論が行われた。
同訴訟は、「種子法」を国が廃止したことは、憲法違反だとして、全国の農家や消費者らが国を相手取り、提訴したものである。
本記事では、午前中に行われた原告本人尋問をレポートするが、これは、採種農家、一般農家、一般消費者の各代表の3人の原告が、原告側と被告側の各弁護団の尋問を受ける場である。
そして、この尋問を通じて、種子法廃止による、原告の憲法上の権利侵害が認められれば、ただちに種子法復活へとつながる、非常に重要な尋問に他ならない。
採種農家の菊地富夫氏は、「種子法が時間を使って審議されず廃止されたことに、大きな怒り」を感じたと述べ、「ウクライナ問題での防衛費増大より、農業に予算を使い、自給率を高める方が大切ではないか」と訴えた。
一般農家の舘野廣幸氏は、「県からの原種購入価格は3倍に」上昇したと指摘。「種は農業の命。農業が成り立たなければ、国民の命も保障できない。だから種子は国の責任で守るべきだ」と述べた。
消費者代表でパルシステム東京顧問の野々山理恵子氏は、「種子法廃止で大企業が種子生産を独占し、多様性が失われれば、飢餓につながる」と危惧を表明。さらに「大企業が開発する遺伝子組み換え作物の種子は、農薬とセット販売される」と安全性に強い懸念を示した。
これら原告の、種子法復活を望む、強い意見表明に対して、国側からの反対尋問は、ほとんど行われなかった。
詳しくは、記事本文を御覧いただきたい!

▲種子法は米麦大豆を対象とする。写真は10月初旬の稲穂。(Wikipedia, Sphl、写真はイメージ)
※本記事は「note」でも御覧いただけます。単品購入も可能です。
https://note.com/iwjnote/n/n434fe6628ab3
<ここから特別公開中>
この尋問を通じ、種子法廃止による、原告の憲法上の権利侵害が認められれば、ただちに種子法の復活へ!
2022年6月3日、「種子法廃止等に関する違憲確認訴訟」第7回口頭弁論が東京都千代田区の東京地方裁判所で行われた。裁判長は春名茂氏、裁判官は横井靖世氏、下道良太氏である。この口頭弁論については、前日、司法記者クラブで原告側弁護団が記者会見を行っており、IWJが取材、ご報告している。
本記事では、口頭弁論の午前中に行われた「原告本人尋問」についてご報告する。
同訴訟は、戦後、良質な農産物の種子を生産してきた「主要農産物種子法」(種子法)を国が廃止したこと(2018年4月1日)は、憲法25条の生存権の保障等に抵触するとして、全国の農家や消費者ら約1300人(その後順次増加)が国を相手取り、2019年5月24日に東京地裁に提訴したものである。
請求内容は、「主要農産物種子法を廃止する法律」の違憲無効の確認、採種農家、一般農家、消費者が種子法にもとづく活動を行う地位の確認、原告への損害賠償(各1万円)を求めている。
原告本人尋問は、採種農家、一般農家、一般消費者の各代表である3人の原告が、原告側弁護団の尋問と被告側弁護団の反対尋問を受ける場である。
この尋問を通じて、種子法廃止が、3人の原告が種子法にもとづいて行ってきた種子や農作物の生産、消費を妨げ、憲法上の権利を侵害しており、原告は従来通りの活動を行う法的地位にあることが認められれば、種子法廃止の違憲性が認められることになる。
原告弁護団の平岡秀夫弁護士(元法務大臣)は、それが、ただちに種子法復活につながると、前日の記者会見で述べた。たいへん重要な意味を持つ尋問である。
採種農家の菊地富夫氏「種子法が時間を使って審議されず廃止されたことに、大きな怒り」「ウクライナ問題での防衛費増大より、農業に予算使い自給率を高める方が大切では」!
最初に、採種農家の菊地富夫氏が、原告弁護団の尋問を受けた。
尋問によれば、菊池氏は山形県の白鷹町で、県の指定圃場(菊地氏6ヘクタール所有)で、稲の種もみを作っている。20歳から45年間、採種農業に携わる。
現在の品種は山形県の奨励品種「はえぬき」と「つやひめ」で、年間約500キログラムの種を生産。生産した種は、県の外郭団体である産米改良協会に出荷、そこから一般農家に渡る仕組みだ。種もみ生産のための原種は、協会を通じて山形県から毎年購入する。

▲もみ米。(Wikipedia、Green、写真はイメージ)
種もみ供給は、一般農家の死活問題に直結するため、採種農家は、一般農家に比べ、自然災害があっても契約数量を確実に作る必要をはじめ、健全な充実した種、また混入のない純粋な品種の種を作る必要がある。
したがって土づくり、多収を望まず、強く育てる減肥栽培、集約管理をはじめ、農業機械の頻繁な分解掃除など、特別な手間暇をかけるという。こうした種子生産の大変さを勘案した価格設定が協会により行われることで、「なんとか続けてこられた」と、菊地氏は語った。
裁判に原告として参加した思いを聞かれた菊地氏は、「優良な種子を生産する種子法が、国会でちゃんと時間を使って審議されたこともなく、廃止されたことに、大きな怒りを感じる」と語った。「自分の仕事がなくてもいいというか、否定された」と感じ、「国のやっていることを、司法の場で」明らかにしたい思いがあったという。
これまで厳格な公的管理がされてきた原種が、種子法廃止で民間の管理にとってかわられることで、多収性の売れる種中心に生産され続ける可能性について聞かれると、「今よりも農業がしづらくなり、種もみの値段も上がる可能性がある、(日本の食料)自給率ももっと下がる可能性がある」と述べた。
原種を県が作らず、民間が作るようになると、採種農家を続けられるかと聞かれると、「なってみないとわからないが、トウモロコシや他の野菜の種が、あっという間に外国産が横行している現状からは、民間の例えばグローバル企業等が私に(生産を)頼むことは考えにくい」「戦略物資である種もみが、民間あるいはグローバル企業に行くというのは、この国にとっては不幸なことだと思う」と語った。
菊地氏は、山形県の種子条例制定の運動に関わった。「国が種子法をあっという間に廃止したことに対する怒りがまずあり、なんとしても山形県では、ちゃんとした種の生産できる仕組みを残したいという思いがあった」という。
山形県では、県条例を作ることを進めていた結果、種子法同等のしっかりした条例が作られ、現在は種子法廃止以前と同じ生産が行えているという。
しかし条例は、社会的状況の変化や、知事や県議会議員の交代で、いつどう変化するかわからず、国からの予算もなくなる可能性もある懸念を述べ、「一番大事なのは、種子法廃止を撤廃して、種子法を復活させること」だと訴えた。
最後に菊地氏は「今回コロナで分かったことは、国民にとって、命にかかわる食料は、国内で自給しないと、とても不安だということ。マスクでさえ(品薄で)大騒ぎをし、ワクチンも国内にあったら、もっと安心できた。命にかかわる食料の自給力を増やすことが大切だ」「ウクライナ問題で、防衛費の増大が与党から聞こえるが、農業に予算を使い、自給率を高める方が(安全保障として)大切ではないか。国民の命を軽んじる種子法廃止という国の暴挙に対し、司法の正しい判断がされることを望む」と語った。
菊地氏に対する、被告の国側からの反対尋問はなかった。
一般農家の舘野廣幸氏「県からの原種購入価格は3倍に」「種は農業の命。農業が成り立たなければ、国民の命も保障できない。だから種子は国の責任で守るべき」!
次に、一般農家の舘野廣幸氏が、原告弁護団の尋問を受けた。
舘野氏は、栃木県下都賀郡野木町で専業農家を1982年頃から営んでいる。米を中心に小麦、大豆などを生産し、所有する約3ヘクタールと借地を合わせて約14ヘクタールを耕作。はじめは農薬を使用する慣行農法を行っていたが、足尾銅山鉱毒事件の被害で知られる渡良瀬遊水地に隣接するため、環境問題への関心を深め、農薬で田んぼのカエルやトンボ、ホタルなどがどんどん死んでいくことに疑問を持ったという。

▲舘野氏は大豆も生産。種子法は味噌、醤油、豆腐などの原料である大豆も主要農産物として対象とする。(Wikipedia、‘Uncle Carl’、写真はイメージ)
はじめに減農薬農法を行い、1992年に農薬を全く使わない有機農法に転換。その結果、収穫量が約2割減り、雑草に悩まされたという。そこで、NPO法人民間稲作研究所が開発した「2回代掻き」等の技術を取り入れた。舘野氏は1980年頃から同研究所と関わるようになった。
有機農業では、種も有機栽培の種子使用が原則だが、有機栽培の種子は病害虫被害や雑草混入などで生産が困難なため、日本では生産体制がなく、民間稲作研究所が唯一、有機指定圃場として栃木県から指定を受けた圃場で種もみの開発を行っている。
舘野氏が約12ヘクタールの水田で使用する種もみは約240キログラムだが、舘野氏が民間稲作研究所から入手できるのは8キログラムで、残りは自家採種と、民間種子業者から200キロ購入しているという。
種子法廃止により、種もみの価格が上がったという。民間稲作研究所は栃木県から原種を購入しているが、以前1キログラム465円だったのが、2020年から1548円と3倍以上に上昇。そのため、民間稲作研究所から農家が購入する種もみもコシヒカリ4キロ4950円から5050円に上昇、京都の業者の種も20キロ1万5000円から1万5290円に上昇した。
さらに舘野氏は、今後、価格以外に、県の関与がなくなることで、品質や安定性が保証されるか不安だと訴えた。
舘野氏は最後に次のように訴えた。「種子がなければ農業はできない。農業において種は命。農業が成り立たなければ、国民の命も保障できない。だから、基本的に種子は国の責任で守っていくことが重要」「有機栽培では農薬、化学肥料不使用だけでなく、遺伝子組み換えやゲノム編集の種子も使えない。国が『みどりの食料システム戦略』を打ち出しているが、そこでの有機農業の25%達成のために、有機種子の確保を国が法律を作り、進める必要がある」「古くから栽培される在来の伝統的作物の種子も、単なる種子ではなく、重要な文化財として国が守っていく必要がある」
被告の国側弁護団は、舘野氏の陳述書にある「私たちは有機稲作を実践する農業者や消費者団体、大学の研究者などを中心に、1999年にNPO法人民間稲作研究所を立ち上げ、有機稲作の栽培技術の開発と普及に取り組んでいます」との記述を取り上げ、「舘野氏自身が立ち上げに関わったのか?」と質問した。
舘野氏は「有機稲作を求める人々は以前からいろいろな会を立ち上げていた。その中でNPOとして立ち上げに関わった」と回答。国側はさらに「舘野氏自身が立ち上げに関わったのか?」「立ち上げは1999年で間違いないか?」と念押しし、舘野氏はいずれも「はい」と答えた。
消費者の野々山理恵子氏「大企業の種子生産独占で多様性が失われれば飢餓につながる」「大企業の遺伝子組み換え作物の種子は農薬とセット販売される」!
最後に、消費者代表として、生活協同組合パルシステム東京の顧問を務める野々山理恵子氏が原告弁護団の尋問を受けた。
野々山氏は、2006年にパルシステム東京の理事となり、2013年の選挙で理事長に就任、2019年から顧問となった。関わったきっかけは、子どもができてから様々な生協に接したが、食へのこだわりや組合活動が活発なことから、1994年からパルシステムに加入したという。
パルシステムは関東中心に約2500億円の事業を運営。パルシステム東京は、1970年代の複合汚染問題をきかっけに、子どもたちに安全な食べ物を食べさせたいというお母さんたちが集まって作られたとのこと。
生産者と消費者の対等な関係を踏まえ、生産者の収入の安定と消費者が安全な食品を得る活動を行い、パルシステム東京の事業で食品が占める割合は、2021年度約82%である。
種子法廃止による消費者への影響について聞かれると、野々山氏は、「それまでは米麦大豆など主要農作物が国に守られてきたが、廃止後に民間企業の種子生産に移ると、利益追求のために安全性が担保されないことを危惧する」と答えた。
さらに、食料価格の上昇とともに、大企業による種子生産の寡占化・独占の結果、品種、地域、食べ物の多様性が失われる問題を指摘。種子法のもとで、各地の気候風土にあった作物がつくられていたのが、大企業によりマーケティングで作られた種が各地に押し付けられることを懸念。種子や農産物の多様性があることで、例えば冷害があっても国全体では穀物の収量が確保されていたのが、失われることが問題だとした。
野々山氏は、世界的な問題も指摘した。
2021年、米国やカナダが緊急事態宣言が出されるほどの旱魃(かんばつ)が起き、オーストラリアではここ数年旱魃に襲われ、小麦生産の代替地とされたウクライナで危機が発生。インドが小麦の輸出禁止措置を発表し、エジプトではパンが1.5倍に高騰したと述べた。
日本国内では、1993年の平成の米騒動の際は、冷夏で米の作況指数が74まで下がったが、全国で多様な品種が作られていなければさらに下がっただろうと指摘した。当時はタイ米を輸入してしのいだが、今後は海外から入らない可能性もあると懸念を示した。
そして、「食べ物がなければ生きていけないが、それを守ること、その元の種子を守ることは、国の責任である。これは憲法で保障されていることではないか」と訴えた。
一方、農産物の安全性についても詳しく語った。種子生産の世界シェア第1位バイエルをはじめとする種子生産の大手企業は、農薬を販売する化学企業でもあることから、それら企業の種子は農薬とセットで売られることが多くなっていると危惧した。
さらに、これらの企業は、遺伝子組み換え作物やゲノム編集作物の開発に熱心で、それらの生物への長期的影響が不明、かつセット販売される農薬の危険性も指摘した。
除草剤耐性遺伝子の作物の場合、セットで除草剤を大量に使用するため、南米等で子どもたちに大きな被害が発生。米国では除草剤グリホサートによる癌発生の訴えが続出し、和解金として何兆円も支払われた例をあげた。
IWJでは、これら除草剤や遺伝子組み換え作物等の問題について、これまで繰り返し報じてきた。
さらに野々山氏は、有機農業について、安全とともに、地球温暖化防止に効力を発揮しており、有機農業の生産面積は、世界で15倍に拡大していると指した。
近代農業は、第二次世界大戦の化学兵器工場が(軍民)転換して肥料や農薬を生産し、土壌にダメージを与えてきたことから、国連が2015年を国際土壌年に指定。また、国連は2015年を国際家族農業年にも指定、家族農業の10年も提唱して、「家族農業こそが持続可能な農業である」と謳っているという。
民間企業の参入で、小規模農家排除につながる種子法の廃止は、これらの国際的な動きに逆行する。
一方、日本では農林水産省が『みどりの食料システム戦略』で有機農業推進を謳っているが、種子法廃止はこれに反するとも指摘した。
最後に野々山氏は、「種子法は戦中戦後の食糧難に苦しんだ経験から食料の安定供給のために作られたが、それが廃止されたことに強い危機感を覚える」「国連発表では、世界人口の1割以上の8億1100万人が飢餓状況にある。そのような中、国民が飢えで苦しまないように、食料確保は国が責任をもってやってほしい。さらに食料のもとになる種子は国が守るべきものだと憲法で保障されていると、この法廷で認めていただきたい」と訴えた。
国の弁護団からの、野々山氏に対する反対尋問はなかった。
結局、これら3人の原告の、種子法復活を望む、強い意見表明に対して、国側からの反対尋問は、ほとんど行われなかったことになる。これは、口頭弁論前日の記者会見で、原告弁護団の山田正彦弁護士(元農林水産大臣)が予想した通りの展開であった。
山田弁護士はIWJ記者の質問に対して、「多分、(国側は)反論はしてこないんじゃないかと思う。(中略)最終準備書面を我々も書いて、向こうも書いて、そして結審ということになるので、早ければ年内に判決という形になるんじゃないでしょうか」と語っていたのである。