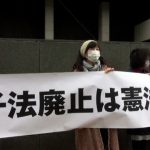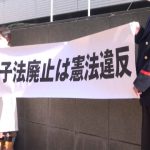2022年6月3日、「種子法廃止等に関する違憲確認訴訟」第7回口頭弁論が、東京地方裁判所103号法廷で行われた。午前10時から原告証人尋問が行われ、午後1時10分から証人尋問が行われた。
裁判官は春名茂氏(裁判長)、横井靖世氏、下道良太氏であった。
本稿では、午後に行われた証人尋問の報告をする。午前中の原告証人尋問、また終了後の報告集会については以下を御覧いただきたい。
同訴訟は、種子法廃止は憲法違反だとして、全国の農家や消費者らが国を相手取り、提訴したものである。
証人尋問では、順番に、山口正篤氏(元栃木県農業試験場)、鈴木宣弘東京大学教授(食料・農業・農村政策審議会委員)、土屋仁美准教授(憲法学・食品法ほか)が証言をおこなった。
担当弁護士はそれぞれ、順番に、弁護団共同代表の田井勝氏、弁護団共同代表の岩月浩二氏、古川(こがわ)健三弁護士であった。
山口正篤氏は、栃木県職員として、農業試験場で種子法廃止前の種子に関する一連の業務に携わるなどし、また、県OBとして種子法廃止後の県業務の実態を知り得る立場にある。山口氏は県業務の実際と意義を語り、種子法廃止後、国の主張とは異なり、県の業務が逼迫している実態があるとして、強い危惧を表明した。
鈴木宣弘教授は、食料・農業・農村政策審議会委員として、国の農政の審議・決定プロセスに通暁されている。鈴木教授は、審議過程について、従来は農業の現場から声が上がり、それを農水省が受け止め、国会に送るという流れであったと解説した。
しかし、TPPに関連するさまざまな改革が進められるなかで、規制改革推進会議からのトップダウンで行われ、農水省側が異議を唱えれば人事で報復を受けるといった実態があることを証言した。
土屋仁美准教授は、日本国憲法25条「健康で文化的な最低限度の生活」と、世界人権宣言25条「十分な生活水準を保持する権利」等から「食料への権利」について解説した。種子法廃止の問題点として、従来の農家の存続が危ぶまれること、食糧の安定供給に懸念が生じること、種子の品質保持が危ぶまれることなどを指摘し、それらが「制度後退」にあたると論じ、司法審査を求めた。
土屋氏は、50分にわたってパワーポイントを用いた詳細な証言をおこなった。
被告・国側の反対尋問は、山口氏と土屋准教授の経歴確認などに留まり、実質的な内容に踏み込むものではなかった。
詳しくは、記事本文を御覧いただきたい。
- 日時 2022年6月3日(金)10:00~12:00(原告本人尋問)、13:15~17:00(証人尋問)
- 場所 東京地方裁判所(東京都千代田区)
- TPP交渉差止・違憲訴訟の会 サイト内告知
山口正篤氏「国として種子法をなくしてはいけない、種子法を復活し、良い種子をつくる手助けをして欲しい」

▲「田植え」(撮影:Arttecture、PhotoACより)
山口正篤氏は栃木県(作物部)の農業試験場の職員として30年間、地域に適した奨励品種の調査・選定、新品種の開発育成、原種・原原種の生産、農家へタネ生産の指導と審査を行ってきたと述べた。以下、山口氏の証言を要約でご紹介する。
種子法にもとづいた県業務の実際について、山口氏は以下の内容を述べた。
「地域にあった品種を調べ、奨励品種を選定する業務が、種子法にもとづいた最も重要な県の業務であった。県北であれば、寒さに強い品種を選定するなどである。南では、病気に強い麦の品種を選定した。
新品種の開発育成では、栃木県県北地域に適した「ナスヒカリ」の育成に携わった。通常であれば、新品種の開発は10年程度だが、那須光の場合12、3年に及んだ。他県で育成された品種を栃木県に適合するかテストし、奨励品種として採用できるかどうかを確認する。
米の品種は国が管理しており、それらが栃木県に適合するか試験をする。例えば、福井県で生産された「コシヒカリ」が栃木県に適するかどうかを調査する。
奨励品種として採用された種子の原種・原原種を維持することも重要な業務であった。原種・原原種の生産にあたって、農家にタネ生産の指導と圃場審査と生産物審査を行っていた。圃場審査は年2回、生産物審査では、取れた種子の外観・汚れ、充実度、異品種の混合がないか等を審査する」。
続いて、種子法が廃止されたことの弊害について問われ、山口氏は以下のように証言した。
山口氏「種子法にもとづく最も基本的な業務は奨励品種調査であった。その後、地域に適した新品種の育成も始まった。これは東北や関東のほとんどの県がやってきた。そして、しっかりしたタネをつくり、安く農家に提供するために、種子の生産も行ってきた。これらが種子法にもとづいた業務であった。
種子法がなくなるということは、奨励品種調査や育成事業、種子の生産といった事業がなくなることを意味する。長く積み上げられてきたこれらの事業が徐々に失われていくという懸念がある。
新しい品種の育成事業は、種子法に明記されているわけではないが、奨励品種の調査育成がなくなれば、こちらも徐々になくなっていくと思われる。
最大の問題は財政である。これまでは種子法にもとづいて国から照例品種の選定調査などのための交付金が来ていたが、現職の栃木県職員に聞くと、種子法がなくなって国からの交付金がなくなったという。そのため、奨励品種調査などを実施する財源がないと、県の財政課から言われているという。したがって、事業を縮小せざるを得ない状況になっている」。
田井弁護士は、「国は種子法が廃止されても、都道府県ごとに品種をつくれば良いというが、それはどうなのか」と質問した。
山口氏「財源がなくなり、奨励品種の選定調査など基本的な事業がなくなれば、その上に乗ってすすめてきた新品種の育成も難しくなる。職員も減ってくる。
奨励品種の選定ができなくなれば、民間で『多収性』を売りにした品種が生産されても、それが栃木県に適合するかどうかをチェックできなくなる。土壌や気象の条件が異なれば、『多収性』を実現できない可能性もある。やはり、適合調査は必要であると思う。
民間の参加も良いが、それが現場に適合するかの公的なチェックは必要である。そうしなければ、適合しない品種が地域に普及し、市場を独占すれば、生産性や品質、食味が落ちるということも考えられる」。
田井弁護士は、「種子の生産に県が関与しなくなると、何が懸念されるのか」と質問した。
※本記事は「note」でも御覧いただけます。単品購入も可能です。
https://note.com/iwjnote/n/nc7d39da47495
<ここから特別公開中>
山口氏「タネはどこかでつくらなければならない。種子法が廃止されても、仕方なく県が条例をつくってタネ生産の指導を行なっているが、タネの品種の審査をしなくなり、責任を持たなくなっている。
栃木県の条例には、審査のことは書かれていない。無責任な条例だ。栃木県でも条例をつくって種の生産を指導・確認しているが、審査はしない。タネに対して責任を持たない。トラブルがあっても県は補償しない。つくった民間の責任だと、逃げてしまう。無責任な体制になりつつある」。
山口氏は、平成24年25年に、ナスヒカリにコシヒカリが混入した事件が起こり、その年の作付けを停止したが、全農や農協、県が補償を行ったが、今後はそうした補償が行われなくなる可能性が高いと指摘した。そうなれば、農家は経営していけなくなるのではないかと懸念した。
田井弁護士は、「種子法廃止後に、原種の価格が2〜3倍に高騰したそうだが」と質問した。
山口氏「原種はだいたい3倍になった。一般のタネも2〜3割上がった。県は財源がなくなった分、経費をできるだけ削っても価格を上げなければならない。昨年は米価が下がった。現在は、資材、油、肥料などの価格が上がっており、さらに種子の購入費も上がってくるとなれば、農家はもう生産を続けられなくなる。私の身近でもある。種子法が廃止された以上、価格がさらに高騰する可能性がある」。
最後に山口氏は、国として種子法を維持してほしいと訴えた。
山口氏「その地域にあった品種を選び、育成し、農家に安く提供する。こうした一連の事業の基本は種子法であったと思う。県の条例では限界がある。国として種子法をなくしてはいけない。種子法を復活し、良い種子をつくる手助けをして欲しい」。
被告・国からの反対尋問は、山口氏の経歴についての確認のみであった。
鈴木宣弘教授「歪んでしまった政策決定過程を正すことが必要」「グローバル主義と結びついた『今だに、カネだけ、自分だけ』の人たちが、政治、行政を私物化している」と批判! 日本もまさに「オリガルヒ」に食われている!?

▲「黄金色に稔った稲穂」(撮影:FRANK211、PhotoACより)
続いて、午後1時50分ごろから、鈴木宣弘教授教授の証人尋問が始まった。岩月弁護士が、鈴木教授の経歴を確認した。鈴木教授は1982年に東京大学農学部を卒業後、農林水産省に入省した。その後、九州大学を経て、2006年より東京大学教授に就任した。「食料・農業・農村政策審議会」委員として会長代理、企画部会長、畜産部会長、農業共済部会長などを歴任された。
岩月弁護士は、「食料・農業・農村政策審議会」を含め、意思決定のプロセスがどうなっていたかを問うた。以下、鈴木教授の回答を要約で示す。
鈴木教授「例えば、2008年の世界的な食糧危機(畜産飼料の暴騰)の際、生産者がまず声を上げ、政治が動き、農水省が対策原案をつくり、審議会にはかる。審議会には生産者や消費者など、さまざまな関係者が含まれている。そこで提案を合議でまとめ、コンセンサスが得られれば、政策決定される」。
岩月弁護士は「審議会はボトムアップで、広くいろんな意見を集めるという役割をしていたということですね」と確認した。鈴木教授は、その通りだと認めた。
鈴木教授は、現在の状況は、2008年当時を遥かに上回る危機的な状況だが、農水省は以前のように農家など生産者の声を捉えることをしていないと指摘した。審議会を開いて多くの声をある目何か対策をしようという動きがない、と危惧した。
鈴木教授「今までの民主的なシステムが崩れている。
2008年の危機の時、いつまでも輸入に依存していると、また同じことが起こる。長期的には体制を変えないといけないと提言した。
今の日本の食料自給率はカロリーベースで約38%というが、種子や飼料や生産資材も輸入に大きく依存していることを考慮すれば、y野菜の実際の自給率は8%程度に過ぎない。野菜の種子の9割は海外の圃場で生産されている。非常に危険な状況で、特にタネが問題だ。
2035年には米の自給率は11%になると試算している。種子法が廃止され、米などのタネ生産も民間に移行すると見られている。日本の圃場は狭い。野菜と同じように、海外の業者にタネの生産を委託し、広大な海外の圃場に生産が行われることになる。
今は国がお金を出して、都道府県が生産する、公共のタネだが、民間になれば、海外流出の歯止めはなくなる。
2日前にも今年の秋から肥料の価格が2倍になると報じられた。原料もない。ウクライナ危機もあるが、それ以前から中国はじめ各国が自国の生産を守るために囲い込みに入って、なかなか売ってくれなくなっていた。
『食料・農業・農村基本法』は自給率を上げることをめざしているが、日本はWHO・GAT体制の中で自由貿易をどんどんたたみかけるように進めてきた。有事の際には輸入が期待できなくなることから、ある程度の自給率を実現することが基本法の役割である。
種子法の廃止は、自給率を上げるという基本法に著しく反する」。
岩月弁護士は、種子法廃止の審議過程について、国会に上程されてから、はじめて気がついた関係者が多かった、山田正彦氏ですら知らなかった、生産者もほとんど知らなかった、まるで不意打ちであったと言われるが、鈴木教授は知っていたか、審議会にかけられていたら、種子法廃止が通ったと思うか、と質問した。
鈴木教授「はい、私も知らなかった。
仮に審議会に出ていれば、大変いろんな意見が噴出して、簡単にまとまることはなかったはずだ。もし私が事前に知っていれば、反対の立場で議論を展開し、世論にも訴えていたと思う。
反対者もたくさん出る、大変な問題だということで、通常の審議過程を取れば実現できないということで、秘密裏に進められたと思う。
(国会の審議でも種子法を廃止しても、種苗法があると説明されたが)、両者は全く異なるものでそのような主張は論理破綻している。理解に苦しむ。
(種子法が廃止されても、都道府県の取り組みを後退させないとされるが)、実際にいろんな県に聞くと、予算が切られ、人が切られている。ゲノム遺伝子だけ予算が増えている。現実には縮小されているので、栃木県のように種子の値上げが行われている」。
鈴木教授が外資を含む大手資本優先の種子法廃止の内情を暴露! 「種子法廃止に農水省は反対してきた。しかし『規制改革推進会議』の決定が絶対であり、反対する官僚は左遷された」
岩月弁護士は、農水省の2017年11月の通知について説明を求めた。
鈴木教授「種子法廃止に対して、農水省はなんとか都道府県の育種生産事業が続けられるようにしようと通知を出した。
しかし、蓋を開けてみると、都道府県が事業を継続できるのは民間に移行するまでの間だけ。そして県の品種も民間に譲渡することになっていた。これで県の担当者はひっくり返ってしまった。
農水省は種子法が廃止されても、なんとかこれまでの事業ができるように対応していたが、農水省の意図を無視するかたちで種子法廃止が行われた。
米、麦、大豆の種子を公的に提供する種子法は、食糧生産の根幹を成す法律である。農水省はこれを維持しようとしていたが、これを潰したい勢力があった。種子法の廃止は農水省の本意ではないと確信している。
種子法だけではなく、畜産法などでも同じような経緯があり、抵抗する局長などが左遷されるなどの人事が行われている。
『規制改革推進会議』(注1)の決定が絶対であり、農水省も抵抗できないという、強力な権限が与えられていることが最大の問題である。これはTPP協定と関係がある。米国はTPPを破棄したが、日米2国間の合意は生き残っている。
米国企業の要望は『規制改革推進会議』を通じて、実行するという約束になっている。そのため、『規制改革推進会議』の権限はさらに強大になった。
森林関係の法改定も、トップダウンで行われた。『規制改革推進会議』の上位にある『未来投資会議』から降りてきた案件である。林政審議会の会長は憤慨して『クビになってもいいが、これはおかしい』と抗議した。これは財産権の侵害で、憲法違反だと内閣府法制局も指摘したが、強行した。
漁業法も同じ。漁業権を切り離して、公共でもない民間企業に与えた。補償もない。やはり、財産権の侵害にあたる。水産庁も全く知らないところで強行された。
こうした例は枚挙にいとまがない。」
最後に鈴木教授は、現在の日本の政策決定過程の異常さについて警鐘を鳴らした。
「従来の民主的な政策決定過程は崩壊し、グローバル企業と結びついた『今だけ・カネだけ・自分だけ』の人たちが、政治・行政を私物化し、自分たちに有利な法改定を強行している。誰も異論を言えない。
こんなことが続けば、世界食糧危機で農家がどんどん潰れていっても何もしない。国民全体が飢餓に陥るような状況にならないと、あるいはそういう状況になっても、何もしないという恐るべき状況だと思う。歪んでしまった政策決定過程を正すことが必要である」。
被告・国からの反対尋問はなかった。
土屋仁美准教授「種子法の廃止は『食料への権利』に対して悪影響を及ぼすもの。司法審査が必要」

▲「田舎の風景・棚田」(撮影:花散歩、PhotoACより)
休憩を挟んで、午後2時50分から、土屋仁美准教授の証人尋問が行われた。担当は古川弁護士である。証人尋問は土屋教授のパワーポイントに沿って進められた。
土屋教授は、種子法は農家への支援として、食料供給の安定をめざして制定され、1986年の民間事業者の参入を促す改定を経ても、その立法趣旨は現在も変わっていないと指摘した。
土屋教授「種子法廃止のメリットは、民間事業者の参入を促すことであったが、従来の個人経営・家族経営の農家が参入するには、専門的な知識と技術が必要であり、困難な内容になっている。
民間事業者が参入してくれば、公的な生産普及体制における種子価格よりも当然、種子の価格が高くなる」。
続いて、土屋教授は、国際人権法上の「食料への権利」について解説した。
土屋教授「国連の特別報告者は、自由貿易下で、少数の企業関係者に権利が集中していると指摘し、『種子の支配は生命の支配』になると警鐘を鳴らした。
世界人権宣言25条1項、そして社会権規約11条1項、2項で、『十分な食料への権利』が示された。ここには、安全な食料、生活水準だけではなく、文化的側面も含まれている。
さらに、『小規模農家にとって不可欠な既存のサービスを撤廃することは後退措置』になるとし、禁じている。
種子法の廃止の問題点は、民間活力に従来の農家が含まれていないこと、食糧の安定供給や農業が果たす多面的機能の議論の欠如、種子の品質や価格が市場原理に委ねられること、である。
日本国憲法では、25条の生存権で『食料への権利』を明記していないが、食料・農業・農村基本法、食育法を見れば、『良質な食料が合理的な価格で安定的に供給』されること、食文化の意義が示され、『食料への権利』を包含するものだと考えられる。
日本国憲法についても、生存権の自由権的側面から立法府による制度後退を違憲とする見解がある。
食品安全基本法には、食品の安全性の確保、安全な食品へのアクセス、行政の責任が示されている。
種子法廃止には、種子の安全性の確保、食糧の増産と安定供給、食品の安全性の確保等に悪影響を与える可能性が懸念される。市場メカニズムに品質保証を委ねれば、経済の民主性(独占禁止法1条)が損なわれる恐れがある。『安全への権利』と『選択の自由』が相克する。
第3回未来投資会議構造改革徹底推進会合『ローカルアベノミクスの深化』、第4回規制改革推進会議農業ワーキンググループ合同会合(2016年10月6日)では、『国家戦略として種子に関する施策を活用する』目的で、種子法廃止を提案しているが、消費者不在の議論になっている。
経済規制・緩和・撤廃立法に対する司法審査が必要である。それぞれの立法の真の目的を炙り出し、誰かの利益になり、誰かの不利益になるといった不平等な立法が行われないよう、司法が審査すべきである。
種子法廃止は、農業の競争力強化、私的利益の確保にもとづく議論に終始し、種子法が民間企業の参集を阻止しているという具体的な根拠も、民間企業が参入することによって種子価格が下がるという根拠も、生産者の所得向上になるという定量的な根拠もなく行われた。その審議課程では、行政も国会議員に適切な資料を提供しないなどの問題があった」。
土屋准教授は以下のように、「司法審査が求められる理由」を最後に訴えた。
土屋准教授「種子法の目的と日本の主要農作物をめぐる状況について、その立法趣旨や公的機関の役割に変化はない。
『食料への権利』に対して、種子法廃止の影響は、種子に対する安全性確保のための事前規制において、後退している。事後救済も困難である。事前・事後ともに消費者の利益確保が崩されている。
種子法廃止の『審議と決定のプロセス』の問題点を、食料の安定供給や、消費者の視点からの審議がなく、国会議員への資料提供にも問題があった。国会と行政の関係が問題になってくる。
司法が審査することが必要である」。
被告・国による反対尋問は、土屋准教授に対して経歴などを確認するだけのものであり、証言内容の議論に踏み込むことを回避した。