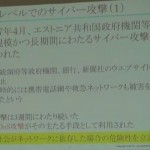「核燃料サイクルが進まない中、40トン超ものプルトニウムを抱える日本。2018年には日米原子力協定が切れるが、米国は『寝た子を起こすな』との立場だろう」と太田昌克氏は語った──。
地政学的な視点から、政治・外交・教育・安全保障・経済・歴史認識など、国家の重要分野の知見を広く発信している国際地政学研究所が主催するワークショップの11回目、「日米同盟 ―核の将来を軍・民の視点から見る―」が、2014年11月20日、東京都千代田区のアルカディア市ヶ谷にて行われた。
この日の講師は、日本原子力研究開発機構の和泉圭紀氏と、共同通信社編集委員・論説委員の太田昌克氏の2人。和泉氏が日米原子力協定のこれまでを振り返り、太田氏は1954年に起きたビキニ環礁沖での第5福竜丸の放射能被曝事故に言及して、「あの事故がなければ、日本の核をめぐる状況はだいぶ違うものになっていた」と論じた。
両講師が共に指摘したのは、国内で核燃料サイクルが進んでいない中で、日本が核兵器に利用できるプルトニウム40トン超を国内外に抱えていること。
和泉氏は「核兵器を持たない国の中で、日本だけが再処理を認められていることに不満を抱く国が増えている」と述べ、太田氏からは「日本は、イランや韓国の手本になるようなプルトニウムの使い道を考えねばならない」との主張があった。
- 日時 2014年11月20日(木) 14:00〜
- 場所 アルカディア市ヶ谷(東京都千代田区)
核燃料サイクルに「軍事転用」の意図あり
ワークショップは、同研究所の理事長で元内閣官房副長官補でもある柳澤協二氏の談話からスタートした。今年2014年、米国が高濃度ウランと分離プルトニウムの返還を日本に求めたことが、最初の話題になった。この一件は日本ではあまり報じられなかったが、米ホワイトハウスは3月24日、オバマ大統領と安倍晋三首相が返還に合意した、との共同声明を発表している。
対象となったのは、日本政府が研究用として米国から提供されていた高濃度ウランと分離プルトニウムで、日本原子力研究開発機構が使用済み核燃料の再処理技術(核燃料サイクル)の確立を目的に、高速炉臨界実験装置用に保有中だった全量である。
共同声明では、「この返還合意で何百キロもの核物質が削減され、世界にある高濃縮ウランと分離プルトニウムを最小限まで減らす共通目標が推進される」と強調。米国に戻される分離プルトニウムと高濃度ウランについては、それぞれ最終処分と希釈後の民生利用が表明された。
軍事同盟と原子力協定を背景に、日本の「核燃料サイクル」は米国からの了解を得ているが、その実施には、使用済み燃料から取り出したプルトニウムでいつでも核兵器製造が可能であることを海外にアピールし、「抑止力」を高めるという、安倍政権を含めた歴代自民党政権の「もうひとつの狙い」があると柳澤氏は語る。
その上で、「(今回の合意のように)核拡散防止という側面では、日本は米国に協力することもあるが、今後、日本が核燃料サイクルをめぐってどこまで我を貫き通すかで、日米関係の将来は揺さぶられる可能性がある」とした。
ウラン需要膨張で「再処理容認」の気運が高まる
続いて、講演を行った和泉氏は、「日本の原子力開発は、1950年代の黎明期から現在に至るまで、ある意味では防衛分野以上に米国との切っても切れない関係をバックにしてきた」と強調した。
2007年に妥結した米国とインドの原子力協定を例に取り、「インドが米国から原子力資材を輸入したいと希望したことを受け、米国はインドに対し、(その資材の使用をめぐる)ある種の縛りをかけることを目的に協定締結を求めた」と解説。そして、1955年に日本が日米原子力研究協定に調印した折も、米国には同じ狙いがあったと話した。
同年に発効された研究協定の中身は、日本が米国から一方的に支援される立場であるだけに、片務契約的なものにならざるを得なかった、と和泉氏は指摘する。貸与燃料の転用禁止や、使用記録の毎年報告義務などが具体的な項目であることを紹介し、「その後1958年には、日本の原子力技術の進展により、ウランの使用量が締結時に定めた限度を超えることが確実になったため、協定は改定された」と続けた。
和泉氏は「改定の際に、米国には『当初の見通しを上回るペースで世界の原子力利用が進んだため、ウラン需要の増大に米国からの供給が追いつかなくなるのではないか』という懸念もあった」とも述べ、その懸念が、米国が日本などの友好国に対し、条件付きながら「核燃料サイクル」開発を容認する下地になった、との見方を示した。
カーター大統領が東海村施設稼働に「待った」
それから10年後の1968年。日本の原子力開発が、それまでの研究用原子炉をめぐるものから、発電用原子炉をめぐるものへと進展したのに伴い、旧原子力協定が結ばれる運びとなる。旧協定では、日本で建設・計画中の原発に、向こう30年間にわたって必要となるウランの全量を、日本が米国から受け入れなくてはならない旨が明記された。
そして、核燃料サイクルでの日米両国の「共同決定」が義務づけられ、日本国内での再処理が可能になった。「これは(日本で最初の核燃料サイクル工場となる)茨城県東海村の施設建設を視野に入れたものだった」と和泉氏は言う。
だが、その後、日本の核燃料サイクルは暗礁に乗り上げる。1974年にインドが強行した核実験が原因だ。和泉氏は「(インドの核実験は)平和利用目的で輸入した原子力資材の、軍事転用が可能であることを証明してみせた」とし、「これを重く見た米国(カーター政権)は、従前の原子力利用の拡大路線から核拡散防止へと軸足をシフトした」と強調した。
米国は日本の核燃料サイクルにも、無期限の開始先延ばしを求めてきたのだが、1971年に建設が始まった東海村再処理施設の稼働については、「1977年3月の日米首脳会談で、カーター大統領は福田赳夫首相に『日本のエネルギー事情はわかったが、再処理は行うべきではない』と告げた。だが、福田首相がこれに応じなかったため、会談では結論が得られなかった」と続けた。
新協定でも残った「米国の呪縛」
その後に行われた実務レベルの日米再処理交渉で、日本側は、経済発展や安全保障に原子力は不可欠との立場を主張。和泉氏は「東海村の再処理施設では、プルトニウム単体ではなくウランと混合して取り出すという、核拡散に抵抗性のある方法を採用することを条件に合意が得られ、運転開始へと至った」と話す。その後、1981年には核燃料サイクルに寛容なレーガン政権の誕生を受け、再処理をめぐる規制も緩和される方向に向かったという。
1988年には、現行の日米原子力協定が締結されるのだが、「1955年の研究協定以来、日本がずっと負い続けてきた米国への一方的な義務は、新協定では規制に『双務性』が認められるようになったため緩和された」と和泉氏は言う。
また、旧協定が、その時々の米国の原子力政策上の主観的判断が反映されやすい個別審査型だったのに対し、新協定では、前もって定めた条件の枠内で一括して承認する包括同意方式が導入されたことにも触れ、これにより日本は長期的視点での核燃料サイクル計画の立案が可能になった、とした。
一方で、和泉氏はこのような発言もしている。「米国の国内法に基づく対日規制権を、日本の原子力政策に行使する部分は依然として残っており、日本は今なお、米国のくびきの下に置かれている印象がある。1955年の研究協定調印の時に問題になった、原子力政策をめぐる日本の自主性の確保については、新協定でも実現されていないと見ることが可能だ」
その後、現行協定の満期到来による「2018年問題」に話題がおよぶと、和泉氏はその際の留意点として、1. テロ対策としての核セキュリティーの強化、2. 再処理施設をめぐる国際情勢の変化への対応、3. 核燃料サイクルを通じて日本が国内外(海外は再処理委託先の英仏)に保有する40トン超(2013年12月時点)というプルトニウムの利用見通しの説明、の3つを挙げた。2.の国際情勢の変化とは、核兵器非保有国の中で、日本のみが核燃料サイクルによる核物質保有を容認されていることを、不公平と見なす国が増えていることを指す。
「核の平和利用」に込められた狙いとは
次に登壇した太田氏からも、2018年問題に関しての発言があった。「先月、取材でワシントンを訪れた際に、関係筋に『2018年に原子力協定が切れるが、どうする?』とぶつけてみた。米国の腹づもりは『自動延長』であるらしい。つまり、日米のどちらかが『もうやめる』と言わなければ、そのままだ」と話した。
さらに、2018年問題に絡めて、日本が、核燃料サイクルが進まない中で40トン超ものプルトニウムを持っていることにも言及した太田氏は、米国は「寝た子を起こすな」の立場に立つだろうと述べ、その理由を、「満期後に協定を書き直すとして、その際に日本の核の再処理をもう一度認めるとしたら、米議会が強く反発するだろう。だからといって、日本から再処理の権利を引きはがそうとしたら、日本は大いに抵抗するに決まっているからだ」と説明した。
また、福島第一原発事故への対応で、米国の技術面での援助が大きかったと語る太田氏は、「日本の原子力政策の源流は、1954年3月1日、ビキニ環礁沖で第5福竜丸が米国の水爆実験に巻き込まれて被曝した一件にある」と力説した。
そして、「ビキニでの水爆実験の4ヵ月ほど前には、アイゼンハワー米大統領がニューヨークの国連総会で『核の平和利用』の演説を行っている」と続け、次のように話した。
「その時の米国の狙いは、旧ソ連が核開発を進める中で、『核の平和利用』を軸にしつつ、西側同盟国の結束を図ることだった。これは間違いない。さらに、もうひとつ、核兵器の威嚇効果を最大限に利用して、旧ソ連の欧州攻撃を抑止する大量報復戦略(ニュールック戦略)を実現するため、同盟国管理用のツールにするという隠された狙いがあったのではないか」