「日本」という国家から、この日の少女たちへのクリスマスプレゼントが、これなのか。クリスマスの夜、政府は少女たちの未来を危険に晒し続ける判断を下した――。
全身が痙攣(けいれん)し、失神にまで至ったり、四肢の機能に障害が出たり、知覚が異常になったり、全身が脱力するなど、深刻な副反応被害が出ている。そうした報告が相次ぎ、ワクチンの中止を求める声が高まる中、接種事業は今後も継続されることが本日(12月25日)決まった。判断を下したのは、厚生労働省である。
厚生労働省は、12月25日に行われたワクチン副反応検討部会で、現状の措置を維持し、子宮頸がんワクチンの「積極的勧奨」の再開を見送った。これは、ワクチン接種事業に対する多くの反対の声を無視できなかったためとみられる。とはいえ、接種事業が中止されることはなく、子宮頸がんワクチンの接種は継続されるので、結局、被害者の少女らの声は聞き入れられなかったも同然である。
子宮頸がんワクチンをめぐる、国と医師会と自治体の発言を辿っていくと、福島第一原発事故による放射線被爆問題についての、国や東電の弁明が脳裏に浮かぶ。御用達者と役人が手を結び、被害者の救済よりも、業界の利権を最優先に守ろうとする構図が重なりあうのだ。子宮頸がんワクチンの副反応被害対応でも同じ愚行を繰り返すのか。犠牲になるのは、今回もまた子どもたちだ。
下の動画をご覧いただきたい。IWJが5月10日に取材した全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会で紹介された、ワクチン被害者の少女らの映像である。子宮頸がんワクチンを接種したことで、全身痙攣や歩行困難などの副反応に苦しむ少女たちは、外に出て友達と遊ぶことも、運動をすることも、学校で勉強をすることもできなくなってしまったのだ。
ここでは、IWJがこれまで取材した子宮頸がんワクチンをめぐる推進派の動きと、彼らの思惑について明らかにする。まずは、子宮頸がんワクチンをめぐる、これまでの経緯や問題点をおさらいしたい。
4月に「定期接種化」、2ヶ月後に「積極的勧奨」を一時中止
2009年に導入(※注1)され、任意で接種することが可能になった子宮頸がんワクチンだが、2013年4月から、予防接種法に基づき、「国や自治体が接種を勧める努力義務が必要なワクチン」に分類され、「定期接種化」された。
しかし、わずか2ヶ月後の6月、接種者の副反応被害が相次いで報告されたことを受け、厚労省は、十分な情報提供ができるまでの間、接種の「積極的勧奨」を一時的に中止するとした。
国は、ワクチンそのものを禁じたわけではない。対象者や保護者に対して、広告紙やポスター、インターネットなどを利用した「接種勧奨」を控える措置をとっただけである。「中止するほどリスクが高いわけではない」という理屈で、希望者にはワクチンの接種が受けられるような措置をとっていた。
(※注1)子宮頸がんワクチンは2006年に米国で初めて承認され、日本では2種類のワクチン(サーバリックス:2009年、ガーダシル:2011年)が導入されている。
そもそも、子宮頸がんワクチンは必要なのか?
子宮頸がんの原因とされるHPV(ヒトパピローマウイルス)は性交渉により感染するが、性交後の女性にはワクチンの効果はない。このことから国は、性交前の小学6年~高校1年の少女たちを接種の対象にしているが、実は子宮頸がんによる死亡者のほとんどは60代以上の女性だ。
子宮頸がんワクチンの効果の継続は、長くても20年間と言われているが、米国でこのワクチンが初めて接種されたのが10年前であるため、効果が20年間も持続するのかどうかまだ確認されていない。子宮頸がんによる死亡者のほとんどが60代以上であることと照らし合わせると、10代の少女にワクチンを接種したところで、子宮頸がんにかかるピークの60代まで、40年以上もその効果が持続するとは考えにくい。
そんな、効果のあやふやなワクチン接種のために、重い副反応のリスクを引き受けなくてはならないものなのだろうか。
厚労省の12月25日のワクチン副反応検討部会資料によると、子宮頸がんワクチンの9月までの接種者数337万人(推定)のうち、副反応の報告件数は2320件、うち重篤な副反応が1083件という。つまり、10万人のうち、68.84人に副反応が起き、うち32.14人には重篤な副反応が起きるという計算になる。
では、子宮頸がんワクチンで予防できるウイルス(※注2)に感染してしまう確率はどの程度なのか。厚労省の矢島鉄也健康局長(当時)は、3月28日の参議院厚生労働委員会の質疑の中で、日本の研究者が海外の医学系雑誌に発表したデータを参照し、日本の一般女性(18~85歳)のうち、子宮頸がんの原因とされているHPV16型、18型の感染の割合が、それぞれ0.5%と0.2%であることを認めた。また、同局長は、HPVに感染しても、9割以上が2年以内に自然排出されることも認めている。つまり、10万人のうち7人のみがワクチン接種の効果を享受できる計算になる。
またHPVに持続的に感染しても、適切な治療により治癒率はおおむね100%であることが、同委員会において示されている。ワクチンを接種しなくても、定期的な検診や治療でほぼ100%子宮頸がんを予防することができると、厚労省自らが認めているのだ。そうであればハイリスクなワクチンなど、不要ではないか。副反応被害の出る確率の高さと深刻な症状実態を見れば、接種事業そのものに疑問を抱かずにいられない。
(※注2)日本で認可されている子宮頸がんワクチン2種のうち、サーバリックスはHPV16型・18型、ガーダシルはHPV6型・11型・16型・18型の感染を予防するワクチンである。
ワクチン接種の勧奨に「待った」の声
ワクチン接種の「勧奨」を控え、副反応被害者へ救済措置を、という声は、全国各地の自治体で強まっている。
北海道議会は12日、国に対してHPVワクチン被害者の救済を求める意見書を全会一致で提出。道内では、ワクチン接種後に頭痛や発熱などの副反応と見られる症例報告は48件にのぼっている。
横浜市議会でも、17日に同様の意見書が全会一致で可決された。意見書は、子宮頸がんワクチンの副反応との因果関係が明確になるまでの間、ワクチン定期接種の「積極的勧奨」を行わないことを要望。また、ワクチン接種による症状が出ているとされる生徒の学校生活や進学についても、特段の配慮や支援策を講じるよう訴えている。
千葉県野田市では、厚労省の「積極的な勧奨の中止」の判断を受け、市民の健康を最優先するという観点から、6月18日にHPVワクチンの接種を一時見合わせていた。
こうした自治体の動きについて、田村憲久厚生労働大臣は、17日に行われた閣議後の記者会見で、「副反応検討部会でしっかり議論していただく」と回答。「今までいろんな症例等々を検証しながら、実際問題どれくらいの数があるのか、海外と比べてどうなのかという調査をしております」と述べた。
子宮頸がんワクチン副反応被害者の救済に関しては、「法律に則って救済はできるようになっておりますので、救済の対象ということに。もし、そういう方々がおられれば、副反応の報告をいただいて、その上で救済という話になろうと思います」と述べた。
ワクチン被害者の救済が機能していない実態
しかし、田村大臣の答弁とは裏腹に、実際のところ、子宮頸がんワクチン被害者の救済は、ほとんど行われていないのが現状だ。その理由としてあげられるのは、副反応の症状が、ワクチンの接種によって引き起こされたのだという因果関係の証明が難しく、証明されるまでに非常に長い期間を要するから、というものだ。さらに、ワクチン接種による副反応の症状を専門的に治療できる医療機関も全国で17ヶ所しかない(※注3)。
子宮頸がんワクチン被害者らは、ワクチンの副反応に対する検査体制が不十分であり、検査・治療にあたる医療機関に被害の実態が理解されていないと指摘している。ワクチンとの因果関係を認めてもらえないだけでなく、いまだ治療法が分からず、病院のたらい回し、不適当な診断、処方された薬の副作用が重なるなどの過酷な状況に置かれており、中には、被害者本人が『こうした症状が一生続くのか』という不安や苦しみから、自殺やリストカットなどの自傷行為に及んでしまうケースもあるという。
(※注3)17ヶ所の医療機関は以下の通りである。
北海道大病院・札幌医大付属病院・福島県立医大付属病院・東京大医学部付属病院・東京慈恵医大付属病院・順天堂大付属病院・名古屋大医学部付属病院・愛知医大病院・滋賀医大付属病院・大阪大医学部付属病院・岡山大病院・高知大医学部付属病院・愛媛大医学部付属病院・山口大医学部付属病院・九州大病院・鹿児島大医学部付属病院
ワクチン接種勧奨を再開させたかった学会
子宮頸がんワクチン被害者の切実な声をよそに、ワクチン推進派は、「接種勧奨」の再開を待ち望んでいた。
日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本婦人科腫瘍学会の3団体は9月、田村大臣に子宮頸がんワクチンの接種勧奨再開を求める要望書を提出。子宮頸がん征圧をめざす専門家会議も、6月14日の厚労省の「積極的な接種勧奨の一時中止」の措置を「非常に残念なこと」と表明していた。
全国子宮頸がん被害者連絡会の事務局長を務める池田利恵日野市議によれば、製薬会社によるロビーイングは徹底的に行われているという。池田議員は、IWJの取材に対し、専門家会議の実行委員長をつとめる自治医科大学附属さいたま医療センターの今野良医師が、「サーバリックス」を製造するグラクソ・スミスクライン社がスポンサーの新聞広告に何度も登場して、子宮頸がんワクチンを推奨していると語った。
ワクチンのリスクが語られない「予防接種研究会」
子宮頸がんワクチン推進派による巻き返しの動きは、これだけにとどまらない。
神奈川県の黒岩祐治知事は、9月に県で独自の「神奈川県予防接種研究会」を設置した。9月2日に開催された第1回目の研究会では、冒頭、黒岩知事自身が挨拶を行った。
神奈川県は、この研究会を設置した目的について、「今後の予防接種のあり方を神奈川県から提案するため」だと説明しているが、子宮頸がんワクチン被害者らから、実は研究会の委員のほとんどが、ワクチン推進派であるとされ、委員の選定の仕方を問題視する声が出ていた。
この人選の件について、10月25日の会見でIWJが黒岩知事に質問したところ、「推進派ばかりを集めたわけではないと認識している。(議論や選定の仕方に)問題はない」と明言した。
ところが、実際に研究会での議論がスタートすると、ワクチン被害者らの懸念が現実のものとなってしまった。現在までに9月、11月と2回の研究会が開かれたが、2回とも、ワクチン副反応のリスクに関して、議題にのぼることはなく、出席した委員からは一切言及がなかった。
予防接種の接種義務化を求める推進派の驚くべき発言
それだけではない。驚くべきことに、11月20日に開催された2回目の研究会では、委員らから、現状の「定期接種」(※注4)を「集団接種」にすべきではないかという意見があがった。つまり、接種を「義務化」せよ、というのである。これが何を意味するのか、日本における予防接種をめぐる経緯を、少し振り返ってみた。
現行の予防接種法では、予防接種の接種義務化はされていない。1994年の法改正で、義務化された接種、いわゆる「集団接種」の規定を、接種を勧奨し、努力義務とする「定期接種」に変更したためである。
(※注4)予防接種には、「定期接種」と「任意接種」とがあり、「定期接種」は、一部の季節性インフルエンザワクチンなどを除き、国や自治体が積極的に接種を勧めることが義務付けられているワクチンで、通常、接種費用もかからない。これに対し「任意接種」は、接種の勧奨が義務付けられているものではなく、接種費用も基本的に自己負担となる。
そうした予防接種法が施行された1948年から1990年代までの間に、各種ワクチンの副反応による被害が生じた。各地で集団訴訟が起こり、予防接種が大きな社会問題となった。この法改正が行われた背景には、そうした経緯がある。「接種の義務化」から、「接種の勧奨」へと法改正されることで、予防接種を行うかどうかは、個人の責任で、個人の自由意志によって選択すべきものに変わったのである。
つまり、研究会の委員らが言う 「定期接種」を「集団接種」にすべきではないかという意見は、日本の予防接種をめぐる考え方の変遷を真っ向から否定するものであり、時代の流れに逆行するものであると言える。
さらに、同研究会では、驚くべき発言が飛び出した。委員の一人である岩田眞美氏(横浜市健康福祉局健康安全部医務担当部長・健康安全課長)が、「大学においては、(予防接種が)努力義務ではないので、接種を義務化してもよいのではないか」と発言。大学に入学する際、予防接種を受けていることを条件とし、「接種していない場合は、入学を断ってもいいのではないか」とまで言い切った。「義務化」とは、つまりはワクチンの「強制」である。
岩田氏は、横浜市健康福祉局の職員であり、ワクチン被害者とも接している人物である。被害者らからの切実な声を常に聞いている環境にありながら、ワクチンの副反応問題に言及しないばかりか、逆にいかにしてより多くの少女たちにこのワクチン接種を強制するか、そちらの方向に前のめりになっているのだ。
同研究会では都道府県別の接種率のデータから、神奈川県が最下位だったことを「問題視」し、とりわけ横浜市・川崎市などの大都市での接種率が低いことを指摘した。
しかし、先にも述べたように、接種するか否かは、個人の自由意志で決めるのが日本における予防接種の現在の考え方であり、接種率の低さを悪いことだと単純に決めつけることは、接種する側の自己決定権をないがしろにする一方的な押し付けであると言わざるをえない。
少なくとも、接種の是非を選択できるだけの情報提供が充分に行なわれているかをまず議論すべきである。接種率の議論に移るのは、それからではないか。
IWJでは今後も取材を続け、被害者の女性たちから得た証言や家族の声を、動画とともにお届けする予定だ。次号のウィークリー第33号では、ワクチン接種勧奨の再開を待ち望む医師らのとんでもない発言の数々を一挙公開する。

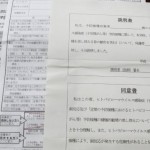





























ワクチンで発症消滅できたのは天然痘のほかまだない。
関連学会の「子宮頸がん予防HPV ワクチン接種の接種勧奨差控え延長について」12月26日声明によると、副反応はワクチン接種だけでなく、献血や通常の採血でもおき得るることとしている。声明は「慢性疼痛に対処できる医療ネットワークを形成し」とあるが、この「ネットワーク」は治療的対応の具体性に欠け、補償とともに所在のあいまいさを指すことは明白である。
すでに337万人の女性が子宮頸がんワクチンを接種しているのですか。
薬害肝炎救済法の施行後、フィブリノゲン製剤を使用していた病院名が新聞に一斉に掲載されましたが、
それをはるかに超える被害者が子供たちの中にいるのかもしれないと思うとぞっとします。
それも、病気の治療ではなくワクチンで!
新型インフルエンザのワクチンも、臨床試験の期間が極端に短いままに接種が始められ異様でした。
薬害に関して慎重にならざるを得ないような事態は何度も繰り返しているのに、さらに悪い事態を政府が引き起こしているのではありませんか。