元ユネスコ(国連教育科学文化機関)事務総長顧問を務めた服部英二氏の講演会が2014年8月1日(金)13時より、長野県諏訪市にある諏訪市文化センターにて開催された。
服部氏は京都大学大学院博士課程を経て、フランス政府給費留学生としてソルボンヌ大学博士課程に留学。UNESCO(国連教育科学文化機関)広報部主席広報官、文化担当特別事業部長等を歴任し、1994年に帰国、ユネスコ事務局長顧問に就任した。現在は、麗澤大学比較文明文化研究センター客員教授、道徳科学研究センター顧問を務める。1996年にフランス政府より学術功労章オフィシエ位を、2010年に全国日本学士会からアカデミア賞授与されている。
服部英二氏は、ヨーロッパ文明の特質を、「ロゴスとトーラ(戒律)、つまり、理と不条理が共存する文明だ」といい、「紀元前6世紀、アケメネス朝ペルシャでのバビロンの捕囚になったユダヤ人は、ゾロアスター教の影響を受けた。ここで口頭伝承を書き留めることを学び、バイブルの成立に至った」と説明した。
日本とヨーロッパ、とりわけユダヤ教との違いについて服部氏は、「日本では信仰と科学が対立したことはなかった。神道にも、仏教、儒教にも、科学を排斥する要素がない」。しかしヨーロッパは、「戒律、不条理の世界だ。アブラハムがやっと100歳になって子をもうけ喜んでいると、神はその子を犠牲に捧げろ、と命令を下す。これがユダヤ教で、ただ信じるしかない不条理の世界だ。だから、科学とも戦った」と分析した。
また、システィーナ礼拝堂のミケランジェロの天井画『創世記』について、「中世まで、キリストの父なる神の姿は描かなかった。それをミケランジェロが初めて、老人の姿で描き込んだ」と述べ、『最後の審判』の筋骨隆々のキリスト像に、ギリシャ神的な影響があることを指摘。「ここは神の殿堂ではなく、人間の殿堂を暗示させる」と語った。
また、専門の美術史では、「岩窟の聖母だけでなく、モナリザも2枚ある」と言い、証拠として、ラファエロのスケッチが残っていることと、その1枚は、やや若い顔立ちで、今、スイスの銀行に保管されているなど、興味深い話も述べた。
理と不条理が共存するヨーロッパ文明
服部英二氏は「ソルボンヌ留学中、友人たちと文明の成熟度は個人の確立で測れる、と議論した憶えがある」と当時を振り返る。そして、個の確立は、14世紀末に始まった「再生」の意味を持つルネサンスから始まり、17世紀の科学革命、18世紀の産業革命から、現在のヨーロッパにつながっている、と話した。
まず、基礎知識として、ヨーロッパの由来を、ゼウスとフェニキアの王女エウロペアの古代ギリシャ神話にたどった。「それはオリエント(東方)との合体を示すが、それを消し去っている」と話し、その後、ユダヤ・キリスト教とギリシャ・ローマ文明の合体を経て、12~14世紀、スコラ学派が、理と不条理を共存させ、一方の思想がルネサンスに向かい、もう一方が宗教改革に向かったと解釈した。
ヨーロッパの出自はルネサンスが創りだした
服部氏は、紀元前8世紀に地中海を制覇していたフェニキア文明の勢力図を映し、フェニキア(現在のレバノン辺り)が重要な位置を占め、カルタゴとのポエニ戦争でローマが勝ち、文明がフェニキアからローマに移ったと、ヨーロッパ文明の生い立ちをたどり、「ルネサンスは人間開放の輝かしい文明であったのか? 人類史をどのように変えたのか。どのようにして起こったのか。文芸復興なのか?」と問いかけた。
「ヨーロッパの出自をギリシャ文明に求める風潮は、ルネサンスに起こった。そこでオリエント、ビザンツ文明を消し去り、突如、泡から生まれたイメージを打ち立てた」と述べ、「1860年、ブルクハルトの『イタリア・ルネサンスの文化』で、その幻想がさらに、強く裏づけられたのではないか」と言う。
地獄への恐怖が最後まで残ったルネサンス
次に服部氏は、16世紀、ジョルダーノ・ブルーノやガリレオ・ガリレイなど異端審問をとりあげ、理と不条理の共存が続いた理由も分析した。
ヘブライ的超越神の排除、ギリシャ的理性の獲得、パースペクティブ(遠近法)を含む個人の確立、神に観られている立場から、神を観る視点の変化、意識は神との合体から、その知覚への移行などと、聖と俗の拮抗が数世紀続いた。なぜなら、地獄への恐怖は残ったからだと説明する。
そして、コジモ・デ・メディチが、プラトンの翻訳をさせ、ダンテ、ペトラルカ、ボッカッチョが美術の巨匠より先に活躍した。ラファエロのアテネ学園のスライドを見せ、「プラトンとアリストテレスの本の持ち方に、思想と自然への受け取り方がわかる」と面白い見方も解説した。
ルネサンスの前にイスラームが席巻したヨーロッパ
12世紀、(東ローマ帝国の首都)コンスタンティノープルを第4次十字軍が征服。東ローマ帝国が実質上、没落し、ヴェネチアの隆盛をもたらす。1453年、再びオスマントルコが奪取し、イスタンブールが興る。
8~15世紀、イベリア半島でイスラーム文明が繁栄、キリスト教と融合したのが、モサラベ芸術になった。トレド図書館には、アラビア語で古代ギリシャの著作が保存されていて、スコラ学派たちがラテン語に翻訳する。
服部氏は「イスラームは、8世紀からバグダッド、コルドバ、ケルーアン、コンスタンティノープル、パレルモ、トレドが文化センターになった。ヴェネチアは、東方のビザンチン(イスタンブール)と交流があった」と言い、礼拝の窓を追加したアヤソフィア、ビザンチン様式のモザイク装飾がされているヴェネチアのサンマルコ寺院、バチカンのサン・ピエトロ寺院などのスライドを見せた。
物を直接、扱う学問は蔑まされたヨーロッパ
塩野七生氏の説くルネサンス論を取り上げ、それは古代ギリシャ時代の、テオリア(観照)、プラクシス(実践)、ポイエーシス(創作)の合体だという。職人(奴隷)が行なうポイエーシスが、ルネサンス期に、他の2つ(テオリアとプラクシス)と合体したので巨匠が輩出した、と述べ、服部氏もそれについては合意し、「なぜなら当時、マテリアル(物)を直接、扱う学問がいちばん下だった。哲学、神学、数学と序列があり、ゆえにフランスの大学には、工学部は作られなかった」と語った。
そして、「日本は素材に触れることは卑しいことではないのでルネサンス型。中国は手を汚すことは卑しいと考えていたので、ギリシャ型だ」と述べた。
教会との自然科学の勝利が科学革命につながった



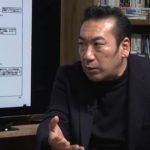

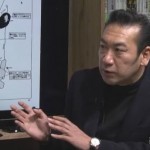























レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』が取り上げられると、体が乗り出してしまいます。
フランスの侵略に脅かされていたフィレンツェで、レオナルドとマキアヴェッリがチェーザレに仕えていましたが、
彼らはいかに戦争を早く終わらせるかというアイデアを模索していたのではないかと思います。
『最後の晩餐』は聖書がモチーフになっていますが、教会の壁に描かれたものではありません。あの壁画が描かれた場所にレオナルドが通う様子を思うと、周囲の街の風景や暮らしを未来に残すための彼の発明のように思います。
それをガウディが引き継いだのかどうかはわかりませんが、奈良の大仏さまもどこか通じてきます。
差別が介在できないような卓越さと解放感。
イタリアの街には彫刻があふれ、学生さんがデッサンをする姿を見かけました。
同じ絵は描けないジレンマ。自分自身と向き合う作業を繰り返す姿が街中にあふれていました。
レオナルドたちからのギフトを現代人が引き継いでいる様子を見たのだと思います。