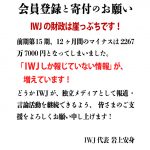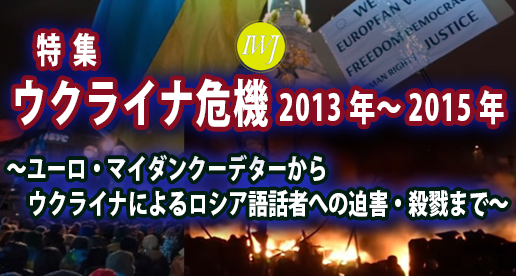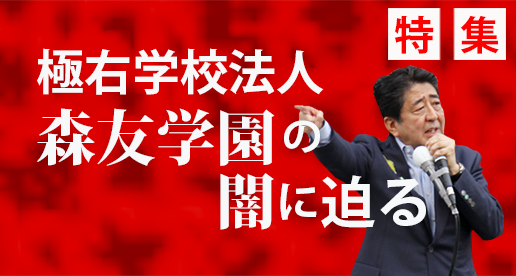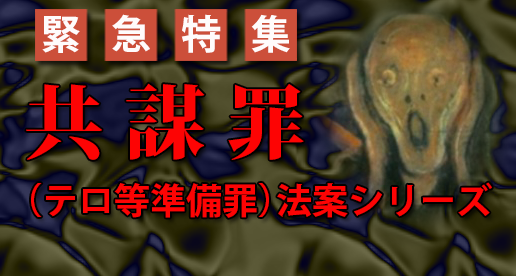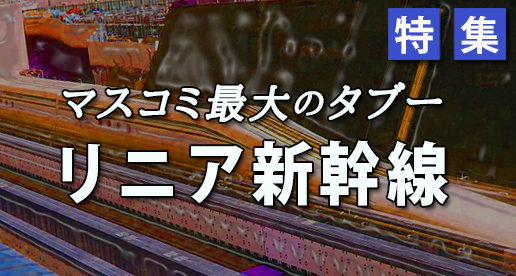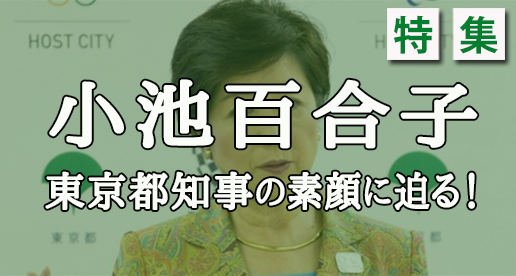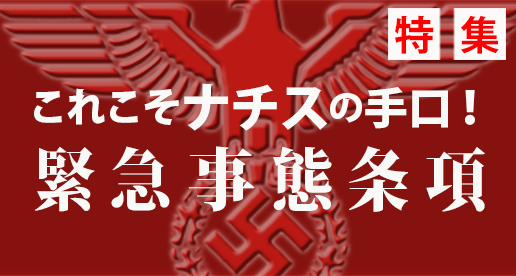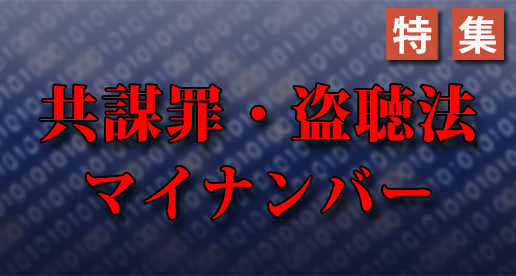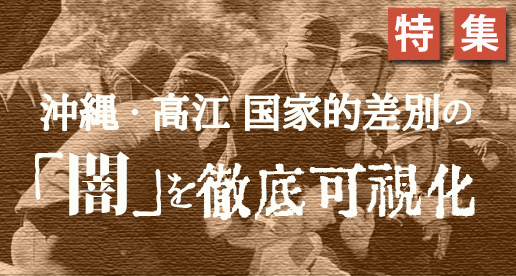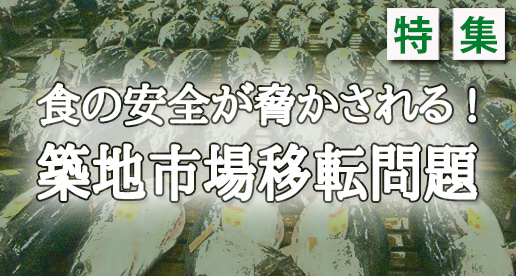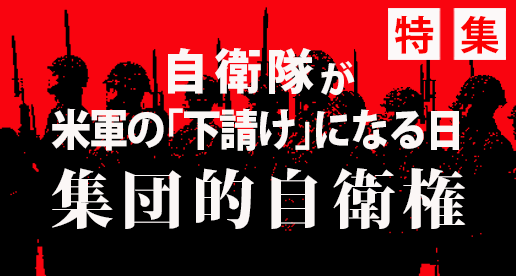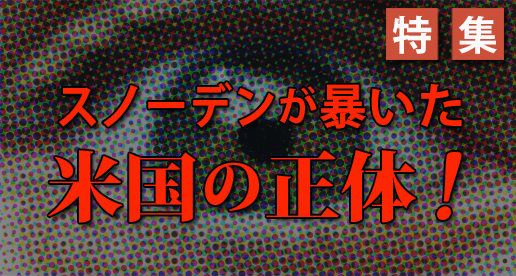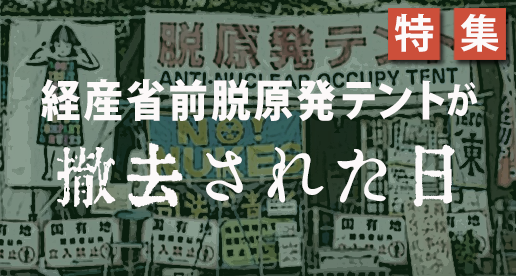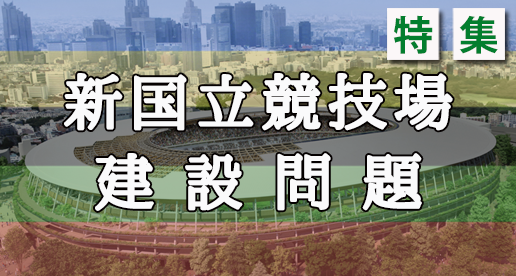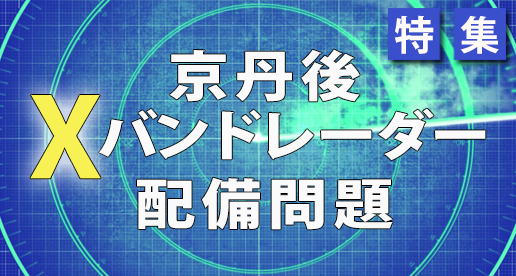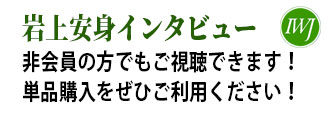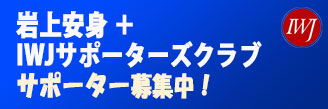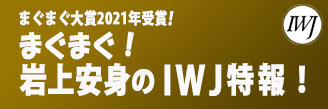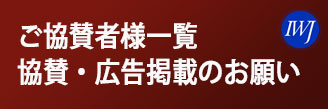岩上安身のインタビューにも、ご登壇いただいている、松里公孝東京大学法学部教授が翻訳された、ルガンスク人民共和国とドネツク人民共和国に関するきわめて重要な論文を、前半と後半に分けてお届けします。
論文の著者はドネツク国立大学政治学講座のキリル・ヴァレリエヴィチ・チェルカシン准教授、題名は「ドンバス2共和国の内政とそれらのロシアへの(再)統合の諸方策」です。
日本では、ウクライナ紛争の大きな要因となった、2014年から行われてきた、ウクライナの国内でのロシア系の自国民に対する迫害や虐殺について、語られることも、ミンスク合意で高度な自治権を認められていたはずのルガンスク人民共和国とドネツク人民共和国について語られることもほとんどありませんでした。
そのプロパガンダ支配の状況は、今もほとんど変わりません。これらプロパガンダ支配から逃れている者は、知識人では、松里教授のような幾人かの人々、メディアではIWJのような独立メディアの、ほんのごく一部しかいません。
マスメディアと政府は、戦況がロシアに有利となり、トランプ政権の誕生で、前政権のバイデン政権とウクライナに対する外交政策がガラッと変わっても、なお、大きく変わっていませんし、変わろうともしていません。
松里教授は、チェルカシン准教授について「ドンバスの、ウクライナからの分離運動を、(ドンバスの)内側からずっと見ている」貴重な研究者として、中国で企画された「ウクライナ危機に関する国際プロジェクト」に紹介し、チェルカシン准教授が上記論文を執筆した、とのことです。
ただし、「ロシア語では絶対に公表しない」ということが、執筆の条件でした。そして、結局、中国でもデリケートな内容だとして発表されなかったため、英語訳も、中国語訳もウクライナ語訳もありません。現在は、松里教授が翻訳した和文でしか読めない、貴重な資料となっています。
その経緯は、1月31日に行われた、岩上安身による東京大学法学部・松里公孝教授インタビュー第1部・第3回を御覧ください。
チェルカシン准教授による「ドンバス2共和国の内政とそれらのロシアへの(再)統合の諸方策」は、以下の大項目からなります。
・ドンバスの2共和国が生まれた諸前提
・ルガンスクとドネツクの人民共和国の内政の基本原則
・人口と経済
・憲法体制
・ルガンスクとドネツクの人民共和国における政党制と選挙制
・ロシアへの(再)統合のための諸方策
・結論
前半では、「ドンバスの2共和国が生まれた諸前提」と「ルガンスクとドネツクの人民共和国の内政の基本原則」「人口と経済」「憲法体制」をお送りします。
また、ぜひ、IWJ会員登録をして、岩上安身による松里公孝教授のインタビューの全編を、以下より御覧ください。
【訳者(松里公孝東大教授)より】
ここに紹介する論文は、ドネツク大学歴史学部准教授のキリル・チェルカシン氏が、2014年から2022年までのドネツク・ルガンスク両人民共和国の内政と、それらのロシア指導部との関係について書いたものである。
チェルカシン氏は、本来は投票地理学の専門家だが、上海の華東師範大学が組織したウクライナ危機に関する国際研究プロジェクト(Ministry of Education, PRC, 22JJD810009)に参加し、ロシア語では公表しない、という条件の下で本稿を書いた。
チェルカシン氏は、本稿を2024年2月には上梓していたが、華東師範大学のプロジェクトリーダーは、本稿の学術的な価値は認めつつも、あまりにも微妙な内容を含むため、中国語では出版できないという残念な結論に達した。そのかわり、日本語に訳して発表するのは結構、という許可をいただいた。
訳はできるだけ直訳のスタイルを守ったが、日本人にわかりにくいところは[ ]で言葉を補ったり、訳注をつけたりした。
著者はドネツク在住の政治学者であると同時に、ドネツク人民共和国最高会議(2014年4-11月に存在していた議会)の代議員であった。
そのため本稿は、日本で報道されているドンバス紛争や露ウ戦争のイメージからはかけ離れているだろう。
読者は、著者の価値判断に違和感を感じるところがあっても読み飛ばし、現地の人間ならではの事実の証言に関心を注いでいただきたいと願う。
なお、訳者が書いた『ウクライナ動乱―ソ連解体から露ウ戦争まで』(ちくま新書、2023年)にもドンバス現代史は詳しいので、併読をお勧めしたい。
東京大学大学院・法学政治学研究科・教授 松里公孝
ドンバス2共和国の内政とそれらのロシアへの(再)統合の諸方策
キリル・ヴァレリエヴィチ・チェルカシン
ドネツク国立大学政治学講座准教授
本稿で提示される評価は、生まれて以来ドンバス、ドネツク市に住む筆者の個人的見解にすぎない。
筆者は、ドネツク人民共和国の生成過程に参加した。本稿で述べられる情報の全てに、注が付けられるわけではない。なぜならそれら情報の一部は、出来事の関与者との会話や筆者自身の観察により取得されたからである。
ここ数年、国際社会における紛争が激化している。事態の不幸な発展が続けば、これら紛争は第3次世界大戦と人類絶滅に発展しかねない。
これら国家間紛争の一事例が、かつてのウクライナであり、2013年末以降それが生み出した「ウクライナ危機」である。
事態の破滅的展開を防ぐためには、この危機の原因と前提、関与者たちの利害と立場を解明する必要がある。
本稿の執筆意図は、そこにある。
現代のウクライナと西側の研究史においては、ウクライナ危機は、多くの場合、偏向し、一面的な形で描かれている。
権威主義的で帝国主義的なロシアが、民主的で自由を愛するウクライナに襲い掛かり、その領土の一部を奪ったというのである[1]。
そのような偏向した見方からは、ドンバスの2共和国は、「ロシアの侵攻」を助けるためにロシアによって作られた疑似国家だということになるのである[2]。
そのような解釈が、西側の支配下にあるマスメディアや、学術出版物においてさえ、氾濫している。西側や、西側の統制下にあるウクライナにおいては、ドンバス2共和国の諸問題は、無視されている。
世界的に著名な政治学出版物において、ドネツクとルガンスクの人民共和国について、また「ウクライナ危機」についてまがりなりにも客観的であろうとする論文が少ないのは、そのためもあろう[3]。
ロシアの研究史においても、このテーマは十分に扱われていない。
なぜなら、ロシア連邦がドネツクとルガンスクの両人民共和国を承認したのは比較的最近のことであり(2022年2月)、それまでは、ミンスク合意にもとづいて、それら地域を(それまでに刷新されていると仮定された)ウクライナに再統合する政策がとられていたからである。
政治学において、このテーマでの業績はあまり多くなく、あるにしても国際関係や社会学的な側面に注目したものばかりである[4]。
ドンバスの内政に関する学術的業績は一握りに過ぎない[5]。
だからこそ、本稿は、2014年から2023年までのドンバス2共和国の内政の基本原則と、それらのロシア連邦への統合の諸措置を明らかにすることをめざすのである。
西側の視点は、読者に周知であろうから、本稿はロシア愛国主義の視点をとる。
本稿で「ロシア」という場合、第一義的には「歴史的ロシア」を意味している。それはロシア連邦よりも広く、ベラルーシ、ウクライナの大部分、伝統的に東スラブ・正教世界に属してきた他のいくつかの地域(たとえば沿ドニエストル)を含む。
【ドンバスの2共和国が生まれた諸前提】
<2014年2月のクーデタ>
旧ウクライナ領における大規模な暴力と武力対立の引き金になったのは、2014年2月に起こったクーデタである[6]。
このクーデタは、ウクライナ住民の中でロシア連邦に友好的な感情を抱く層の、地政学的・民族文化的志向に配慮することを拒絶し、またロシア連邦そのものの国家利益と安全保障を無視するものであった。
キエフでのクーデタは、汚職や「ヤヌコヴィチ体制」による権力簒奪との闘争、言論の自由、国の一層の民主化を含意すると考えられたウクライナの親西側的な地政学的選択といった、一般民主主義的なスローガンのもとで行われた。
にもかかわらず、権力を掌握した勢力には、全国民的な対話を行ったり、親露的な政治勢力に常時投票してきた、ウクライナ南東諸地域の広範な大衆の意見を考慮したりする意図は毛頭なかった。
<ウクライナ東西の対照性>
2014年のクーデタまでは、ウクライナは「分裂した」国家であった。国の住民のおよそ半分は「親露的な」、残り半分は「親西側的な」政治勢力を支持していた。
ロシア寄り、西側寄りのうち、いずれの統合ヴェクトルをとるのかが、ウクライナ政治において鍵となる争点のひとつであった。
選挙得票は、地理的に顕著に分化していた。
2000年代初め以降、「親露的」勢力は、都市化と工業化が進み、全国人口の48%が住む南東10リージョンにおいて伝統的に当選者を出した。
概して「親西側的な」勢力は、都市化や工業化において劣り、全国人口の52%が住む西部・中央部の17リージョンにおいて当選者を出した。
このような、およそフィフティ・フィフティの力関係のため、1991年に「独立」を受け取って以降、国の最高権力の座には、「親西側」勢力、「親露」勢力が交互に就いた。
二つの対立する「プロジェクト」間の相違は、ほぼすべての争点に及んでいた。
◆地政学的選択:ロシア及び旧ソ連共和国とのできるだけ緊密な統合か、反対に、欧州・大西洋機構に組み込まれようとする(最終的にはEU・NATOに加盟する)志向か。
◆言語問題:ロシア語に国家語(第2国語)、またはできるだけ高いステータスを保証するか、あるいはウクライナ語のみを国家語とするか。
◆歴史的記憶(特に第2次世界大戦について):ロシアと共に獲得した諸勝利(特にナチズムへの勝利)を尊ぶか、あるいは第2次世界大戦中に歴史的ロシアに反対した勢力、なかでも(ウクライナ民族主義者組織、ウクライナ蜂起軍、SS師団「ガリツィヤ」などの)第2次世界大戦中のウクライナ領でナチスと協力した勢力を崇拝するか。
◆国制:連邦化も視野に入れつつ、リージョン(地域)に大きな権利を付与するか、あるいは厳格な中央集権、首都に最大限の権限を集中する単一制国家を維持するか。
◆経済発展:以前は単一だった「ソ連共通の」経済圏内での協力を志向するか、あるいは欧米、西側、またはグローバルな経済ネットワークに一義的に包摂されることを志向するか。
上記の違いは、ウクライナの西部と東部の社会構造の違いから生じていた。
◆東部ウクライナ社会は、顕著に多民族的であった。住民はロシアやウクライナの様々な地域の出身者で、大ロシア人の比率が高く、いくつかの地域では大ロシア人が多数派でさえあった。露ウ民族以外の「第3」民族集団も有意な比率を占めていた。
また東部では、ロシア語が優勢であった。住民の大多数にとってロシア語が母語で、民族間コミュニケーションもロシア語で行われた。また東部は都市化・工業化が進んでいた。
◆西部ウクライナ社会は、顕著に単一民族的で、ウクライナ語が優勢であるか、住民は露ウ混淆言語で会話した。農業が優勢で、経済的に遅れていた。西部7州のうち5州では、農村人口が過半を占めていたのである。
以上のような諸リージョン(諸地域)の民族・文化的相違に、経済的相違が加算された。
ウクライナ主義のイデオロギーからすれば、半人前とみなされていた南東諸リージョンが、国のGDPの70‐80%を生み出していたのである[7]。
<「ロシアの春」=南東部の抵抗>
1991年から2014年までは、ウクライナの東部と西部は単一の国家の中で共存していた。様々な矛盾にもかかわらず、諸問題は、多くの場合、平和的に(少なくとも武力を用いずに)解決された。
2013年末から2014年初めにかけてのユーロ・マイダン・クーデタが、この伝統を破壊した。
※ここから先は【会員版】となります。会員へのご登録はこちらからお願いいたします。ぜひ、新規の会員となって、あるいは休会している方は再開して、御覧になってください!
https://iwj.co.jp/ec/entry/kiyaku.php
(会員限定・続きを読む :https://iwj.co.jp/wj/member/archives/527086)
<ここから特別公開中>
2014年2月のキエフでの武力クーデタへの回答として、また当時ロシア政府が、自らの支配下に入れたクリミアの例に喚起されながら、かつてのウクライナの南東部で、抗議運動「ロシアの春」が拡大した。目標は正反対だったにもかかわらず、「ユーロ・マイダン」と「ロシアの春」の活動家は、大衆抗議行動、行政施設の占拠など、共通した方法論で行動した。
2月末から3月初めにかけて、巨大な抗議行動が、ドンバスとノヴォロシア[8]の全体を席巻した。
しかし、キエフの新政権は、これら抗議行動を無視し、それらのリーダーを逮捕する方針をとった。
キエフ政権の支配を離れたリージョンには、3月、ウクライナ軍が補強的に派遣された[9]。抗議者との真剣な対話は、まったく行われなかった。
言うまでもなく、抗議する活動家にとって最も望ましかったのは「クリミアのシナリオ」(ロシアとの再合同)であった。
ではノヴォロシアの普通の住民の大多数はどうかというと、少なくとも、キエフの反露的な新体制を支持はしていなかった。
首都で権力簒奪した勢力は、いかなる妥協も拒否した。
当時のロシア連邦指導部の見解を考えれば、ウクライナの連邦化、ウクライナの中立維持、ロシア語の国家的地位などで、妥協を達成することは十分に可能だったにもかかわらず。
3月には、ウクライナの新体制は、強制力による抗議行動の鎮圧方針を選んだ。
抑圧と要求無視への回答として、「ロシアの春」の活動家は、4月7日、かつてのドネツク州、ハリコフ州において「人民共和国」の樹立を宣言した。少し遅れてオデッサ州、ルガンスク州がこれに続いた。
これらリージョンの、自立のための住民投票の日付が決められた。しかし、その後も、キエフの新政権は、締め付けを強化するばかりだった。
2014年4月7日、ウクライナ大統領代行A・トゥルチノフは、ハリコフ、ドネツク、ルガンスクにおける行政官庁の占拠、ハリコフとドネツクの人民共和国の樹立宣言を受けて、危機管理司令部の創出を発表し、「武器を手に取ったものに対しては、反テロ措置がとられるだろう」と宣言した[10]。
これらの事態は、I・ストレリコフの部隊が、ドンバスに来る前に起こっている[11]。
結果的には、クリミアと一部ドンバスを除けば、親露運動は強制力により、鎮圧された。
しかもこれは、野党的な政治活動家に対する拷問と殺害、ドンバスの民間住宅地区への無差別砲撃など、ウクライナ側からの数多くの犯罪を伴っていた。
ルガンスク・ドネツクの人民共和国の一部領域は、ロシアからの限定的な軍事援助のおかげで踏みとどまることができた。
その結果、かつてのウクライナの親露住民の完全なジェノサイドは、避けることができたのである。
【ルガンスクとドネツクの人民共和国の内政の基本原則】
<ロシアより急進的だったドンバス>
2014年から2023年までのドネツクとルガンスクの両人民共和国の内政を、1本の論文の中で描くことは困難である。よって、本稿ではそれら内政の基本原則についてのみ論ずる。
両共和国の樹立は、ドンバスの「ロシアの春」活動家の元来の目標ではなかった。むしろ、ロシアの土地をまとめて、キエフで権力を獲得した反露体制からの独立を達成するという、基本目的を達成するための第一歩と考えられていた。
この点について、ドンバスの「旧来の」経済・政治エリートの大部分は、地域住民の多数派と同意することはできなかった。
地域エリートの大部分は、自分の富、企業、特権的地位を失わないために、キエフの新政権と裏切り的な合意を交わして、マイダン後のウクライナの権力構造に入れてもらう気分になっていた。
そのため、地域の経済・政治・行政エリートの上層部で、2014年のドンバス蜂起を支持した人は、ほとんどいなかったのである。
蜂起が大衆的な性格を帯びたもう一つの理由は、それを指揮する単一の組織、単一の中心がなかったことである。蜂起者の利益を代表する、地域の政治経済エリートもいなかった、と言って過言ではない。
ドンバスにおける「ロシアの春」活動家の大半は、「クリミアのシナリオ」(ロシアとの再統合)が繰り返されることを望んでいた。これが目標なら、主体性も主権も必要なかった。そのようなものは、ロシア連邦が「与えてくれる」と想定されたのである。
しかし、クレムリン指導部の計算はいささか違った。彼らは、クリミア併合後も、親露的あるいはせめて中立的な、統一したウクライナを保持したいと考えていたのである。
このような計算は、まったく現実離れしていた。クリミアという最も親露的なリージョンのひとつを切り離したことで、旧ウクライナ(全体)の選挙バランスを壊してしまい、ウクライナ全域における反露の波を起こしてしまったからである。
なぜロシア指導部が、そのような決定を下したのかについて、本稿で追究することはしない。
しかし、ドンバスで活動していた「親露」勢力と、ロシアからそれを支持していた勢力は、やや異なっており、異なる目標を持ち、事態の進展を別様に解釈する可能性があったことだけは、ここで確認しておこう。
2014年春の終わりに、あるロシア市民が旧知のドンバス蜂起参加者に言った言葉だが、「あなたたち(蜂起者)は、今のロシアにソ連を見ているようですが、今のロシアはウクライナと同様、オリガーク国家ですよ」。
<ロシアからの「落下傘部隊」>
2014年春の後半から初夏にかけてルガンスク・ドネツクの人民共和国に送り込まれた「管理のための落下傘部隊」(A.ボロダイ、V.アンチュフェエフ、A.カラマン、Iu.ピンチュクなど )の主な任務は、事態の展開をロシア指導部のコントロール下に置くことだっただろう。
ドンバスの蜂起指導者は、これに対してあまり抵抗しなかった。
なぜなら、蜂起者の主要目的の一つは、ドンバスと全ノヴォロシアをロシア領に再統合することだったからである。そしてこの「管理のための落下傘部隊」が、その方向(ロシアへの編入)での一歩と考えられたのである。
2014年春の終わりごろから、おそらく、ロシア指導部はドンバスの蜂起をむしろ問題[頭痛の種]とみなすようになり、ウクライナで生じた事態から最小限の損失で抜け出すにはどうしたらいいか悩んだ。
新しく選ばれたウクライナ大統領であるペトロ・ポロシェンコとの協力に賭けてみようという話になり(投票日前夜、V.プーチンは、ロシアはウクライナ大統領選挙を認めると表明した[12]。選挙後においては、いくつかのマスメディアの評価によれば、プーチンは「ウクライナ国民の選択を、総じて肯定した」[13])。
<地元幹部の後見>
ルガンスク・ドネツクの両人民共和国の公職には、地元出身者ではあるが、完全に[クレムリンの]コントロール下にある幹部があてられた。
両人民共和国はロシア連邦によって創出されたとは言えないが、2014年夏以降、両共和国は、ロシア指導部によって、次第に強くコントロールされるようになった。
それ以降は、両人民共和国の指導者たちは、形式的には自立的だが、クレムリンの主な決定を執行するような人物たちでなければならなかった。
2014年8月、両共和国の首長職に、ドネツクのA.ザハルチェンコ、ルガンスクのI.プロトニツキーが就いたが、ロシアの監督者が彼らを選んだのである。
ザハルチェンコ、プロトニツキーは、とりわけ、「ミンスク合意」に調印する義務を負った。「ミンスク合意」によれば、ドンバスは(刷新された)ウクライナに戻らなければならず、両共和国は事実上解体され、「ウクライナのドネツク・ルガンスク州の特定諸郡」(ORDLOU)に変質してしまったのである。
当時の「親ウクライナ政策」、特にルガンスクとドネツクの人民共和国に責任を負ったのは、ロシア大統領補佐官のウラジスラフ・スルコフである。
2015年初めまでに、すべての最重要省庁に、ロシアからの監督者(クラートル)のシステムが創出された。
このシステムの下、すべての枢要な決定は、モスクワでなされるか、モスクワから派遣された現地の監督者によってなされた。両人民共和国の指導部は、これら決定に従った。
監督する側は、「監督されるべき」予備役[14]のスキャンダルのネタを握っていた。だから監督される側は、上から降りてくるのが、いかなる決定であれ、拒絶することは難しかった。
結果として、ルガンスク・ドネツクの両人民共和国の指導的な職には、最も理念的な人々ではなく、反対に、特権的な地位を獲得し、保持するためにはいかなる妥協にも応じるような人々がしばしば任命された。
そうした人々は、表面的な忠誠心を誇示しながら、また金銭問題で「許容範囲を越えぬよう注意しながら」、共和国の支配領域でほぼ無制限の決定権を得た。
このような特殊な幹部政策は、多くの異常事態を生んだ。
ルガンスクとドネツクの両人民共和国の内政は、モスクワから(しばしばプーチンの部下たちから相互未調整のままに)降りてくる決定、現地の監督者と任命された共和国指導部の即興的決定の奇抜な混合物となった。
典型的な例は、「小ロシア」国家を創出するという2017年における[ドネツク人民共和国元首ザハルチェンコの]宣言である。これはモスクワの忠告を受けて、すぐに取り消された。
<非承認が引き起こす経済苦境>
これらの行き過ぎがあったにせよ、ロシア連邦と可能な限り緊密に統合するという両共和国内政の総路線は保持された。それ以外の政策は、両共和国住民にも、政治活動家にも理解されなかっただろう。
ドンバスをウクライナに再統合すべきと望んでいたロシア連邦内の勢力も、再統合が可能になるのは、ウクライナが刷新され、最低限でもロシアに敵対的でなくなった場合だと考えていた。
2014年から2022年にかけての「非承認地域」というステータスは、現地住民に多くの困難をもたらした。
特に、低賃金(ロシアだけではなく、ウクライナと比べても低かった)、賃金遅配(特に工業分野で深刻だった)など経済的な困難が深刻だった。
これらの事実は、住民の不満を呼び、いつどうやって秩序を打ち立てるのかという正当な疑問が寄せられた。
こうした「未解決問題」に罪がある者として、かつてウクライナのオリガークだったS.クルチェンコが非難された。彼は、何らかの方法で(とりわけ会社「貿易サービス」を通じて)両人民共和国経済の相当部分をコントロールするようになっていたのである。
おそらく、経済面で生起していた「無秩序」を最も説得的に説明するのは、傭兵会社ワグネル指導者のエヴゲーニー・プリゴジンの言葉である。
プリゴジンによれば、最高指導部の個々の指導者(とシロヴィキ[15]) が両共和国の経済過程を管理し、その混乱から最大限の利益を得ていた。
「ドンバスは切り分けられた。ドンバスは様々な人々によって略奪されつくした」。
この文脈では、「グレーゾーン」[非承認地域]のステータスは、あれこれの人物にとって都合が良かった。なぜなら予算を横領し、非合法な経済活動を行い、法外な利益を得ることができるからである[16]。
特別軍事作戦の開始、ロシアによる両人民共和国の承認、とりわけそれらのロシア連邦への併合後は、これらの違法経済操作の大部分は実行不可能になった。
【人口と経済】
<人口>
2014年前夜には、ウクライナ人口4500‐4600万人のうち、ドンバスには700万人から750万人が住んでいた。
人口の概数しかわからないのは、ウクライナ全国人口調査は、2001年に行われたのが最後だからである。ウクライナ政府は、人口の減少を表沙汰にしたくなかったのである。
2014年から2021年までの軍事対立で、国連人権高等弁務官事務所の資料によれば、14200人から14400人が死亡した。
内訳は、ウクライナ軍事組織の構成員が4400人、ルガンスクとドネツクの人民共和国軍事組織の構成員が6500人、3400人が民間人とされている[17]。
非公式データによれば、約5万人が死亡したとされる[18]。
著者は、後者の方が実態に近いと思う。
紛争が部分的に凍結された2015年初めまでに、両人民共和国はかつてのドネツク、ルガンスク州の3分の1を実効支配していた。そこには両州住民の50‐60%が居住していた。
面積と人口の間に比例関係がないのは、ウクライナがドンバスの辺境農村地帯を支配下に置き、両人民共和国が人口稠密なドンバス中心部すなわち大都市の多く(ドネツク、ルガンスク、マケエフカ、ゴルロフカ)と炭鉱地帯を支配下に置いたことを示している。
2014年の軍事的衝突と、その後の非承認共和国としてのステータスは、ドンバスからの大量の人口流出を招いた。
流出の規模を計ることは難しいが、ウクライナは150万人がドンバスからウクライナ支配地域への難民(「一時的移民」)になったと発表しているし、ロシア連邦は200万人がドンバスからロシアに移住したとしている[19]。
おそらく、そのあわせて350万人の大多数は、ドンバスまたは両人民共和国から一時的に移住したにすぎないだろう。たとえば、ウクライナの支配領域で然るべき社会保障(年金など)を受けるためだとか、ロシアで短期間働くためだとかである。
特別軍事作戦の開始直前、両人民共和国の国家統計委員会資料によれば、あわせておよそ350万人が両共和国に住んでいた[20]。人口減少は、非承認ステータスに起因する、ドンバス経済の危機的状況によって引き起こされた。ドンバスにおいては、一連の経済分野が満足に機能することができなかったのである。
<経済>
2014年の戦争前夜には、ウクライナ面積の4%、人口の10%しか占めていなかったドネツク州が、国のGDPの17%、工業生産の17%、輸出の25%を稼ぎ出していた[21]。
これらの高指標の相当部分は、ドンバス地域にある冶金工場の生産物を世界市場で、よく西側で言われたように「ダンピング価格で」売ることで、もたらされていた。
当時、このビジネスの相当部分は、ドネツク/ウクライナのオリガークであるリナト・アフメトフが支配していた。
2014年以降、ルガンスクとドネツクの人民共和国領域の冶金は、息も絶え絶えの状態になった。あれこれの企業が、半ば資産凍結状態で営業しているのみで、輸出向けの生産など話題にもならなかった。
石炭採取量も、著しく縮小した。石炭を必要とするウクライナとの半ば非合法な石炭取引は、困難をやや緩和したが、全体としては石炭分野は大きな損害を受けた。
鉄道輸送も、同様である。ドンバスにおける鉄道網の稠密さは、世界最高水準だった。
ロシアは、国際的な鉄道法制を順守して、ルガンスク・ドネツクの人民共和国との関係では鉄道輸送を利用しなかった。ウクライナは、散発的にしか鉄道を利用しなかった。
以上の結果、ドンバスの両共和国の領域では鉄道輸送の可能性が限定されていた。以上、全てが工業分野での賃金遅配を生み、労働者のストライキに至ることもあった[22]。
特徴的なことだが、2017年まで、ルガンスクとドネツクの人民共和国では、ウクライナのオリガーク(アフメトフなど)が経営するあれこれの巨大企業(炭鉱など)が合法的に営業しており、そこでは労働者の賃金はフリヴナ[ウクライナ通貨]で払われた。
そののち、これら企業の「国有化」が行われた。噂によれば、現在でもあれこれの巨大企業やその施設(建物など)は、営業しているものも資産凍結されたものも、「ウクライナの所有者」に帰属している。それら所有者は、自分の企業が「刈り取られないよう」「身代金」を「然るべきところへ」払っているとのことである。
ルガンスクとドネツクの人民共和国の統計の多くは、非公開であるか、信用できないかである。近年のドンバスの経済状況は、本稿とは別個の研究の対象である。
しかし、著しい人口流出が起こったこと(両人民共和国人口の少なくとも30%は流出した)、残った住民のうち、多くがロシア連邦の「旧」リージョンに出稼ぎに行くことで、生計を立てていることは事実である。
しかし、出て行った人の大部分が、ドンバスとのつながりを最終的に失ったわけではない。なぜならここに彼らの親戚がおり、住居が残っているからである。
石炭産業と重工業は、全体として著しく縮小した。
この衰退は、商業、サービス業、軽工業、農業の活性化、労働人口の公共セクター(公務員、教員、学生など)への移動によって部分的には相殺されている。「平和経済」の縮小が、軍が兵員を補充できる理由のひとつだった。
現在では、ドンバスで、ウクライナと西側の会社が占めていた場所は、ロシア企業によって完全にとってかわられた。
両共和国の住民多数派の生活水準は、ロシア連邦の「古参リージョン」より低いが、ウクライナの生活水準は、おそらく既に追い越している。総じて、非承認国家・グレーゾーン時代と比べれば、経済分野では明確な肯定的前進がみられる。戦線から遠い郡での建設ブーム、賃金上昇、経済活動の活発化、いくつかの産業分野の活性化などである。
【憲法体制】
<独立当初は社会主義の議会制>
ドネツク人民共和国の国家独立宣言では、共和国の国制は議会制、と規定されていた。つまり、「ドネツク人民共和国最高会議のみが、ドネツク人民共和国人民の名で語ることができる」とされた。
そのうえ、「他者の労働の結果を取得することを除く、憲法によって承認されたすべての所有形態の自由な発展と擁護のための条件」を保証しつつ、「同時に集団的な所有形態が優先される」と定めた[23]。
このような[左派的な]方向性は、これら文書を起草したのが、ウクライナ共産党の代表者の一人であったボリス・リトヴィノフであったことにより生まれたものである。
総じて、このような方向性は、抗議者の一般民主主義的・反オリガーク的な気分に合致していた[24]。ここに述べたことは、ルガンスク人民共和国の建国諸文書にも共通している。
そもそも、それらは、ドネツク人民共和国の諸文書を写したものにすぎなかったからである。
しかし、ほぼ建国直後から、国家建設原理の変化が起こり始めた。
2014年5月14日には、ドネツク人民共和国の最初の憲法が、最高会議により採択された。6月14日には、この憲法は改正された。しかし、5月の憲法にも、6月の憲法にも、議会制、他者の労働成果の搾取の禁止、集団的所有権の優位などの、独立宣言と国家の自立性に関するアクトが宣言した諸原則はすでに含まれていなかったのである。
<議会制から純粋大統領制、そして準大統領制へ>
言うまでもないが、総じて人民共和国初期の憲法の様々な「歪み」は、ウクライナからの軍事的攻撃、共和国内の革命的過程から生じる内政上のごたごたなど、共和国創出に伴う困難な諸条件に起因していた。
その期間、権力機関の名称や機能が変わり、政治過程の多元主義が減退する傾向が見られた(戦時には、ある程度はやむを得ないことである)。
議会の名称は「最高会議」から「人民会議」に変わり、最高機関としての機能は失った。国家の事実上の長は、閣僚会議議長であったり、共和国首長であったり、(それに劣らず)政府首相であったりした。
執行権の最高機関は、最初は閣僚会議という名称であったが、現在は政府という名称である。以前は、閣僚会議を指揮するのは共和国首長であったが、現在では(首長とは別の)首相が指揮している。
これらの変容はすべて、当該期に求められた人々や諸機関の役割を引き上げた様々なロビー集団間の闘争を、性格づけたのである。
現在(2024年前半)では、公式には共和国の長は「ドネツク人民共和国議長」(地元出身者のデニス・プシリン)であるが、多くの問題、特に財政問題に対して責任を負うのは政府と、政府の首班である首相(ロシア中央政府から派遣されたエヴゲーニー・ソルンツェフ)というシステムが確立された[25]。
<民主主義の後退>
2014年から2022年に至る憲法上の変容は、一方では、ロシアの諸規範に接近し、他方では、統治の手続き民主性が後景に退いてゆく過程であった。
たとえば、2022年12月30日に採択された(噂によれば「上から授けられた」)ドネツク人民共和国憲法は、共和国首長の共和国議会による間接選挙を規定した。
これは、ロシア連邦のごく少数リージョン(あわせて約15リージョン)でしか機能していない規範である。
それらは、北コーカサスの民族共和国、州の下位機関である民族管区、2014年にロシア連邦に参加したクリミア共和国とセヴァストポリ市である。[ロシアのその他のリージョンでは、知事は住民により公選されている。]
もっとも、ドネツク人民共和国創成期の法規範に見られた手続き民主主義は、当時の混乱と無政府状態の下では概して実現されず、紙上の願望にとどまっていた。
総じて、ルガンスクとドネツクの人民共和国の上級国家統治のシステムは、相当程度、「手作業統治」と特徴づけられる。
つまり、制度や規範によってではなく、より影響力のある指導者の個人意志による決定(通常、中央政界における決定)により、国家運営がなされるのである。
相当程度、これはロシア連邦全体の問題だと言えるが、かつての非承認共和国においては、これは極端な程度で露呈したのである。
特にウラジスラフ・スルコフが、ドンバス問題を監督していた時期はひどかった。
しかしながら、そのようなシステムの非効率のせいで、最高権力は、当該システムを除去しようと考えるに至ったのかもしれない。現時点では、ロシアの法規範は現地情勢を、より強く規定するようになっている。
(後半に続く)
―――――――
【原注・訳注】
[1]Erika Harris. What is the Role of Nationalism and Ethnicity in the Russia–Ukraine Crisis? Europe-Asia Studies. 29 Jan. 2020. 21 p.;
Vlad Mykhnenko. Causes and Consequences of the War in Eastern Ukraine: An Economic Geography Perspective, Europe-Asia Studies. 03 Feb. 2020. 33 p.; Alla Hurska. Russia’s Hybrid Strategy in the Sea of Azov: Divide and Antagonize. The War in Ukraine’s Donbas. 2021. p.153-173.
[2]Sergey Sukhankin. Russian Private Military Contractors in the Donbas: Rehearsing Future Voyages. The War in Ukraine’s Donbas. 2021. p.175-198.; СабураО.І. «ДНР» та «ЛНР» у науковому дискурсі: пошук термінології // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія, 2017, Вип. 20. С.309-315.
[3]Paul D’Anieri Ukrain and Russia. From Civilized Divorce to Uncivil War. 2019. 282p.; Kudelia Serhiy. Civil War Settlements and Conflict Resolution in Donbas. The war in Ukraine’s Donbas. 2021. p.199-219.; Serhiy Kudelia and Johanna van Zyl. In My Name: The Impact of Regional Identity on Civilian Attitudes in the Armed Conflict in Donbas. Nationalities Papers (2019), 47: 5, 801–821; Elise Giuliano. Who supported separatism in Donbas? Ethnicity and popular opinion at the start of the Ukraine crisis. Post-soviet AffAirs, 2018. 21 p.; Henry E. Hale, Oxana Shevel, and Olga Onuch. Believing Facts in the Fog of War: Identity, Media and Hot Cognition in Ukraine’s 2014 Odesa Tragedy. Geopolitics. 2018, 23: 4, 851-881; Ivan Katchanovski: The OUN, the UPA, and the Nazi Genocide in Ukraine // Mittäterschaft in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust. 67-93 p.; Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives. Edited by Agnieszka Pikulicka-Wilczewska & Richard Sakwa. 2015. 278p.; Tetyana Malyarenko and Stefan Wolff. The Dynamics of Emerging De-Facto State. Eastern Ukraine in the Post-Soviet Space. 2019. 104 p.
[4]КислицынС.А. Предпосылки интеграции де-факто суверенных народных республик Донбасса в постсоветские объединения с участием Российской Федерации // Власть. 2019. No.4. С.138-141.; ОнопкоО.В. Внешняя политика Донецкой Народной Республики: интересы и идеология // Научные ведомости. Серия: История. Политология. 2018. No.2.; Узнаров И.М, Узнародов Д.И. Перспективы развития народных республик Донбасса в качестве самостоятельных субъектов международной политики // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2018.; СтупаковН.В. Применение современных доктрин признания международной правосубъектности государств в согласительных (мирных) процедурах урегулирования конфликта Украины с ДНР и ЛНР // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2015. No.3.; Внукова Л.Б., ВласкинаТ.Ю. Самоидентификация жителей Донбасса в контексте социально-политических воззрений: социально-лингвистический аспект // Вестник Томского государственного университета (филология, философия, история, педагогика и право), Февраль 2021. No. 463. С. 73 – 86.; ЧеркашинК.В. «Русская весна» в Донбассе: предпосылки, ход и последствия // Постсоветский материк. 2021. No.4(32). С.4-15.; ЧеркашинК.В. Политические предпочтения жителей республик Донбасса (в контексте выборов в Государственную Думу Российской Федерации 2021 года) // Вестник Московского университета. Серия12. Политические науки. 2023. No.1. С.50-65.
[5]MatsuzatoK. The Donbass War: Outbreak and Deadlock. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization 25: 2 (Spring 2017): 175-200. MatsuzatoK. The First Four Years of the Donetsk People’s Republic: The Differentiating Elites and Surkov’s Political Technologists. The War in Ukraine’s Donbas. P.37-60.
[6]<訳注>2014年2月の政変当初は、政変推進勢力は、それを「尊厳の革命」などと呼び、政変の革命性を隠さなかった。しかし「革命」という言葉を使うと暴力的事件であったことを西側に向けてアピールしてしまうためか、「革命」という言葉は推進派の言説からはやがて消え、たんに「ユーロ・マイダン」と呼ぶようになった。政変を批判する南東野党(旧地域党)、分離派、ロシア指導部などは、2014年2月の政変を「クーデタ」、「血みどろのクーデタ」などと呼ぶが、これは、旧ソ連圏においては、「革命」という言葉がいまだに肯定的なニュアンスを伴っているからである。 つまり2014年2月の政変の支持者も反対者も「革命」という言葉は忌避しているのである。ちなみに訳者は、この政変の最も顕著な特徴は、その主張の内容や目的ではなく、その形態(暴力性)だったと考えるので、それを「ユーロ・マイダン革命」と呼んでいる。
[7] Державна служба статистики України // https://ukrstat.gov.ua; Валовый продукт регионов Украины // https://aftershock.news/?q=node/823620&full (В официальной украинской статистике этот факт скрывался: якобы наибольшую, около 20%, долю ВВП страны производил один город Киев. Однако такая картина складывалась из-за того, что центральные офисы кампаний, осуществлявшие отчётность и отчислявшие средства, находились в столице, а производственные мощности – в основном на Юго-Востоке).
[8]<訳注>ノヴォロシア(新しいロシア)とは、18世紀後半、エカテリナ2世がウクライナ南部をクリミア・ハン国とオスマン帝国から奪った際に同地に与えた名称である。2014年以降、ウクライナ南東部の分離勢力は、この歴史的地名を好んで用いた。
[9] Колонна бронетехники на Донбассе едет на людей 16 марта 2014 // https://www.youtube.com/watch?v=-ClroOoIda4
[10] Обращение А.Турчинова. 7 апреля 2014 ― Начало вооружённого конфликта // Хроника украинского кризиса. – URL: http://ukrainian-crisis.info/protesty-na-jugo-vostoke/protesty-reakcija-v-mire/protesty-reakcija-ukrainskih-vlastej/7-aprelja-2014-nachalo-vooruzhennogo-konflikta/
[11]<訳注>ここで著者は、「ロシアの武装勢力(ストレリコフ=ギルキン)が国境を越えて侵入したので、ウクライナは反テロ作戦を開始せざるを得なかった」という、一部マスコミや研究者にみられる見解を批判している。
[12] Путин: Россия признает выборы президента Украины // Деловой Петербург. 23 мая 2014. https://www.dp.ru/a/2014/05/23/Putin_Rossija_priznaet_vi?ysclid=ls5378035j888286436
[13] Путин одобрил выбор украинского народа: встреча в Нормандии. 7 июня 2014. RTVI https://ya.ru/video/preview/8567958373498054738
[14]<訳注>ここで著者が幹部ではなく予備役(幹部候補)という言葉を使っているのは、ロシア側が人民共和国の幹部を人選する段階で、理想に燃える活動家は除外され、何らかの弱みを抱えたような活動家を好んだという事情を指していると考えられる。
[15]<訳注>軍、警察、特務などの強制力機構の指導者を指す。
[16] Евгений Пригожин – ЧВК ВАГНЕР 23 ИЮНЯ 2023 года интервью // https://www.youtube.com/watch?v=O9X91rVo1cE
[17]Потери среди гражданских лиц в Украине, связанные с конфликтом. УВКПЧ (27 января 2022). Дата обращения: 20 июня 2022. Архивировано 5 июня 2022 года. // https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-02/Conflict-related%20civilian%20casualties%20as%20of%2031%20December%202021%20%28rev%2027%20January%202022%29%20corr%20RU.pdf
[18]Тайсаев: В Донбассе погибли более 50 тысяч человек // Парламентская газета. 15.02.2022. https://www.pnp.ru/politics/taysaev-na-donbasse-pogibli-bolee-50-tysyach-chelovek.html; РодионовД. Горький счет войны: 13 тысяч или 50 тысяч были убиты в Донбассе? // Свободная пресса. 23 января 2019 // https://svpressa.ru/war21/article/222531/
[19]В Украине почти до 1,5 миллиона человек возросло количество переселенцев. 22 февраля 2021 // https://ru.wikinews.org/wiki/В_Украине_почти_до_1,5_миллиона_человек_возросло_количество_переселенцев; Поток беженцев с Украины в Россию уже превысил число вынужденных переселенцев в 2014 году. 25 июня 2022 // ТАСС. https://tass.ru/obschestvo/15306065?ysclid=ls561yhmct32734232
[20]Численность населения Донецкой Народной Республики на 1 января 2022 года https://web.archive.org/web/20220401055146/http://gosstat-dnr.ru/pdf/naselenie/chisl_naselenie_0122.pdf; Численность населения Луганской Народной Республики на 1 апреля 2021 года http://bit.ly/41XSt9X
[21]Бюллетень Государственного комитета статистики Украины в Донецкой области (март 2012). – Донецк: Госстат., 2012. – С.10.
[22]Азат Абдуллатыпов. О забастовке на шахте “Комсомольская” // Colonelcassad. 12 июня 2020. https://colonelcassad.livejournal.com/5941006.html?ysclid=ls5707ofxz905920982
[23]Полный текст документов, принятых Донецкой Народной Республикой : 1. Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики. 2. Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. 3. Обращение Донецкой Народной Республики к президенту Российской Федерации В.В.Путину. 7 апреля 2014 // https://www.fgu-ocsm.ru/akt-o-provozglashenii-gosudarstvennoy-samostoyatelnosti-donetskoy-narodnoy-respubliki/
[24]<訳注>いわゆる搾取が禁止され、集団的所有権を優先するというのだから、これは社会主義憲法である。リトヴィノフをはじめ社会主義を目指す人々が「ウクライナと同様のオリガーク国家」であるロシア連邦に保護を求めざるを得なかったところに、ドネツク人民共和国の悲劇があったのである。
[25]<訳注>ドネツク人民共和国は、2014年4月の誕生から11月の共和国首長公選までの約半年間は議会制であり、国家元首は議会議長だったが、すでに閣僚会議議長(首相)が事実上の最高指導者であった。共和国首長職が導入されると、共和国首長(2018年までザハルチェンコ、その後はプシリン)が国家元首であると同時に執行権力の長を兼ね、首相職は廃止された。 このように首相がおかれず、公選の首長(大統領に該当)が閣僚会議を主催するアメリカ型の体制を純粋大統領制(full presidentialism)と呼ぶ。2022年秋にロシアに併合された際にドネツク人民共和国憲法が改正され、首相職が導入された。ロシアがその首相候補を派遣し、議会の承認を得たうえで、行政実務を担わせるようになる。他方で地元出身の共和国首長は、象徴的・元首的機能を果たし続ける。このように執行権が首長(大統領)と首相に分けられた体制を準大統領制(semi-presidentialism)という。