「新聞の押し紙とは、押し売りのようなもの。たとえば、新聞販売店に2000人の新聞契約者がいたら、予備と称して1000部多い3000部が納品され、新聞社は3000部の料金を販売店に請求する。その余分に届いた新聞を、押し紙と呼ぶ」──。
2012年5月30日(水)、東京都港区にある初沢スタジオで、岩上安身がフリーライターの黒薮哲哉氏にインタビューを行なった。黒薮氏は、新聞の押し紙問題について独自の取材を続けており、新聞販売店の実態、新聞社と一体化する広告代理店、新聞社相手の訴訟などについて語った。
「押し紙は明治時代からあった。しかし、戦後の専売制度で、新聞社と販売店の関係が強化された」と語る黒薮氏は、近年の不景気で販売店が負担を抱えられなくなった、と指摘。さらに、「新聞社が公称部数の上乗せのため、補助金を出している」と新聞業界のグレーな部分に言及した。
岩上安身は「新聞を社会の木鐸(ぼくたく)と呼ぶには、ほど遠い実態だ」と驚き、利益追求に走りすぎている新聞社の姿勢に疑問を呈した。
販売店が「自主的に」必要以上の新聞を買い取る?
岩上安身は「新聞の押し紙問題を本格的に追っているジャーナリストは、黒薮哲哉氏しかいない」と述べ、黒薮氏の著書『新聞があぶない』(2006年刊行・花伝社)を示しながら、「販売店の押し紙問題は、新聞の内容にまで関わってくる」と前置きしてインタビューを始めた。
はじめに黒薮氏は、ある裁判について語った。2001年、福岡県久留米市近郊の読売新聞販売店の店主である真村氏は、読売新聞社から配達委託地域の一部返還を求められた。理由は、他の販売店に割り当てるためだという。納得できない真村氏が要請を断ると、閉店を強要された。真村氏は裁判に訴えて、福岡地裁、高裁、最高裁とすべて勝訴(2007年12月)する。しかし、読売新聞は真村氏に新聞を卸さず、廃業させてしまったという。
黒薮氏は、その「真村裁判」の争点にもなった押し紙について説明した。「押し紙は、押し売りに似ている。たとえば、新聞販売店に2000人の新聞契約者がいたら、予備と称して1000部多い3000部が納品され、新聞社は3000部の料金を販売店に請求する」。
新聞社側の言い分は「新聞の納入部数が、その販売店で扱う折り込みチラシの枚数となる。チラシ収入は販売店に入るから、店は自主的に新聞を多く買い取っているのだ」というもので、決して、押し紙を認めないという。
岩上安身が「新聞の折り込みチラシは、広告代理店と販売店の収入になるが、広告代理店は新聞社系列が多い。水増しをさせているのは広告代理店なのか?」と聞くと、黒薮氏は「広告代理店は、新聞社からの指示で、公称発行部数を基準にしている」と応じた。
岩上安身は「つまり、新聞社は水増し分(押し紙)を販売店に売り付けているだけでなく、広告主からも、水増しした部数での広告料金をもらっている。広告主からすれば詐欺のような話で、本来なら警察が捜査するようなこと。それが、新聞業界の慣行とされているのか」と驚きの表情を浮かべた。
大新聞と広告主の奇妙な関係
黒薮氏は「押し紙は、明治時代からあった。しかし、戦後の専売制度で、いわゆる拡販競争が始まり、新聞社と販売店の関係が強化された」と語り、近年の不景気で販売店が負担を抱えられなくなってきたと指摘。その上で、「1977年、日本新聞販売協会が残紙(押し紙)の調査を行うと、押し紙率は全国平均で8.3%だった」と述べた。
岩上安身は「新聞は予約購読が基本で、本来、在庫が大量に出るはずはない。押し紙は、印刷工程も含めて資源の無駄遣いだ。しかも、販売店に負担を強いて、広告主から高い広告料金を詐取する。広告主には大手企業も多いが、なぜ、こんなことを見過ごしてきたのだろうか」と疑問を投げかけた。
黒薮氏が「企業は、読売新聞1000万部、朝日新聞800万部の影響力を考慮して、自社にとって不都合なことを紙面で書かれたりしないように、新聞社と敵対することを避けているのではないか」と答えると、岩上安身は「メディアとしての力を背景に、広告料の多寡によって報道のさじ加減を変えるようなことがあるならば、ゆすりたかりと変わらない」と断じた。
折り込みチラシに関して、黒薮氏は別の具体例を挙げた。「ある地方紙は1702部(2005年6月)配布しているが、折り込みチラシの数は、ミスタードーナツ2200枚、イトーヨーカードー2400枚、パチンコ業者も2400枚を入れている。特に、パチンコ業者のチラシは多い傾向があり、トラブルの多い業界だけに(新聞社への)口止め料だという見方もある」。
岩上安身は「つまり、広告営業をする広告代理店も、水増しに加担して儲けている。広告主も、新聞社に口止め料にあたる裏金も含めた広告料金を払っている場合があるという、複雑な仕組みになっている」と眉をひそめた。
押し紙保管のために「小屋を建てろ」
黒薮氏は、業界紙の編集記者を3年経験している。「この時、たくさんの新聞販売店を取材して、押し紙問題は知っていた。店のスタッフは『紙を積んでいる』という言い方をする」。
2002年、押し紙代金が払いきれなくなった販売店が、産経新聞を提訴した裁判では、押し紙の廃棄方法についても明らかになっている。「1日あたり2000部が過剰在庫で、この販売店は新聞社から『小屋を建てて保管しろ』と言われたという。廃棄される押し紙は、古紙回収業者が目立たないように夜明け前に回収に来る。また、コンテナ車で隠して回収する専門の業者までいる」と黒薮氏は語る。
岩上安身が「圧倒的な力関係によって、販売店は抵抗ができない」と言うと、黒薮氏は「新聞社は訴えられることも想定して、毎月、販売店に書面で配布部数、新聞社からの搬入部数を書かせている。訴訟の防衛策を講じているのだ。押し紙は独禁法違反だから、記入する部数に押し紙は算入しないのが慣例だ」と説明した。
増紙を求め、減紙を嫌う新聞社
黒薮氏は、前述の真村裁判について、さらに詳しく説明した。「発端は、地区の有力者の弟の販売店のために、読売新聞社が真村氏の販売区域の譲渡を強要したこと。新聞販売業界には地元のボスがいる。真村氏も、たびたび利権争いで暴力を受けていた。福岡高裁は、新聞販売店に増紙を求め、減紙を嫌う読売新聞社の体質を批判し、真村氏は勝訴した。しかし、半年後、読売新聞社は真村氏への新聞供給を一方的にストップして、店をつぶした」。
「結果的に、販売店は圧力や嫌がらせを怖がり、押し紙を実数に組み込んでしまう。新聞社はそれを逆手にとって、信頼関係をネタに生殺与奪の権利を握る」と黒薮氏は口調を強め、岩上安身も「もし、これが事実だとすると、かなり悪質だ。新聞が社会の木鐸(ぼくたく)という資格はない」と憤った。
毎日新聞は実売251万部、押し紙144万部
「押し紙の割合は、新聞社によって違う」という黒薮氏は、入手した毎日新聞の内部資料を次のように紹介した。「毎日新聞社長室の資料による、2002年10月の発証数(領収証発行数=販売実数)の調査では、実売は251万部、販売店に搬入した部数は395万部。つまり、押し紙は144万部であった。この144万部が生み出す利益を試算すると、月に21億6000万円。年間259億2000万円に上る」。
ただし、これだけの金額を販売店側が負担するのは実際には無理があるため、「新聞社は、販売店に押し紙を買い取るための補助金を出している。それで公称部数を上げる。目的は広告収入のためだ」と黒薮氏は言葉を重ねた。
他の新聞社の状況については、「読売新聞はあくまでも『残紙』と主張しているが、2007年10月頃の大牟田明治販売所への搬入部数は2400部で、うち920部が押し紙。約4割だ。大牟田中央は2520部搬入し、押し紙は900部。久留米文化センター前店では2100部搬入、997部が押し紙だ」と黒薮氏は説明し、さらに、朝日新聞や産経新聞の押し紙裁判の実例を挙げていった。
岩上安身が「今、新聞社の経営状態がとても厳しい。ある新聞社の幹部によれば、収入の7割が広告料だという。つまり、新聞の制作費を売り上げでは捻出できないということで、広告に頼らざるを得ない」と話すと、黒薮氏は「渡邉恒雄読売新聞社主いわく『10年前は約1600億円の広告収入が、800億円に半減した』という。広告収入の激減で、新聞社は押し紙による部数の水増しを広告主に知られては困る。だから、私は読売新聞社から3件の訴訟を起こされている」と語った。
新聞社vsフリーライターの闘い
真村裁判の勝訴により、近隣の販売店も押し紙排除に姿勢を変えていったため、読売新聞はそれを危ぶんだのか、黒薮氏に攻撃の矛先が向けられたという。
まず、黒薮氏のホームページ『新聞販売黒書』に載せた記事の著作権を巡って裁判を起こされたが、2009年3月に黒薮氏側が完全勝訴。その後、この訴訟が虚偽告訴罪にもあたることが判明し、2010年、黒薮氏側は読売新聞側の弁護士に対して懲戒請求を行っている。
2つ目の裁判は、最初の提訴の2週間後に、同じく読売新聞が『新聞販売黒書』の記事を名誉毀損だとして、2230万円の損害賠償を求めて提訴したもの。記事は「2008年3月1日、久留米文化センター前店に読売新聞の幹部3名が来訪、改廃(専売契約の解除)を通告。翌日、折り込みチラシを持ち出したのは窃盗罪にあたる」という内容で、これは地裁、高裁ともに黒薮氏が勝利したが、最高裁では逆転敗訴となった。
その後、久留米文化センター前店の店主は病気を患い、2011年、56歳で亡くなったという。さらに読売新聞は、店主が帳簿類を渡さなかったことで調査費用がかかったとし、店主側(遺族)に500万円を請求して勝ち取っている。
「この店主も押し紙を断った人だ。このように、販売店だろうが、フリーライターであろうが、押し紙を告発する者は手段を選ばずにつぶせ、という方針なのだろう」と黒薮氏は語る。
司法もおかしくなっている
3つ目は、2009年6月、読売新聞が週刊新潮と黒薮氏を提訴した裁判だ。滋賀県の大津市や草津市など5ヵ所で、新聞の購読調査を滋賀クロスメディアが行なった。そこで押し紙を推定できるデータが出てきたので、黒薮氏が週刊新潮で「読売新聞の押し紙率は3~4割」と推測した記事を書いたためだという。
そこで、黒薮氏も3つの裁判をまとめて一連の言論弾圧と捉え、損害賠償裁判を福岡地裁に起こした。「著作権裁判は東京地裁、名誉毀損は埼玉地裁。福岡在住の支援弁護士の交通費など、たいへんな労力を強いられたので、その負担を賠償させる趣旨だ」と話す。
この裁判が異常な展開を見せたと黒薮氏は言う。「当初、裁判所は原告(黒薮氏)の証人調べをせず、原告の陳述書も受け付けない方針を示した。弁護団が抗議して、やっと受け付けたが、つまり、最初から結論ありきなのだ」。
そして、「おかしなことに東日本大震災を境に、押し紙問題に取り組む私や新聞販売店主らの裁判は負けるようになった。全体的に言論に対する締め付けが強くなり、司法がおかしくなっていると感じる」と続けた。
さらに、読売新聞社の弁護団のひとつであるTMI総合法律事務所には、元最高裁判事が3人再就職していることを指摘して、「こういうことをすると、読売新聞と裁判所との人脈ができてしまう」と述べ、司法の公平性にも疑問を呈した。
利益のために動くようになった日本人
岩上安身は、読売巨人軍の清武英利元球団代表の裁判について尋ねた。黒薮氏はあくまでも推測だと断りつつ、「読売新聞は、巨人軍を販促ツールとして重要視していた。しかし、東京ドームの試合入場者数は減少し、もはや野球を盛り立てるための新聞拡販は遅れたシステムになった」と語り、このように続けた。
「そこから焦りが出てきて、内輪モメになったのではないか。清武氏は元読売新聞社会部デスクで、そのグループで執筆した『会長はなぜ自殺したか 金融腐敗=呪縛の検証』(新潮社)の復刊も差し止め請求されて、読売新聞が勝訴した。さらに、清武氏は1億円の損害賠償でも訴えられた」。
黒薮氏は「本来、読売新聞は言論機関だ。言論で対抗しなくてはならないのに、裁判に頼る。自分たちで判断すべきところを、司法に任せる。これがメディア企業の正しい姿勢か。また、読売の弁護団には、薬害エイズ裁判やロス疑惑事件で活躍した喜田村洋一弁護士がいる。自由人権協会代表理事なのに、先頭に立っている」と弁護士の姿勢にも疑問を呈し、「日本人全体が、利益だけのために動くようになってきている」と述べた。
押し紙問題は新聞社のアキレス腱

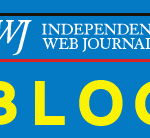
























新聞販売店には上京したばかりの若いころ働いていたこともあり、「押し紙」のことは熟知しています。この「押し紙」というの は折り込み広告の量によっても販売店の収益が左右されるので、販売店としたら受け取らざるを得ない場合もあるのです。反面、そのしわ寄せは購読料金の「切り取り」という、いわゆる集金不能な読者の代金を店員が払わなければならないということが、あたりまえのようにありました。これと並行して、新聞社同志の読者獲得競争が日常茶飯事に行われていたのですが、これに関して新聞社の販売担当は月に二、三度は自分が担当する販売店を訪れ店主に販売(宅配)部数を増やすようにハッパをかけるのです。このしわ寄せも結局は店員にとって無理、無謀な拡販(拡張)しなければならないという事態に追い込まれるわけですが、これが特に酷かったのが新聞奨学生まで使っての読売新聞の拡販のやり方だったと記憶にあります。売れない新聞を強引に読者に勧めるわけですからそのためには拡販材料という、ある意味、言い方は悪いかも知れませんがエサを持って行って契約を結ぶわけです。この拡販材料(拡材)というのは当時はあらゆる生活用品があり、洗剤、ビール券、お米券、図書券、野球券、劇場券、遊園地券などはあたりまえで、鍋釜をはじめ、絵皿時計、安物の腕時計、電卓、はてはミニサイクル自転車まで現れたのを覚えています。とにかく自分の受け持ち区域の部数を増やせが当時のやり方だったのです。このような状況でしたので、学校に通うことも出来なくなる奨学生がたくさんいました。とにかく、万年寝不足も続くわけですから身体をこわす人もたくさんいました・・。もっと書くことがありますが、このへんで・・・
*上のコメント記事の編集
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
新聞販売店には上京したばかりの若いころ働いていたこともあり、「押し紙」のことは良く知っています。この「押し紙」というのは販売店にとって重要不可欠な収入源である折り込み広告の数量が左右されるので、販売店としたら「押し紙」を受け取らざるを得ないのです。宅配販売部数の少ない販売店になればなるほど、折り込み広告が少なくなるわけで、とうぜん収入が減るわけです。この折り込み広告の収入源が店員の給料に反映されてもいるわけです。そして、販売店同志の読者獲得競争が当時は激しく日常茶飯事に行われていたのですが、これに関して、どこの新聞社の販売担当でも月に二、三度は自分が担当する販売店を訪れ店主に販売(宅配)部数を増やすようにハッパをかけるのです。規模の小さな販売店などは店を構える最初に社に借金をして営業を始めるわけでもありますから、販売担当は神さまのような存在で、店主は訪問した担当に向かって正座して頭を下げるのです。宅配部数が減った月にでもなれば、これはもう大変で、鬼のような形相の担当に店主が土下座していたのを見ています。そして、店に居合わせた店員にも睨みつけ、挨拶一つしません・・このしわ寄せも結局は店員にとって無理、無謀な拡販(拡張)しなければならないという事態に追い込まれるわけですが、これが特に酷かったのが新聞奨学生まで使っての読売新聞の拡販(拡張)のやり方だったと記憶にあります。売れるか売れないかわからない、あるいは読んでもらえるかわからない新聞を未読者の家庭や他の新聞読者の家庭を訪問して、勧めるわけですから、そのためには拡販材料というものを当時は店員にも使わせ、読者を誘導するのですが、もともと学業が本来の目的である奨学生にとって無理難題なこの営業は当人にとっても辛い仕事なのですが、これをしなければ自分の区域の部数が減り、結局は奨学生の場合6万円程度ある月々の収入にも関係してくるので読者獲得あるいは部数維持は絶対的な仕事のひとつだったのです。
そして、この拡販材料(拡材)というのは当時はあらゆる生活用品があり、洗剤、ビール券、お米券、図書券、野球券、劇場券、遊園地券などはあたりまえで、拡販員(拡張員)などは、鍋釜をはじめ、絵皿時計、安物の腕時計、電卓、はてはミニサイクル自転車まで使われていたのを覚えています。この拡張員は新聞社が直接的に関与する営業グループに所属している人と、単独で販売店と約束を交わし、日々、販売店の区域を回り、店員が獲得できない読者の家庭を訪問する人に分けられていました。特に強引な手段、手法で営業するのは前者の方です。例えば契約を結ぶ時、購読料を半年サービスするとか、言って契約書に捺印やサインをしてもらうわけですが、販売店がこれを知らずにいると、そのトバッチリは店員にくるのです・・いわゆる、購読料の集金に行ったら、もらえないのです。ですから店員は必死です。
このような営業の手法は序の口で獲得競争がもっとも激しかったころには刃物沙汰もあったと聞いています・・。
最後になりますが、これが公器と呼ぶに相応しいモノでしょうか・・新聞の使命とは何でしょうか・・私は東京新聞の愛読者です・・