第1 はじめに
元徴用工が新日鉄住金、三菱重工業に対して損害賠償(慰謝料)を求めた訴訟の韓国最高裁(大法院)判決が下され、大きな波紋を呼んでいる。「国際法上あり得ない判決」、「暴挙」など、いたずらに対立感情を煽る日本政府の言うことを真に受ける方は、IWJの視聴者の中には多くはないだろう。しかし、これほど社会の雰囲気が韓国政府非難一色になると、その影響を受けないでいることはかなり難しいだろうとも思う。

▲岩月浩二弁護士(2018年11月2日、IWJ撮影)
日韓請求権協定(以下、「請求権協定」とする)の解釈という、優れて高度な法律問題について、一国の法律専門家の超エリート集団が、そうそう容易に論破されるような軽率な判決を下すはずがない。頭から間違っているとする、韓国最高裁判決に対する非難には、韓国を下に置く、近代日本に深く刻まれた朝鮮差別意識が透けて見える。

▲韓国大法院(最高裁)(Wikipediaより)
詳細に検討すれば、ある意味で、日韓の裁判所の立場には、実践的な意味での開きは小さい。求められているのは日韓両国、両国国民が、厳然たる強制労働の被害に対して、どう向き合うかという人権に対する真摯な姿勢である。知恵を寄せた解決の模索が強く求められている。それは、まさに現在問題になっている外国人技能実習生に対する深刻な人権侵害、そして入管法改正による事実上の単純労働に従事する外国労働者の移入拡大に舵を切った安倍政権にどう向き合うか、という点にも通じる。
まず、原告らが訴えている被害がどのようなものであったかを、私自身が弁護団事務局長を務めた名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟(2018年11月29日韓国最高裁は三菱重工の上告を斥け、原告の勝訴判決を確定させた)を通じて、紹介したい。全ては、被害事実を直視するところから始めるべきだからだ(「被害に始まり、被害に終わる」が公害訴訟を闘った我々弁護士の先達の教訓である)。
第2 日本訴訟
1 提訴
それは、特別な光景だった。
多くのテレビカメラが回る中、当時70歳近い原告らとともに裁判所の建物に向かう提訴行動のとき、60歳の弁護団長(内河惠一)は、突然、原告らの手を取り「お手々つないで」を歌い始めた。弁護団が当惑する中、原告らがそれに応えて唱和した。原告らにとって、その歌は身になじんだ歌だったからだ。
1999年3月1日に名古屋地方裁判所に提訴された、名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟は、そうした不思議な明るさの中で始まったのだった。
2 被害事実
(1)皇民化教育
原告らは、徴用工とも慰安婦とも認知されることのない、韓国社会では狭間に落ちた、女性の強制労働被害者だった。
彼女たちは、朝鮮半島で皇民化教育が本格化した1937年前後に小学校(国民学校)に入学し、日本語での教育、宮城(皇居)遙拝、皇国臣民の誓詞の暗唱を求められ、天皇に対する尊崇の念を徹底して埋め込まれる教育を施された。

▲1940年1月1日の朝鮮日報(Wikipediaより)
原告らは、70代になっても、日本語での日常会話に差し障りがなかった。皇国臣民の誓詞すら、ほぼ全員が暗唱していた。
「・私共は、大日本帝国の臣民であります。
・私共は、心を合わせて天皇陛下に忠義を尽します。
・私共は、忍苦鍛錬して立派な強い国民となります。」
小学校入学と同時に皇民化教育を受けた彼女たちは、「皇民化教育の完成品」とも呼ばれ、宗主国日本に対する素朴な憧憬と畏敬の念を抱いていた。
(2)朝鮮少女の労務動員とその波紋
戦時中、日本は成年男性を徴兵した結果、著しい労働力不足を生じた。不足した労働力を補うため、中国、朝鮮、台湾等から多くの労働者を動員した。大戦末期にはまだ幼い少女までを朝鮮から動員して、朝鮮女子勤労挺身隊として富山(不二越・約1100名)、名古屋(三菱重工・約300名)、沼津(東京麻糸・約300名)の軍需工場で働かせた。日本に連れ去られた若い女性の多くが慰安婦とされた中、相対的に少数の女子が労務動員された。
挺身隊の動員は当時の朝鮮では「処女供出」と呼ばれ、恐れられた。未婚の女子を動員されることを恐れた朝鮮では保護者が娘を急ぎ結婚させた。現実に当時のソウル(京城)では婚姻年齢の顕著な早婚化が進んだ(京城府東大門警察署管内では19歳から21歳だった初婚年齢が1944年1月から5月頃にかけて15、16歳に低下した)。
(3)欺罔(ぎもう=人を欺くこと)と脅迫による勧誘
彼女たちは、小学校の担任、校長らから「日本に行けば、女学校へ行ける」「働いてお金ももらえる」と騙されて日本に連れてこられた。当時の朝鮮では朝鮮人が女学校へ進学する道はほぼ閉ざされていた。皇民化教育によって天皇を崇拝し、日本に対する素朴な憧れを抱いていた少女たちにとって、日本で女学校に行けるという誘いは夢のような話だった。教師に対する絶対的な信頼を植え付けられた少女を騙すのは容易なことだった。いったん承諾した少女の親が日本に行くのを反対しても、「憲兵が親を逮捕する」等と脅迫して、彼女らは日本行きを強制された。
要するに年端もいかない少女たちは、皇民化教育により親以上の信頼を寄せた教師らに容易に騙され、親が反対すれば、脅迫を加えられて、日本に連れてこられた。日本訴訟の名古屋高等裁判所判決(2007年5月31日)は、これを強制連行であったと認定している。
(4)強制労働
こうして連れてこられた少女たちは、三菱重工名古屋航空機製作所道徳工場に配置された。軍用機を製造する工場で、幼い少女には過酷な労働を強いられることになった。女学校に行けるどころか、賃金も払われることはなかった。1944年12月6日、東海地方を襲った東南海地震では工場が全壊し、朝鮮女子勤労挺身隊員6名が死亡した。

▲1930年に採択されたILO第29号条約(強制労働撤廃条約)。赤は未批准国。日本は1932年に批准(Wikipediaより)
前記した名古屋高等裁判所は、労働実態・労働環境を踏まえ、ILO29号条約に違反する強制労働であったと認定している。
(5)解放後の人生被害
日本の敗戦によって、故国に帰った彼女たちを待っていたのは、思いもよらぬ偏見と差別だった。当時、「挺身隊」とは「慰安婦」の別名と考えられていた(※)。日本に連れ去られた若年女性の圧倒的部分は「慰安婦」とされ、相対的に少数の少女が労務動員された。「挺身」とは身を捧げることを意味する。連れ去られた朝鮮から見れば、日本に連れて行かれた若年女性は全て「慰安婦」であると誤解されたのである。ある時期までの日本も韓国も女性に対して、純潔であることを極端なまでに要求した。
※韓国では「挺身隊」がほぼ「慰安婦」の意味で使われており、日本での報道でもそうした用法が一般的であった。植村隆『真実――私は「捏造記者」ではない』(岩波書店、2016年)134-135、222―223頁を参照されたい。なお、特定の用語の混同を集中的に批難し、あたかも被害の事実まで否定しようとする歴史修正主義者の「包括否定」の主張は看過できない。こうした行為は、「正確さ」を持ち出しながら、かえって歴史の真実から目を背けるものであろう。この点は高橋哲哉『戦後責任論』(講談社、2005年)137-146ページで指摘されている。

▲挺身隊の京城隊・仁川隊が参拝した朝鮮神宮(京畿道京城府南山)(Wikipediaより)
純潔を失った女性は「汚れた女性」と分類され、「遊ぶ相手」と見做されて、社会や家庭から排除され、婚姻生活に入ることは許されなかった。帰国後まもなくこれを知った原告らは、「挺身隊」に動員された過去に固く封印し、過去を知られることに怯える人生を送ることを余儀なくされた。固く封印しても秘密は漏れる。挺身隊の過去を知られた原告らは、離婚を強いられ、あるいは夫から虐待を受け、夫が家を出た。甚だしくは夫が、外で「汚れていない女性」ともうけた子どもを実子として育てることを強いられた原告もいた。提訴後に、初めて夫に「挺身隊」の過去を打ち明けた結果、離婚された原告もいた(こうした人生被害は「慰安婦」とされた女性も共通して被った人生被害である)。
彼女たちの日本訴訟にかけた思いがひときわ深かったのも、被害者とみなされず、「汚れた女性」として社会や家庭から排除されるという、こうした人生被害のまさに、ただ中にいたからでもあっただろう。
(6)重大な不法行為
上記名古屋高裁判決は、こうした事情を総じて、彼女たちに対して日本国と三菱重工が行った行為を「個人の尊厳を否定し、正義・公平に著しく反する不法行為」であったと断罪したのだ。

▲名古屋地方裁判所(Wikipediaより)
3 日本訴訟の判決結果
2005年2月24日、名古屋地方裁判所判決は原告らの心情まで踏み込んだ異例の事実認定をして原告らの被害に寄り添いながらも、被告国と三菱重工の行為に対する法的判断を回避し、請求権協定を理由として、原告らの請求を棄却した。その論理は極めて特殊技巧的なものであり、後の最高裁判決(2007年4月27日)の論理を先取りしたものであった。この論理については、後に述べる。
2007年5月31日、控訴審判決は、さらに踏み込んで、前記した国と三菱重工の行為は、「強制連行・強制労働」であり、「個人の尊厳を否定し、正義・公平に著しく反する不法行為」であると断罪したが、すでに出ていた最高裁判決(2007年4月27日)と同様の論理によって、請求権協定を理由として、原告らの請求を排斥した。
2008年11月11日、上告を斥ける最高裁決定によって、原告らの日本訴訟は敗訴の結末を見た。
以下では、原告らが敗訴を強いられた請求権協定に関する日本政府及び日本裁判所の解釈について検討する。
第3 請求権協定に関する日本側の解釈について 個人請求権は消滅していない
<ここから特別公開中>
1 政府見解
(1)「個人の請求権そのものを消滅させたものではない」
日本政府が繰り返し持ち出す請求権協定の2条1項は、次の通り定めている。
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、…完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」
2018年10月30日の元徴用工を原告とする訴訟において、新日鉄住金に対する賠償を命じた韓国最高裁の判決以来、日本政府は、「完全かつ最終的に解決された」と繰り返し、「国際法に照らしてあり得ない判断」、「暴挙」と口を極めて韓国判決と韓国政府に対する非難を繰り返している。これを聞いた者は、請求権協定によって完全に解決された以上、個人請求権は消滅したものと理解するに違いない。

▲新日鉄住金本社が入居する「丸の内パークビルディング」(Wikipediaより)
しかし、政府は、請求権協定が締結された直後から一貫して「完全かつ最終的に解決された」とする条文の意味について、個人請求権そのものを消滅させるものではないとの解釈を取ってきた。
代表的な例として、1991年8月27日参議院予算委員会における柳井俊二条約局長の答弁がある。
「請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますけれども…これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。」
この見解は、2018年11月14日にも河野太郎外相によって、再度確認されている(衆議院外務委員会・穀田恵二議員に対する答弁)。
「個人の請求権が消滅したと申し上げるわけではございませんが、個人の請求権を含め、日韓間の財産請求権の問題は請求権協定により完全かつ最終的に解決済みでございます。(中略)
請求権協定において、請求権の問題は完全かつ最終的に解決され、個人の請求権は法的に救済されないというのが日本政府の立場でございます。」
ここで、「解決した」意味として日本政府が主張しているのは、日韓両国の国家間では、国家として有する外交保護権が放棄され、国家間外交のテーマとして個人の請求権を持ち出さないという意味に止まるということである。したがって、「個人の請求権そのものは消滅していない」のである。そして、これは請求権協定締結以来、日本政府の変わることのない解釈である。
つまり、日本政府の解釈は、「個人請求権は残されたまま国家間では完全に解決した」という容易に理解しがたい奇妙なものなのである。
個人請求権が存在するのであれば、強制労働被害者である個人が、加害企業である日本企業に対して請求することは当然であり、裁判で勝訴するのも普通のことであろう。
国家間合意と個人請求権の問題は本質的には、国家は個人の権利そのものを対外的に処分、消滅させることができるのか、仮にできるとして、人道に著しく反する不法行為に基づく根源的な損害賠償請求権まで放棄できるのかという論点に分岐していく。

▲サンフランシスコ平和条約に署名する吉田茂首席全権と全権委員(1951年9月8日)(Wikipediaより)
しかし、日本政府がこのような解釈を取ったのは、より便宜的なその場しのぎのためである。端的に言えば、日本政府は、サンフランシスコ平和条約で、原爆被爆者の米国に対する損害賠償請求権を、後に日ソ共同宣言で、シベリア抑留者のソ連に対する損害賠償請求権を放棄したが、放棄したことの「日本国民に対する責任」を免れるためにこのような論法を取ったのである(これらの被害者個人の請求権は、国家間合意によって「放棄」されても消滅していないので、直接、相手国である米国やソ連に請求することができる、
したがって、これら被害者は日本政府による「請求権放棄」によって損失を被っていない、したがって日本政府には損失を補償する責任はないとする議論。
日本政府は、海外の被害者からの戦争責任追及を免れる前に、日本国民からの戦後補償責任の追及を免れ、そして、日本国民は、それを許した。今、起きている問題の根本は、むしろ、そこにこそあるのかもしれない。
(2)救済を拒む論理
海外の日本帝国主義の被害者が日本政府や加害企業を訴える訴訟は、韓国人被害者を原告とする訴訟を含め、1990年代初頭から多数、提起されるようになった(冷戦崩壊がこの動きを生んだであろうことは想像に難くない。以下、韓国の関係に絞って論を進める)。
しかし、被告とされた日本政府が、請求権協定を抗弁として主張するのは、ずっと後になってから、2000年代に入ってからである。
これは、この種の裁判が、まず時間の壁(消滅時効、除斥期間)、そして国家無責任(「国家無答責の法理」と呼ばれる。国家の権力的行為については、いかに残虐な不法行為であっても、国家は責任を負わなくてもよいとする法理)という壁によって(企業の場合は、戦前の会社とは別の会社であるという形式的な議論によって)、固く守られていたという事情がある。しかし、裁判所は、あまりにも悲惨な被害事実に向き合う中で、時間の壁も、国家無責任の壁も取り払い始めた(本件の名古屋高等裁判所の判決は、「個人の尊厳を否定し、著しく正義・公平に反する不法行為」については、国家無答責の壁を取り払っている。このような裁判状況の中、被告国は、「(仮に請求権があっても)請求権協定によって、応じる法的義務はない」という主張をするようになった。
通常の法的感覚では、とうてい理解不可能な主張である。

▲河野太郎外相(2018年4月17日 IWJ撮影)
これが前記河野太郎外務大臣の答弁する「個人の請求権は法的に救済されない」論である。
日本国民からの責任追及をかわすために「個人の請求権は消滅していない。だから米国やソ連に裁判を起こせ」と主張した一方で、個人の請求権が消滅していない海外被害者からの責任追及をかわすために今度は、「個人の請求権はあるが、法的に救済されない」という幾重にもねじれたことを言い出したのである。
かくして、「外交保護権は放棄したけど、個人請求権はある、しかし、個人請求権は法的には救済されない」なる珍妙きわまりない政府見解が完成したのである。
個人請求権は残したまま、「完全かつ最終的に解決した」とする立論は、反人道的な不法行為責任を永遠に存続させるという反人道的状態を固定化させるものに他ならない。
2 裁判所の解釈
(1)最高裁判決
では、日本の裁判所は、請求権協定が個人請求権にどのような効果を及ぼすと解釈しているのであろうか。条約を含む法解釈の最終的な権限は裁判所に専属する。当然ながら、政府解釈が誤っておれば、裁判所はこれと異なる解釈をし、政府の解釈を是正することができる。近代国家において普遍的に採用される三権分立は等しくこれを前提としている。行政府の解釈が司法府の解釈に優越するようなことは認められない。それは結局、司法府の存在理由を否定することに他ならないからである。
日本の裁判所の判断は、2007年4月27日に中国人強制労働被害者が西松建設を被告として損害賠償を求めた最高裁判決に示されたものが最終的なものである。この判決は、日中共同声明に対する判断を示したものであるが、中国が参加していないサンフランシスコ平和条約の枠組みによって判断するとした。このことから、同条約4条に基づく請求権協定については当然に同様の論理によると考えられる。現に同様の論理で名古屋高等裁判所は原告らの請求を棄却し、被害者原告らの上告を受けた最高裁は、原審の判断を維持した。
最高裁判決の平和条約の個人請求権に及ぼす効果についての判断は次のとおりである。
まず、戦後賠償について定めるサンフランシスコ平和条約14条(b)にいう請求権の放棄について、「ここでいう請求権の『放棄』とは、請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するのが相当である。」と判断した。
その上で、サンフランシスコ平和条約の枠組みは日中共同声明に及ぶとして、「日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は、日中共同声明5項によって、裁判上訴求する権能を失ったというべきであり、そのような請求権に基づく裁判上の請求に対し、同項に基づく請求権放棄の抗弁が主張されたときは、当該請求は棄却を免れないこととなる。」と判示して損害賠償を命じた原判決を取り消した。
最高裁は、被害原告らの実体的な請求権は消滅していないことを明確にしたが、裁判上、請求する権能を失ったとした。請求権はあるが、法的救済はできないという日本政府の見解を追認し、改めて「訴権喪失」なる法的な説明をしてみせたものであり、行政追随といわれる日本の最高裁の性格が如実に表れている。
しかし、さすがに悲惨な被害事実を前に最高裁も気が引けたのであろう。2点、日本政府の望まぬだろうことを付け加えている。以下、サンフランシスコ平和条約、日中共同声明に関する判示を請求権協定に置き換えて述べる。
一つは、請求権協定によって自動的に個人請求権から訴権が失われる訳ではないとしたことである。個人請求権の訴権が奪われるのは、「請求権放棄の抗弁が主張されたとき」(「請求権協定により解決済みとの抗弁が主張されたとき」)だと限定したのである。請求権協定は法規であり、法解釈は裁判所が職権をもってなすべき職務である。したがって、本来、請求権協定の法的効果は当事者の主張の有無を問わず、当然に生じるはずのものである。ところが、最高裁は、請求権協定によって当然に訴権が喪失するとせず、あえて、「請求権協定があるから払わない」と被告が主張して初めて訴権喪失の効果を認めるとした(抗弁構成)。このことは、逆に言えば、被告が「請求権協定により解決済み」との主張をしない限り、被告に対して損害賠償を命じることとなり被告は敗訴を免れないということを意味している。
もう一つは、「サンフランシスコ平和条約の枠組みにおいても、個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられないところ、本件被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人は前述したような勤務条件で中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受け、更に前記の補償金を取得しているなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待されるところである。」との付言をして関係者の自発的解決を促したことである。
ともあれ、この最高裁判決によって、一連の戦後補償訴訟に決着が付けられ、多数に及んだ日本訴訟は終焉を迎えることになった。
(2)請求権の性質
以上に見たように、日本は政府も裁判所も、請求権協定によって個人請求権が消滅したと解釈したことは基本的に過去一度もない。そして、個人請求権があるのであれば、訴訟上の救済を得られるのが自然であるが、これについては、いや訴権は喪失しているとして法的救済を認めないとするのが日本政府の解釈を受けた、日本の最高裁の判断である。
最高裁は請求権協定によって解決済みであることを被告が抗弁として主張した場合は、訴権が失われるとしているので、これは消滅時効と非常によく似ている。
時効にかかった債権は、自動的に消滅するのではなく、時効によって消滅したとする「消滅時効の援用」の主張がなされて初めて消滅する。時効の利益を享受するのか否かを債務者の判断に委ねているのである。債務者の判断の中には、法的には責任を免れることができるが、そうは言っても借りたものは返した方がよいのではないかというような道義的な観点も当然に含まれることとなる。
請求権協定によって「解決済みである」との抗弁がなされて初めて訴権が失われるとする最高裁判決の解釈は、時効の援用と確かに酷似している。しかし、決定的に違う点もある。
通説判例は、消滅時効が援用された債権は、「消滅する」と解している。一方、請求権協定によって失われるのは訴権だけで、実体的請求権は存在するとされているからだ。
最高裁の判例解説によれば、これは「自然債務」であるとされている。「自然債務」自体が、高度に専門的な概念で一般に「講学上の概念」であるなどとされており、滅多にない代物である。
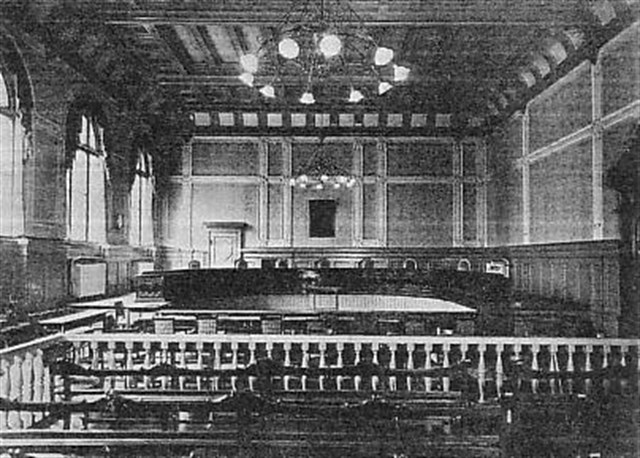
▲2代目大審院庁舎の大審院法廷(Wikipediaより)
古くはカフェの女給の気を引こうとした客が400円をやると約束したのにその約束を果たしてくれないとして訴えた事件で大審院(戦前の最高裁)が女給の訴えを棄却したときに持ち出した議論で、約束が履行されれば受け取る法的根拠になるが(新たな贈与にはならない)、裁判上の請求権を与えたものではないと判断した(大審院昭和10年4月25日)。
この事例が自然債務であると説明されている。その他、免責決定を受けた破産者に対する債権がこれに当たるとされるなど、ばらばらの分野の極めて限られたものが特別な理由からこれに当たるとされている。愛人になるという約束で豪華な金品を与えたにも拘わらず、別れることになってしまった場合の、金品の返還請求なども「自然債務」に当たるとする説もあるなど、実にばらばらなのである。したがって、これらを「自然債務」という一つの括りで議論するのは無意味であるとする説も有力である。
重要だと考えられるのは、これらの「自然債務」事例において、裁判所が、「実体的な請求権は存在する」などと確認的に判断した例はないことである。従来は、限りなく存在しないに近い債権に対応するものを「自然債務」と称していたのであって、平和条約や請求権協定などによって解決済みとされた「個人請求権」をこれらと同列に議論するのは違和感を持たざるを得ない。
むしろ裁判所は、戦後補償にかかる請求権については、限りなく実体的な権利性を認めようとしていると見られる。そのことは、従来の「自然債務」において、決してなされることのなかった「当事者及び関係者が自発的に解決することが期待される」という付言がなされていることからも明らかではないかと考えられる。
そうしてみれば、戦後補償訴訟において裁判所が確立した「訴権のない請求権」というのは、従来議論されてきた債権類型に該当しない新たな債権の類型を創出したと理解するのが適当である。
要するに、裁判所は、「完全かつ最終的に解決したのは、外交保護権のみを放棄したのであって、個人請求権そのものは消滅していない」、「個人請求権は消滅していないが、法的救済は受けられない」という日本政府の二重にねじれた支離滅裂な主張に対して、新たな債権の類型を創出してまで、これに対する法的説明を与えたのであった。
しかし、そうであれば、なぜそれによって「完全かつ最終的に解決された」と言えるのかという、根本的疑問に行き当たらざるを得ないであろう。
一般の読者にとっては、やや難渋な法的論点まで踏み込んで説明をしてみた。率直に言って、司法試験レベルに匹敵すると思われる。ここでお伝えしたかったのは、被害者の請求を排斥するのに、いかに裁判所がアクロバティックな特殊技巧的な議論を展開せざるを得なかったかということだ。
そして、その結果は、かえって「完全かつ最終的解決」とは何だったのかという疑問を突きつけてくるという事実である。
3 小結
日本の行政、司法とも、個人請求権は消滅していないという点で一致している。個人請求権が失われていないとしながら、法的救済は受けられないとするねじれた議論のために、極めて不自然な論になっている。
なお最高裁は、訴権が失われたとする理由を、個別的な民事訴訟で解決を図るのは、協定締結当時に想定できない混乱を生むため、個人請求権の問題は、国家間の交渉で解決するのが適切だとしていることに注目したい。
第4 韓国最高裁判決の概要
1 裁判官の意見分布
今回の韓国最高裁判決は、13名の合議体によって判決がなされている。
多数意見は7、多数意見と結論を同じくするが異なる理由により賠償請求を認容すべきであるとする個別意見が4名(個別意見1=1名、個別意見2=3名)あり、そして、賠償請求を棄却すべきだとする反対意見が2名である(その他に多数意見を補強する補足意見がある)。
日本における議論と異なるのは、日本では、個人請求権が全て請求権協定の対象に含まれることが当然の前提とされているのに対して、まず、訴訟の対象になっている請求権が請求権協定の対象に含まれるかどうかが議論されている点である(多数意見は含まれないとした)。続いて、請求権協定の対象に含まれるとした場合に、個人の請求権は制限を受けるかが議論されている。3名が対象となっているが、個人の請求権は消滅しないとして請求を認め、2名が対象となっており、個人の請求権行使は制限を受けるとして、反対意見を述べている(反対意見の趣旨は、日本最高裁の論理に近いが、より緻密に検討した形跡が見える)。
まず、意見の多様性に注目したい。前記した日本の最高裁の判決は5名の小法廷によるものであったが、全員一致である。また、異なる小法廷で軍による中国女性集団監禁レイプ事件も判決が出ているが、これも全員一致であり、日本の最高裁の高度にアクロバティックな論理は、最高裁裁判官の全員一致であると考えて間違いない。彼我の差を見せられる思いがするのは、私だけではあるまい。
この多様な意見を通じて、日本で議論されているような内容は、韓国最高裁の中で議論が尽くされていることがわかる。
2 多数意見
多数意見は、この事件における請求内容である「日本政府の韓半島に対する不法な植民支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権」は請求権協定によって解決された個人請求権には含まれないとしたものである。
原告らの請求権は、請求権協定の対象外と判断して原告らの請求を認めたものである。
日本では、韓国最高裁の判決も読まずに、国際法上の観点から判決を批判する議論が有力な学者からも出される等、的外れな議論が少なくない。協定の対象に含まれないのであれば、その解釈の当否が問題とされるのはともかく、国際法上の観点から原理的にあり得ないなどとする批判は全く当たらないことは明らかである。
判決は、請求権協定が、サンフランシスコ平和条約の14条の戦争賠償条項によるものではなく、4条の財産・請求権清算条項に基づくものであって「両国間の財政的・民事的な債権・債務関係を政治的合意によって解決するためのもの」との基本的性格を認定し、請求権協定に賠償請求を含むことは困難であったとしている。

▲盧武鉉・韓国大統領(第16代)(Wikipediaより)
また、日本では、韓国最高裁判決は、韓国政府の見解に反しているとする見解が一般であるが、これは誤解である。判決は、盧武鉉政権当時、個人請求権問題を検討した2005年の官民共同委員会の見解も検討しているが、同見解が必ずしも強制労働被害者の請求権を日韓請求権の適用対象とする前提に立つものではないと判断している。
いわゆる5億ドル(内無償の3億ドル分)が個人請求権と対価関係がないとの判断も示されている。以下では、この問題について改めて請求権協定の条文から検討を加えたい。
第5 請求権協定による資金は賠償金・補償金ではない
1 「5億ドル問題」についての誤解
日本では、請求権協定に基づいて日本が支払った5億ドルを、韓国政府がインフラの整備等に流用したため被害者に対する救済が不十分であったとする風聞が一般的である。問題は韓国政府の流用によって起きたのだから、第一義的に韓国政府の責任において処理すべき問題であるとする理解である。
あまりにも誤解が一般化し過ぎており、日本の植民地支配の問題に向き合おうという姿勢のある人ですら韓国政府の流用に原因があると思い込んでいることがある。
これは、請求権協定の条文さえ見れば、直ちに氷解する初歩的な誤解である。
2 5億ドルの内容
請求権協定によれば、5億ドルの内、2億ドルは「貸付」であり、3億ドルが「供与」(無償)である。つまり、利息が付いて返ってくる金も含んで5億ドルである(他に民間借款が3億ドルあり、8億ドルと言われることもあるが、これも貸付であって、供与ではない)。
そして、これらは全て「日本国の生産物及び日本人の役務」で提供されることが請求権協定には明記されている。かつ、「大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない」とされており、これらの内容については「両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する」こととなっており、資金の使い道まで、日本政府が主張できる内容の資金としての5億ドルである。
こうした規定に基づいて提供される請求権協定資金が、被害者の賠償に使われることを予定していなかったことは明白である。どうすれば、韓国の経済発展に役立つ日本の生産物や役務を被害者個人の救済に充てられるというのか。この点に関して流布されている誤解は、あまりにも不自然という他ない。
確かに交渉過程において、強制動員被害者に対する未収金や補償を韓国政府が求めていたことは事実であるし、この要求を勘案して日本側から無償3億ドルの金額が提示されたことも事実である。
しかし、最終的には、日韓両国政府は、経済協力資金で妥結し、被害者の個人請求権をインフラの整備等にすり替えたのである。
交渉過程で韓国政府は植民地支配の不法性を前提に賠償金を請求し、日本政府は植民地支配は正当だったとして、賠償や補償を一切、拒絶した。その結果、落ち着いたのが経済協力方式だった。
3 開発援助としての請求権協定資金
「日本国の生産物及び日本人の役務」で行う経済協力は、海外で行われる日本の公共事業に他ならない。日本政府が日本企業に発注して、受注した日本企業が韓国で事業を行う。その代金を日本政府が支払う。まさに開発援助である。

▲ソウルにあるポスコタワー(Wikipediaより)
代表的な例として知られるのは、韓国最大の製鉄所となった浦項(ポハン)製鉄所(現ポスコ)の例だ。この製鉄所は徴用工訴訟の被告となっている新日鉄住金(富士製鉄、八幡製鉄)と日本鋼管(現JFE)が、日本政府から受注して、製鉄所の建設に当たった。要するに、戦争中、徴用工に劣悪な条件での労働を強い、賃金も払わずに利益をむさぼった企業が、戦後は、請求権資金で大規模プロジェクトを受注して潤った。しかも、新日鉄住金にとっては、その後長く続く韓国市場での足場を築くこともできたのである。
ODA(政府開発援助)が、戦後賠償から始まったことは政府自身も認めているところであり、2014年版「政府開発援助(ODA)白書」(外務省)には、次の通り記載されている(第1部第1章第1節1)。
「初期の日本のODAは、主として戦後処理としての賠償支払いと並行して行われました。1954年のビルマ連邦(現ミャンマー)との賠償・経済協力協定を皮切りに、フィリピン、インドネシア、ベトナム共和国(南ベトナム)との間で賠償協定が結ばれたほか、同じく戦後処理の一環として、対日賠償請求権を放棄したカンボジアとラオス、さらに、タイ、マレーシア、シンガポール、韓国およびミクロネシア連邦に対しても、経済協力等が行われました。(略)このような賠償と、それに並行する経済協力は、戦後処理を進め、近隣のアジア諸国との関係改善や日本の国際的地位の向上につながるだけでなく、輸出市場の拡大を通じた日本経済の復興と発展に寄与することも期待されていました。」
「戦後処理の一環として、対日賠償請求権を放棄した」とされるグループに韓国も含まれるとともに、「輸出市場の拡大を通じた日本経済の復興と発展に寄与」したことも明記されている。
大日本帝国臣民に塗炭の苦しみを与え、侵略戦争で帝国臣民や徴用工・中国人労務者(華人労務者)等から搾取して利益を上げた日本企業は、戦後は戦争賠償、戦後処理の名で、大規模な海外事業を日本政府から受注して再び利益を上げたのである。
請求権協定による経済協力資金は、両国政府の管理の下で、10年間の延べ払いで合計5億ドルまで「日本の生産物及び日本人の役務」として提供されていく。政府には事業名、事業内容、受注企業名、受注金額を記載した「請求権協定事業総覧」のような総括的な文書が存在する筈であるが、明らかにされていない。
4 経済協力資金による開発援助と個人請求権の関係
前記のとおり韓国最高裁は、請求権資金と個人請求権の間には関係がないと判断した。つまり請求権資金が提供されたからと言って、個人請求権に影響が及ぶものではないと判断したのである。
日本政府も明確に請求権資金と個人請求権は無関係であるとしている。

▲椎名悦三郎(Wikipediaより)
請求権協定締結直後の国会において、条約締結を担当した椎名悦三郎外務大臣は、次の通り答弁して、請求権と経済協力は無関係であることを力説した。いわゆる「独立祝い金」答弁である。
「請求権が経済協力という形に変わったというような考え方を持ち、したがって、 経済協力というのは純然たる経済協力でなくて、 これは賠償の意味を持っておるものだというように解釈する人があるのでありますが、法律上は、何らこの間に関係はございません。
あくまで有償・無償5億ドルのこの経済協力は、経済協力でありまして、韓国の経済が繁栄するように、そういう気持ちを持って、また、新しい国の出発を祝うという点において、 この経済協力を認めたのでございます」(参議院本会議1965年11月19日)
5 日中共同声明との相違
さきに述べた日本の最高裁において、被害者に対する自発的解決を期待するとされた西松建設は、その後、同社が中国人被害者に謝罪し、基金を設立して同社の強制労働被害者に対する損害賠償を包括的に解決する和解を行った。同様の解決例は、鹿島による花岡基金、三菱マテリアルの例など複数存在する。

▲西松建設旧本社ビル(Wikipediaより)
こうした例に対して、韓国と中国では違う事情として、中国は、日中共同声明において金品の提供がないまま、全ての賠償請求権を放棄したと主張されることもある。
しかし、中国に対するODAは日中平和条約発効直後から実施されるようになったという事実がある。すなわち、日中共同声明に基づいて日中平和条約(1978年8月12日署名・10月23日発効)が締結された翌年度の1979年度から各種プラント事業にODAを開始し、2018年までに総額約3兆円以上のODAが実行された。この中には無償資金協力1576億円も含まれている
つまり、日本との国交正常化に伴い、経済協力資金を獲得した点において、中国と韓国との間には何の相違もない。請求権協定のような明文を伴うか否かの点で相違はするが、請求権と経済協力資金の間には何の関係もないことは日本政府が明らかにしているところである。
したがって、請求権資金(物品・役務)の提供は、中国と韓国の間で個人請求権の扱いを異にする理由とはならない。
6 「韓国政府が責任を取るべきだ」論の誤り
こうして、上記した中国人被害者との和解事例とは異なり、韓国人被害者と和解することはできないとする、残る根拠は、日韓会談の過程で、韓国側代表者が「強制動員被害者に対する補償は韓国政府が責任を持って行う」と述べたとする件のみとなる。
代表的な例として、河野太郎外相が2018年11月3日、神奈川県の街頭演説で述べた「1965年の国交正常化でいちばん問題になったのが補償や賠償をどうするかで、日本が経済協力として一括して韓国政府に支払い、国民一人一人の補償は韓国政府が責任を持つと取り決めた」とする主張である
河野外相によれば、個人請求権については、「補償は韓国政府が責任を持つと取り決めた」というのである。
政府の解釈によれば、「個人請求権は消滅しないが、全面的かつ最終的に解決した」とされる。これ自体支離滅裂な解釈であるが、さらに日本政府は「経済協力資金は独立祝い金であり、賠償・補償とは全く関係ない」と個人請求権が残ることにダメを押している。
当然、個人請求権をどう処理するかは重大な論点である。
河野外相によれば、この「取り決め」について、書面化することなく、「韓国政府が責任を持つ」とする、口約束をしたというのである。
請求権協定を見れば、明らかだが、「完全かつ最終的に解決」し、「いかなる請求もすることができない」ようにするために、極めて子細を尽くした言葉使いで合意署を交わしている。それにも拘わらず、「(消滅していない)個人請求権についての処理は韓国側が責任を持って行う」との一文を入れなかったというのだから、そうした確たる合意は成立しなかったという他ないであろう。交渉過程で河野外相が主張するようなやりとりがあったことは事実である。交渉過程において様々なやりとりがなされ、合意は書面化される。
一大論点であることが明らかであるにもかかわらず、最終的には文章化しなかった「韓国政府が責任を持つ」という確定的な合意が成立して、取り決められたとするのは無理がある。重要事項について明記しなかったという問題はどこまでも弱点として残るのであって、請求権資金と個人請求権は無関係であるとしながら、請求権資金の提供によって個人請求権については、「韓国政府が責任を持つ」との口頭の、若しくは暗黙の取り決めがあったとする矛盾した主張が通るのか、普通に考えれば、誰の目にも明らかであろう。
第6 先延ばしの結末
1 判決遅延の経過
2018年10月30日の韓国最高裁の判決は、2012年5月24日の最高裁判決によって破棄差戻された高裁判決に対する再上告審の判決である。2012年になされた元の最高裁判決は、被害者原告らの請求を棄却していた高裁判決を破棄して原告らの不法行為請求権を認めた上、損害額について審理が尽くされていないとして、差し戻した判決であった。差戻を受けたソウル高裁は2013年7月10日に判決を下している。
先の最高裁判決は、請求権協定によっても徴用工らの個人請求権は失われず、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償である)を認め、損害額を決定するためだけに差戻をしたのであり、論点が限定された、再上告に対する最高裁判決は早々に出ることが予想されていた。
ところが、損害額を決めるだけのはずの上告審判決が出るまで、再度の高裁判決から実に5年以上を要したのである。この間、この訴訟に関心を持つ者は非常に不審な思いで判決を待っていた。
同じ事件(同じ裁判手続)で、最高裁が先に示した判断と異なる判断をすることは、極めて特殊な事情がない限りあり得ない。そのようなことを繰り返せば、裁判手続が極めて不安定になり、紛争解決機能は根本から阻害される。この判決遅延は異常で、最高裁が異なる判断をなすのではないかとする疑念も抱かせるものであった。
2 日本経済界・日本政府の動き
この間、差し戻し審であるソウル高裁の判決を受けた新日鉄住金は、和解を含めた対応を検討し、敗訴判決が確定した場合には、賠償金の支払いに応じる意向を固めたことが報道された
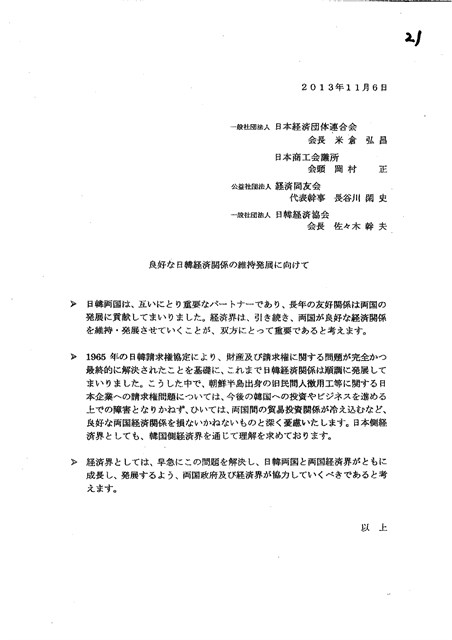
▲日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、日韓経済協会「良好な日韓経済関係の維持発展に向けて」(2013年11月6日)(岩月氏提供)
また、経団連ほか経済4団体は同年11月6日、「経済界としては、早急にこの問題を解決し、日韓両国と両国経済界がともに成長し、発展するよう、両国政府及び経済界が協力していくべきであると考えます。」とするコメントを発出した。
他方、日本政府は、ソウル高裁判決自体が国際法違反だとする、日本側の主張を韓国政府に伝え、企業側の敗訴が確定すれば、国際司法裁判所に訴えるなどと韓国政府に揺さぶりをかけた。それとともに、関係企業に対して、敗訴が確定しても支払いをしないように政府の立場を伝えた(産経新聞2013年11月25日)。日本政府の韓国政府に対する要求は繰り返され、韓国政府から基金方式による解決策が打診されると、これに強く反発し、「菅義偉官房長官や岸田文雄外相は、(1)判決前の和解には応じない(2)敗訴判決が確定し、韓国側が日本企業の資産差し押さえに出た場合は、日韓請求権協定に基づいて協議を呼びかける(3)協議が不調に終わった場合は国際司法裁判所(ICJ)へ提訴する-との方針を確認し」、「韓国側にも複数の外交ルートを通じて伝えた」とされる。
3 顛末
日本政府のこうした強硬な対応が、どのように今回の裁判遅延につながったか具体的な経路は現段階では明らかではない。しかし、普通にはあり得ない裁判遅延が日本政府の強硬な対応と無関係ではないことは明らかであろう。韓国内では、この間の裁判遅延について、韓国最高裁事務総局の具体的な関与が指摘されて刑事事件に発展している。日本政府の強硬な対応がいずれかのルートを経て韓国最高裁事務総局を動かしたと見るのは自然である。
この間、日本政府は、韓国政府に対しても、日本企業に対しても、解決を拒むように働きかけを続けてきたもので、経済界に存在した自発的解決の芽を摘みとってきたのは日本政府の強硬な姿勢である。
日本政府のこのような対応は日本国にも、日本経済界や日本国民にも不幸をもたらす以外、何物も生み出さない。
第7 解決への道
1 日本政府の対応の拙劣さ
日本政府は、「国際法上あり得ない判決であり、毅然として対応していく」(安倍首相)、「判決は暴挙」、「国際法に基づく国際秩序に対する挑戦」「適切な対応がなされない場合は、あらゆる手段を取る用意がある」(河野外相)等、判決を強く糾弾している。
自国の立場を絶対視して、相手国の判決を非難するだけでは問題が解決しないことは明らかである。相手国を威嚇する態度は、問題の解決を困難にするばかりで、いたずらに両国の対立感情を煽る拙劣なものといわざるを得ない。
この間、日本政府は対抗策として、司法裁判所への提訴に繰り返し言及し、その都度、報道が繰り返された。
国際法上、原則として、国家が最高の主体とされる。国際司法裁判所も当然に国家の上位にある訳ではなく、裁判手続を相手国に強制できるものではない。例外的に強制できるのは、両当事国が、国際司法裁判所の強制管轄を予め受諾している場合に限られている。強制管轄を受諾している国は70カ国に止まっており、日本は受諾しているが、韓国は受諾していない。したがって、仮に日本が提訴しても、応訴するか否かは、もっぱら韓国政府の自由に任されている。
このことを承知で、日本政府が繰り返し国際司法裁判所への提訴に言及するのは、自らの主張の正しさを国内向けに信用させる手段でしかなく、いたずらに国民感情を煽る以外に、何の意味も見いだせない。仮に提訴して、韓国政府が応訴しない場合に、この韓国政府の対応を、さらに非難しようとするかのようにも見えるが、応訴しないことについて、何ら韓国側に非難されるような謂われはない。
たとえば、現在、トヨタは、米国でシートの不具合を理由とする巨額賠償を命ずる判決を受けているが、これを国際司法裁判所に提訴して、強制管轄を受諾していない米国が応訴しないのはけしからんなどと非難するなどということがあり得るかを考えれば、このことは容易に理解できるはずだ。
2 日韓請求権協定による解決手続
日韓請求権協定は、両国の請求権協定に対する解釈が相違する場合の解決方法の定めを置いている(3条)。
それによれば、解釈の相違は、まず外交ルートによって解決するものとされ(3条1項)、交渉によって解決が得られない場合は、仲裁によって解決するとされている。仲裁委員は、両国がそれぞれ1名を指名し、両者の合意によって第3の仲裁委員を指名し、この3名によって仲裁委員会を構成するとされている(3条2項、3項)。仲裁委員会の判断には拘束力があり、両国は仲裁委員会の判断にしたがうものとされている(3条4項)。(なお、3条2,3項は、一方が仲裁委員の指名を怠る場合を想定して、相当に周到な規定となっているが、それでも仲裁委員会不成立の場合はあり得るようである)
請求権協定に明示されている手続があるのであるから、日本政府は、本来、外交ルートを用いて解決を探るべきである。
今後も同様の判決が繰り返されることが予想される。そのような事態を放置することは、事態をエスカレートさせるだけであって、誰も望まない筈である。
すでに現段階で、新日鉄住金、三菱重工に対しては、敗訴判決が確定しているのであり、日本政府としては、外交保護権に基づき、韓国政府に対して、外交交渉を求めることが可能な立場にある。日本政府は外交交渉を求めることができ、請求権協定上、韓国政府は応じる義務を負っている。日本政府は、請求権協定の筋道にしたがい、外交交渉による解決を目指すべきである。
韓国政府から外交交渉を求めることも可能である。しかし、「解決済み」とばかり繰り返す日本政府が応じる目処がないために交渉が成立していないのではないかと想像される。
3 解決の可能性
11月5日、韓国最高裁判決に対する弁護士有志の声明が発表された(発表当時、弁護士80名・学者6名。11月17日現在弁護士275名・学者13名。)。
声明では、本件問題の本質がまず重大な人権侵害行為であり、その救済が図られるべきことを指摘している。そして、日韓請求権協定は自発的な解決の何らの障害にもならないとして、新日鉄住金等に対して、包括的解決に取り組むよう自発的解決を求めている。
日韓両国は、個人請求権は残されているという点において共通しているのであり、重大な人権侵害行為について自発的な解決が望ましいという日本の最高裁判決もある。日本の最高裁が結論において訴権喪失の抗弁を認めたのは、訴訟による個別的解決に任せるのは適切ではないとする点にあった。今回のように日韓間の大きな問題に発展しているケースこそ、関係企業とともに政府が積極的に解決を図ることが適切である。ただ、敵対感情を煽る日本政府の振る舞いはこうした自発的解決を著しく困難にするだけである。
韓国大法院が徴用工等の慰謝料請求を日韓請求権協定の対象外であるとした実質的理由は大きく分けて二つある。一つは本件が「不法な植民地支配に直結した行為」であること、二つは「反人道的不法行為」であることである。後者に着目する限り、深刻な人権侵害行為を放置してはならないという共通の価値観に立つことが可能であるし、そうした立場に立つことこそ国際人権法の発展にも寄与する貢献となる。
歴代政権は、植民地支配に対する「痛切な反省と心からのお詫び」を繰り返し述べており、安倍総理も戦後70年の首相談話において「この立場は今後も揺るぎない」と確認している。こうした原点に立ち戻り、日韓両国政府・経済界が抜本的解決に向けて知恵を絞ることが求められている。
4 植民地主義の克服
(1)日本政府の対応、日本世論に現れた植民地主義
一国において最終的な法解釈の権限を有する他国の司法府の判断に対して、頭ごなしで非難する日本政府の高圧的で威嚇的な対応は、実に不愉快である。恰も韓国政府に対して、司法府の判断を正せと裁判干渉を求めるような感情的な非難は、韓国の三権分立を完全に無視している。全国紙の中にも同様の論調が目立った。韓国政府が責任を取るべきであるとの結論を明確に述べた新聞社もあった。
こうした日本政府や国内世論の対応の中には紛れもなく韓国を日本の下に見る植民地時代の感覚が含まれている。
(2)入管法改正と植民地主義
本件判決と同時期に進行した出入国管理法改正法の審議の過程では、国際貢献と称して連れてきた技能実習生に対する賃金の強制貯金、過酷な労働実態や暴力など、虐待に等しい扱いが次々と明るみに出た。米国務省までもが人身取引白書で技能実習生が置かれた無権利状態に対して警告を発する有様である。
このような事態に対しては、近代日本に根深く刻まれたアジア蔑視の国民性を痛感せざるを得ない。監理団体や統括管理組織の役員に超党派の閣僚や議員、官僚が名を連ね、これらの団体が中間搾取によって利益を上げる構図は、かつて植民地や傀儡国家(満州)の利権に蝟集した者を想起させ、醜悪である。
戦後日本には、アジア蔑視が連綿として生き続け、20年以上に及ぶ経済停滞の中、再びこれが噴出している。入管法改正は、かつての「華人労務者内地移入」、「朝鮮人内地移入」の引き写しである。

▲森友学園との土地取引の経緯に関する決裁文書の改竄問題に関する記者会見で、笑みを浮かべながら話す麻生太郎財務相(2018年6月4日 IWJ撮影)
韓国の徴用工訴訟の加害企業に麻生セメントなど、麻生財閥の関連企業が名を連ねていることは極めて象徴的である。今、日本を支配している政治家のトップは、植民地や傀儡国家の人々の血と汗を吸い上げて巨大な利益を上げた者たちの子孫(※)なのだ。
※麻生財閥は、麻生太吉が福岡県飯塚市で1872年に始めた石炭採掘の麻生鉱業を手始めに、セメント事業などに、事業を拡大。九州で有力財閥となった。麻生太郎副総理兼財務相は政界転身までグループ企業の中核、麻生セメント株式会社の社長だった。
麻生鉱業における朝鮮人労働者が、1944年以降にあたる狭義の「徴用」とそれ以外にあたるのかといった区別など、詳細は今後の資料発掘にもとづいた検討を待たなければならないが、米国立公文書館より「麻生鉱業報告(Aso Mining Report)」が発掘されたことで、朝鮮人・中国人労働者だけでなく連合国軍の捕虜が麻生鉱業で強制労働を強いられていたことの裏付けが得られた。この文書は、2009年2月6日に当時民主党所属の参議院議員であった藤田幸久氏が、国会議員会館で開かれた「麻生鉱業捕虜使役問題に関する報告会」で発表したことでよく知られることとなった。
(出典)麻生首相の父、炭鉱で朝鮮人を強制労働させる(中央日報、2009年2月7日)
以下に基本的な二次文献を掲げる。
・横田一「麻生一族の過去と現在―首相側近が語る『強制連行否定論―』」『世界』第786号(2009年1月)90-98頁
・西成田豊「朝鮮人強制連行と麻生鉱業」『世界』第788号(2009年3月)120-125頁
・Fukubayashi Toru, “Aso Mining’s Indelible Past: Verifying Japan’s Use of Allied POWs Through Historical Records,” The Asia-Pacific Journal, 7-33-2 (August 2009), pp. 1-8
(3)植民地下における重大な反人道的不法行為
敢えて日韓の政府・裁判所の間に大きな相違を見いだすとすれば、基本的に、日本による朝鮮の植民地化が適法であったか、違法であったかの論点に行き着く(植民地争奪の侵略戦争が合法とされた時代であったとしても、元首の生命に対する個人的な脅迫によって国家の外交権を剥奪した上でなされた韓国併合が違法無効だとする韓国側の主張に理があるように思う)。
しかし、求められているのが、植民地主義の克服であり、重大な人権侵害行為に対する国際法上の裁きだとするのであれば、国際法上、植民地支配の違法性を争うのとは全く異なるアプローチが可能である。確かに、未だに植民地支配下における人権侵害行為に対する損害賠償が確定した事例は世界的に見ても存在しない。しかし、(たとえ合法であろうと)「植民地支配に直結した反人道的不法行為」について、加害企業が責任を負うべきだとする主張は、国際司法裁判所でも十二分に成り立つ主張であり、被害者が勝訴する可能性もある。むしろ国際人権法の潮流は、それを後押ししているのが現状だと言ってもよい。
三菱重工の勤労挺身隊員らの闘いは提訴準備から数えれば、すでに20年を越える。それ以前、韓国国内において「慰安婦」と誤解されて、強制労働被害者と認知されなかった長い孤独な年月を考えれば、韓国最高裁における判決の確定はあまりにも遅すぎた勝訴といわざるを得ない。
ただ、そのことによって、原告らは、国際法における人権法の新たな地平を開く可能性をもたらす存在となった。
日本政府が、威嚇的に繰り返す国際司法裁判所の見通しは決して日本政府にとって明るいものではない。
韓国政府には国際司法裁判所の提訴を受けて立つという選択肢もあるのだ。
5 アジアの国として日本
少なくとも今後20年のスパンに限ってみれば、東アジアは、その比重を高めつつ、確実に世界経済の中心の一つであり続ける。
繁栄する東アジアにある島国として、日本がアジアの国としての立ち位置を確立することが痛切に求められている。韓国最高裁判決のもたらすインパクトにどう対応するかが、今後の我が国の帰趨をも決しかねない。









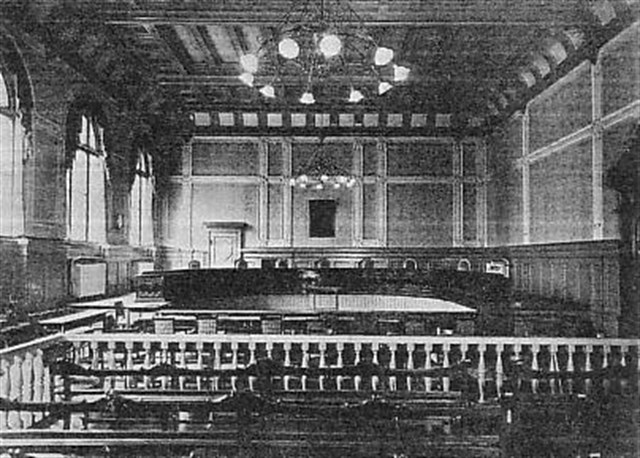




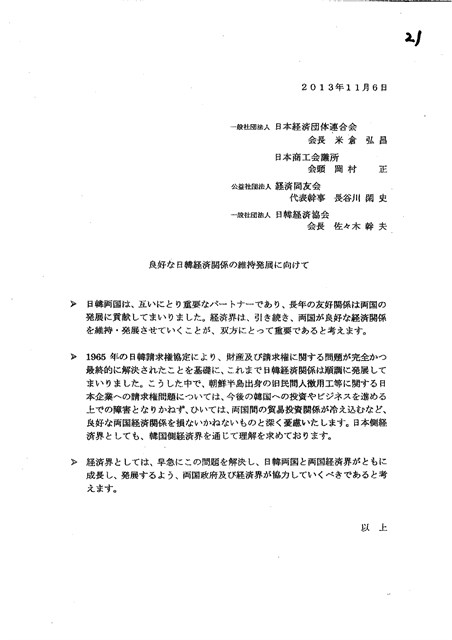




































奥が深いないようですね。
歴史を見ると朝鮮も日本も考え方が似てますね。
汚れた嫁・・・・外で作った子供を育てられる・なんか日本も女性の
差別は酷いですからね。
まだ私は勉強不足と感じた記事ですわ。