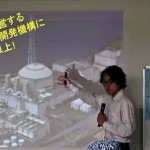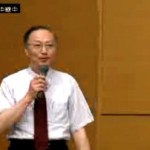- 内容
報告 曽根康夫氏(医師)「フクシマの被曝問題」
講演 片山恭一氏(作家)「原発をやめ、愛ある日々と未来を」
- 日時 2013年6月23日(日)13:30~
- 場所 愛媛大学南加記念ホール(愛媛県松山市)
- 主催 伊方原発をとめる会
文学が目指すもの
片山氏は、「原発をやめる」ことの意義を、文学的な見地から語りかけた。まず、玄海原発運転差し止め訴訟の法廷での意見陳述において、「核エネルギーを容認することは、自分の文学を否定することになる」と発言したことについて、かなりの時間を割いて、その趣旨を詳しく説明した。
この中で、自身が考える「文学が目指すもの」について、「人間という概念の拡張」とする考え方を紹介した。特に、近代文学においては、波乱万丈記のような偉人的な作品とは別に、非常に深い苦悩を抱え、殺人や不倫、姦通などに手を染める場面を描いた作品が好んで読まれている点を挙げ、「人間には深さや幅があるということを、文学は指し示そうとしている」と語った。また、文学を読むことについて、「道徳的な判断からひとまず離れ、ニュートラルな立場で物事を判断するテクニックを身につけること」と意義を述べた。そして、人間の願望や空想は無限の広がりを持つ一方で、「人間の能力にはおのずと限界がある」とし、「人間の持つ自由」については、「時間的にも、遠い過去から未来を貫くもの」とした。
その上で、「日本国民とか、電力会社の社員とか、そういった立場を離れて、『人間』という場所でものを見られるか、判断できるかが、自由や主体性ということになる」と述べた。そして、「文学作品には、悪いことをする奴や卑しい奴など、いろんな登場人物が出てくる。そういう錯倒した人間の難しさを通して、できるだけ広く人間を捉え、一つの価値観や善悪観、倫理観、あるいは国家利害や個人の利害、感情など、それらを離れたところで人間というものを捉えることができるし、歴史や世界を考えることができる。そういう場所を目指しているのが、僕は文学だと思う」と持論を述べた。
核エネルギーは、文学を真っ向から対立するもの
片山氏は「文学が目指すもの」について一通り持論を述べた上で、「核エネルギーは、文学のあり方、文学が目指しているものを否定し、文学と真っ向から対立するものである」と語った。その理由として、「放射性廃棄物の問題は、人間的環境から隔離して、数万年も数十万年も管理保管しなければならない。自分たちで処理できないものを、未来の人間に押し付けるということだ」と述べたほか、「地球環境や資源の問題でも、例えば二酸化炭素の排出基準をめぐって、いま欧米とか日本のような先進国だけで合意を作って他の国々に押し付けようとしている」と語った。
さらに、「たった半世紀ほどの間に繁栄を謳歌した国で、しかも、地球上のごく一部の人間だけでルールや合意を作って、それを世界に押し付けている」とし、「結局、押し付けるといっても、その負担を引き受けるのは、未来の人たちであり、未来に生まれる人たち。負担を未来に押し付け、自分たちのツケを未来に回すという問題が、原発や核エネルギーにはある」と指摘した。
技術をコントロールすることは、技術からコントロールされること
片山氏は、人間の持つ技術に関して、最も本質的な考察をしている人物として、ドイツの哲学者・ハイデガーを紹介した。この中で、「彼は『技術というものは、人間には制御できない難しさを持っているものだ』と繰り返し言っている」とし、「人間は、技術に対して、決して超越的に振る舞うことができない。人間が技術をコントロールするということは、同時に、技術からコントロールされているということだ」と続けた。
また、「原子力発電という技術を採用するということは、そこから核燃料を取り出すという、一つの大きな技術とされているが、それは同時に放射性廃棄物という形で、この先、数万年、数十万年にわたって、人間が技術からコントロールされるということだ」と語り、「放射性廃棄物を管理し続けなければならないという形で、技術に縛り付けられてしまうという相互性や双方向性を、人間の技術は必ず持ってしまうということを、ハイデガーは『ゲシュテル』という言葉を使って盛んに言っている」と述べた。
そして、「原子力発電が新しい技術として登場する。技術的にみれば、あるいは産業の歴史としてみれば、進歩や発展ということになるのかもしれないが、それは同時に、原発を厳重な管理のもとに運営、運転するということでもある」とし、「一歩間違うと、今回のように取り返しのつかない放射能災害を引き起こすという、よりストレスフルな技術との関係にとらわれるということを意味している」と述べた。
核エネルギーの容認は、未来の人たちの自由や主体性を奪うこと
さらに、片山氏は、「仮に、原発推進派が言うように、将来、核エネルギーをめぐる技術体系が完成し、人間に害を与えないような原発をマネージメントできるようになったとしても、より大きな、より深刻な技術的弊害や破壊性が待ち受けているというのは、技術の本質からして避けられないことだ」とし、「原子力発電を選択するということは、より技術的な未来を選択するということだし、非常にストレスフルな技術に拘束される、拘束されざるを得ない人たちを、未来に生み出してしまうということになる」と語った。
その上で、「そこには、現在と未来の他者に対する、現在からの規定や拘束がある」とし、「核エネルギーを容認し選択するということは、未来の人たちが人間として本来持つべき自由を限定し、歪曲し、彼らが主体的に生きる可能性を奪って、非常に狭い技術的な場所に縛り付けることになってしまう。彼らの自由や主体性を奪うことになってしまう」と厳しく批判した。そして、「以上の点が、意見陳述の中で、『核エネルギーの問題を容認する、放置するということは、自分のやっている文学を否定することになる』と申し上げた意味だ」と総括した。
「他者を公正に扱え」
片山氏は、講演タイトルの、「愛ある日々と未来」についても詳しく語った。この中で、九州大学農学部に在籍した片山氏が、文学に傾倒していったきっかけとして、大学の教養課程で国文学を学び、夏目漱石や森鴎外などの作品に出会ったことを挙げた。また、これらの作品が生まれた時代背景や、当時の人々の文化や風俗、恋愛観についても詳しく語った。
その上で、詩人であり思想家でもある北村透谷(とうこく)について紹介した。この中で、北村透谷を、「文学史的には、『恋愛至上主義のはしり』のように位置づけられる人だ」と紹介し、「恋愛は人世の秘やくなり」という書き出しではじまる「厭世詩家と女性」という評論について解説した。また、北村透谷が自由民権運動に挫折し、自身の自我の救済を、女性との恋愛に求めていったことを説明した上で、北村透谷や芥川龍之介、有島武郎や国木田独歩らが、「近代」と「恋愛」とを結びつけて考えたことについて、「日本の近代文学にとって、非常に大きなテーマであり、特徴的なことである」とした。
さらに、当時の近代文学の作家が、キリスト教の影響を強く受けていたことを挙げ、キリスト教が定義する「博愛」や「隣人愛」という考え方をもとに、「他者との新しい関係の可能性を示してくれるものとして、『他者を公正に扱え』というキリストの教えを、彼らはメッセージとして受け取ったのではないか」と分析した。
自分の欲望を抑制し、未来の人たちを公正に扱う
一方、「他者を公正に扱え」というメッセージを受け取ったとしても、「当時の日本社会には、他者を公正に扱うための自由や平等が実現する可能性はほとんどなかった」とし、その中において、現在からは考えられないほど女性の地位が低かった時代の中にあって、彼らは、女性を対等に扱い、自然な感情で愛するという関係に、「近代的な自我を求めたのだと思う」とした。また、そのことが、「彼らにとっては『主体的に振舞うこと』であり、『自由である』と感じられたのだと思う」と述べた。
そして、「自由や主体性の中には、自分の欲望を抑制し、相手の欲望を優先させるということが含まれている」と述べ、「例えば、自分の欲しいものを我慢して、好きな人のプレゼントを買う。なぜそうするのかというと、自分の欲しいものを買うよりも、それを我慢して誰かに贈り物をすることによって得られる喜びや満足感のほうが大きいからだ」と語った。
片山氏は、「そういうことを、原発についてもやればいいじゃないかと思う。未来に生まれる人たちに、安心して暮らせる、放射能のない安全な環境をプレゼントして、『幸せ』と思えばいいじゃないかと思う」と語った。さらに、「人間は、本当はそういうことがやりたくて仕方がない動物だと僕は思っている」とし、「電力がほしいという自分たちの欲望を抑制し、未来の人たちに、放射能に汚染されていない国土をプレゼントすること」「自分たちの不利益を受け入れることで、未来に生まれる人たちを公正に扱うこと」「未来の人々との間に健全な関係を築いていこうとすること」という点について、「自己のあり方として、僕たちはそれを喜ばしいもの、快いもの、心地よいものと感じることができるはず」と語った。
為政者の言っていることは見当外れだ
片山氏は、「経済的に豊かになることで、果たして僕たちは幸せになれるんだろうか」と疑問を投げかけ、「もう、経済的に豊かになることでは、僕たちは幸せになれないのではないかという気がする。もう、飽き飽きしているというか、疲れているような気がする」と続けた。その上で、「日本のGDPは世界第三位。これだけの経済力を持っていながら、国民の多くは、豊かさや幸せを実感していない。だから、『さらなる経済成長が必要だ』という理屈になるのかもしれないが、それは目指すものが間違っていると思う」と述べた。
そして、「原発を稼働させないと、日本の経済が行き詰まって、国が不幸になってしまう、そういうことが本当にリアルなのだろうか。あるいは、国防軍を作って防衛力を強化しないと、どこかの国が日本を侵略する、そんなことが本当にリアルなのだろうか。全然違う」と語り、「為政者の言っていることは、見当外れなのではないか。そんなところにリアリティなど全くない」と強調した。
さらに、「大量消費を続けているのではないか」「目に見えないところで誰かを虐げているのではないか」「誰かのものをかすめ取っているのではないか」「自然や環境を損なっているのではないか」といった不安感や、「自分が不当なことに関わっているのではないか」「意識せずとも、生きること自体が、不当なことに関わってしまうシステムの中に取り込まれてしまっているのではないか」といった嫌悪感を挙げた上で、「これらへの不快感や嫌悪感のほうが、よほどリアルだと思う」と語った。また、「現在や未来の他者を公正に扱っていないという『やましさ』が、形のない不安感のようなものとして、いまの日本の社会を覆っている気がする」とした。
「みんなで豊かに幸せに貧しくなっていく」という考え方を
片山氏は、「僕たちが目指すべきことは、経済成長や軍備増強ではなくて、現在や未来の他者を公正に扱うこと。その一つの契機として、脱原発を考えていけばいい」とし、「原発から離脱するということは、なんとなく不正で不当なことをやっている自分から離脱するということ。そういう自分の生き方から離れる、少しでも離れようとすることだ」と述べた。
その上で、「経済成長や軍備増強、あるいは大量消費などをいい加減に切り上げ、これからは『みんなで豊かに幸せに貧しくなっていく』という考え方をするべきじゃないか。そのことが、現在と未来の他者を公正に扱うことになる」と強調した。さらに、「誰もが、そういう生き方を望んでいるはず。なぜかというと、恋愛と同じモチーフ、恋愛と同じ情動がそこには流れているから」とし、「みんな本当はやりたくて仕方がないはず。原発から離脱することに夢中になると思う。そこには恋愛と同じ喜びや充実感があるはず」と力説した。
憲法9条にも言及
片山氏は、憲法9条にも言及し、国際的には武力行使は違法という考え方が趨勢(すうせい)を占めているのに、「自衛」という大義名分によって戦争や紛争がなくならない現状に憂慮の念を示した。その上で、「自衛という考え方をいかに乗り越えるか。自衛権の否定を考えていかないと、戦争を回避し戦争をなくすことにはならない」と持論を述べた。
一方、戦力の不保持と交戦権否認を規定した、9条2項の非戦条項を変えようとする人々について、「人間という場所に立てない考え方だ」と批判した。そして、「9条の非戦条項は、国や文化を超越している。地球上の全ての人間が共有できるものであり、人間や人類が普遍的な立場を取りうる、現実的には唯一の場所ではないか」とし、「僕たちが最も自由に、主体的に生きることのできる場所が、9条の非戦条項に象徴されている」と強調した。
■曽根康夫医師による問題提起
なお、片山氏の講演に先立ち、愛媛大学医学部出身で医師の曽根康夫氏が、「フクシマの被曝問題」とのテーマで問題提起を行った。この中で、曽根氏は、福島第一原発事故により、高濃度の放射能汚染に見舞われた飯舘村を訪れ、各所で線量を測定した結果や、農地で行われている大規模な除染事業などについて解説した。また、甲状腺ガンを引き起こす恐れのあるヨウ素131による被曝について、「国は、事故発生直後に、甲状腺内部被曝調査を適切に行わなかった」と述べた上で、弘前大学の床次(とこなみ)眞司教授らが事故から1ヵ月後に調査した測定データを紹介したほか、周辺住民を対象に福島県が実施した調査で、甲状腺ガンや、ガンが疑われる症例が通常より高い確率で見つかっていることについて、強い懸念を示した。
■片山恭一氏の講演内容全文
今日、ここに来るまでに、こういうことになっているというのは知らなくて、伊方原発に反対しておられる方の集会があって、そのいろんなイベント中の一つの流れとして、いろんな出し物の一つとして、僕の話があるんだと思っていたんですけども、「片山恭一講演会」ということになっているのは知りませんでした。
最近はときどき、こうして講演会なんかに呼ばれてお話しすることがあるんですけれども、そうすると、どうも主催者の人たちは「愛」という言葉に絡めた企画を立てたい、そういうふしがあって、今日の講演のタイトルも、「原発をやめ、愛ある日々と未来を」ということになってるんですけども。何なんでしょうね、「愛ある日々」っていうのは。僕のほうが教えてもらいたいというところもあるんですけど。去年の暮れに、玄海原発訴訟の原告として意見陳述をしたんですけれど、そのときの地元の新聞が取材をしてくれまして、翌日の見出しが、「法廷の中心で、脱原発をさけぶ」というものだったんですね。ですから、だいたいそういう調子ですので、慣れてしまって、少々のことでは驚かないというふうになってるんですけどね。
意見陳述では、「核エネルギーを容認することは、自分の文学を否定することになるんだ」というような、かっこいいことを言ってますが、法廷だからそれぐらいのことを言ったほうがいいだろうと思って言ったんですけども、今日のチラシにも引用してもらってたみたいですね。ですから、身から出た錆というか、自分で自分の立場を苦しくしているところがあるんですけれど、今日は最初にその話を少しさせてもらおうかなと思っています。なぜ、核エネルギーを容認することと、それが文学という、自分のやっている文学という仕事を否定することになるのかという、その話をしたいと思います。
僕は、文学というものはどういうものだと考えているのか。僕は、意見陳述でも書きましたが、人間という概念を拡張するといいますか、人間の可能性を探るというのが文学だ、そういうものだと思っています。人間の概念の拡張とはどういうことか、わかりやすくいえば、例えば100メートルを9秒台で走るというのも、人間という概念の拡張であるわけです。限られた人ではありますが、それだけの潜在能力、隠された力があるというのを証明するのが、人間の概念の拡張ということになるのだろうと思います。
そういうことでいいますと、例えば、モーツァルトとかダビンチとか、そういう天才的な人のことを物語に書けばいいんじゃないかという話になります。実際、ルネッサンスがイタリアで起こりますが、ルネッサンスという時期には、天才という概念によって人間という概念を拡張しようとした、そういう時期だったと捉えられます。つまり、それまでは神様のことだけ考えていればよかったんですが、ルネッサンスの時代になって人文主義というか、人間というのは何なんだ、理想的な人間はどういうものなんだということを考えはじめると、いわゆる天才というか、天賦の才能を神様から授かった人たち、一種の万能、常人とは並外れたような能力を持った人たち、そういう人たちに、ひとつの人間の理想を見ようとしたわけです。
そういう時期があったわけですけれど、実際に皆さんが小説をお読みになると、特に、近代文学といわれている、主に19世紀以降に書かれた小説ですけれど、そういう小説をお読みになると、あまりそういう天才的な人の話というのは出てきません。あるいは偉大な人とか、あまりそういう話は出てきません。むしろ、人間の弱さとか卑しさとか強欲さとか、あるいは残酷さ、残虐さ、どちらかというと暗い面、あるいは悪い面を描いた作品のほうがずっと多いわけです。そういう作品に優れた作品が多いというのも、文学の面白いところだと思うんです。例えば、マルキ・ド・サドというフランスの小説文学者がいますけど、あるいはもっと新しいところでいいますと、ドストエフスキーとかフォークナーとか、明白な人間の悪を描いた小説家というのが何人もいます。
では、そういう作品、人間の悪というのを描くことで、人間という概念の拡張が起こるのかということなんですけども、僕は二つの面から考えることができると思います。一つは、人間というのは、こんなことを考えたり、こんなことをやってしまったりだとか、そういうその、幅として非常に広い可能性を持つ、良いほうにも悪いほうにも、幅を持ってるんだということを描くということだと思います。良いほうでいえば、天才的な人たちや偉大な人たちとか、そういう人たちの生涯を描いて、彼は波乱万丈の人生を歩んだ、あるいはこういう苦労をして偉大なことを成し遂げましたという、そういう書き方をしてもいいわけですけども、そうすると文学作品としても、ちょっと物足りないというか、どういうところが物足りないかというと、要するに、自分とかけ離れた人のことを読んでも、共感できないというか、何か自分とは遠い人たちの話だというふうになるんだと思います。
それよりは、自分と似たような人間が、非常に深い苦悩を抱えているとか、あるいはこんなに豊かな感情を持っているとか、そういうことを示したほうが説得力があります。だから、例えば一人の青年がある観念にとりつかれることで、罪もない老婆を殺して金を奪ってしまうとか、あるいは上流社会のご婦人が、ある状況に置かれたことで、不倫というか姦通の罪を犯してしまうとか、そういうお話が非常に多くなってくるわけです。それを僕らが面白がって読むわけですけども。結局それが何をやろうとしてるのかというと、人間というのは、幅があるものなんです。
普段、僕たちは市民生活で、ある程度、道徳とか法律とかモラルに則った行動をしていますが、あまり常識外れなことはしないけれど、可能性として、非常に深さもあれば振幅もあるという、そういうものなんだと、文学は指し示そうとするわけです。そうすることによって、人間に対する認識が深まったりとか、あるいは視野が広がったりする、そういうことがあるわけです。それが、近代文学がやろうとしている人間概念の拡張という一つのポイントだと思います。
もう一つ重要なことがあって、それは、そういう作品を読む側の問題、読者の問題ですけれど、たとえば作品を読んで、殺人は悪いことだ、あるいは殺人が描かれている本なんていうのは出版禁止にすべきだと思っているような人には、例えばドストエフスキーとかフォークナーの小説というのは読めないと思うんです。自殺はけしからんというふうにいえば、ゲーテの「ウェルテル」というのはけしからん小説ということになるでしょうし、あるいは姦通なんてとんでもないという人には、フローベールの「ボヴァリー夫人」や、あるいはトルストイの「アンナ・カレーニナ」は、とんでもない作品だということになるでしょう。あるいは赤裸々な性表現はもってのほかだという人は、D・H・ローレンスの「チャタレイ夫人の恋人」とか、ヘンリー・ミラーの「北回帰線」とか、あまりお読みにならない方がいいかもしれません。まして、サドの一連の作品とかは、地上から抹殺すべきだというふうに思われる方も出てくるかもしれないと思います。
ですから、こういう、特に近代文学といわれている作品を文学として観賞するには、とりあえず倫理とか善悪とか、貞操観念とか猥褻だとかどうだとか、そういう通説的な倫理観、あるいは道徳観念のようなものを、「括弧」に入れるというか、ちょっと離れないと、小説を読むということができないと思うんです。それが、小説を読むということなんですけども。ですから、あまり善悪にこだわりすぎるとか、あるいは個人的な好みとか快・不快という場所にあまり執着すると、文学を、小説を、文学として観賞することはできないということになると思うんです。
たまたまテレビでやってたんですけども、明治期の洋画家に黒田清輝がいますけど、彼が明治のはじめごろに、展覧会にはじめて裸婦像、ヌードを出展したんだそうです。そうすると、当時の日本人はヌードを鑑賞する習慣がありませんでしたから、非常に驚いて、一種のスキャンダルになったんでしょうね。それで、社会的な風紀を乱すということで作品の撤去を求められたとか、そういうことがあったらしいんですけども。でも、いま僕たちは、普通にヌードを鑑賞することができますね。美術館なんかに行ってルノワールの裸婦像を見て、「きれいだな」と思うことができるわけですけども。それだけ、僕らの自我のありようが広がったというか、明治時代の人たちと比べると、もう少し自我の余裕が出てきたといいますか、領域が広がったというように言えると思います。だから、逆に、裸体だとかヌード写真とか、「そういうものは、社会風紀を乱す」とか、あんまりうるさく言う人は、逆に性的関心が強いのかもしれません。そういう、性的にしか、女性の裸というのを性的にしか見られない人たちなのかもしれません。
ですから、芸術とか美という観念が成り立つためには、そういう道徳的な判断、あるいは個人的な好きとか嫌いというところを、ひとまず離れる必要があるわけです。それは、別に道徳的なものを否定するということではなくて、道徳的な判断に対して、ニュートラルな場所に立つとか、あるいは個人的な好み、快・不快ということを離れて物事を見たりとか、判断したりするという、そういうテクニックを身につけるということだろうと思います。ですから、文学作品を読むだとか、美術や音楽などもそうですけども、そういう芸術を鑑賞するというのは、そういう役割があるんじゃないかと思います。
僕たちは、普通は、一つの国家とか民族とか共同体に帰属しているわけですから、そこで無自覚に身につけている価値観があると思うんです。それを解除するというか、括弧に入れてくれる働きというのが、おそらく芸術、あるいは文学というものであって、それによって、より広い視点とか視野というところに立てる、そういう視点で物事を見るという術(すべ)を身につけていくということじゃないかと思います。それは、自我という場所、あるいは自分という領域が広がっていくことでもあるし、自分の感情とか利害を超えて、もう少し公平にというか、パブリックに、そういう視点で世界を見るという、そういうことであると思うんです。
僕たちは、普通は、一人一人は個人として生きているわけですし、一つの個体としての生命というのは、だいたい70とか80とか90ぐらいで終わってしまうわけですけども、そういう意味でいうと、個人としてなし得ることは、おのずと限りがある、限界がある。いくら足が速いといっても、100メートルを5秒台で走るとか、生身の人間にはおそらくできないだろうと思うんです。そういう意味で、僕たち一人一人というのは、有限な存在なんですけども、しかし、「こういうふうにありたい」とか、「人間とはこうあるべきじゃないの」とか、あるいは、「世界はこうなっていくべきじゃないの」とか、そういうことを考えたり、空想したり、構想したりするというのは、無限の拡がりを持つということができると思います。
時間的にも、遠い過去から未来を貫いて、全人間というのを調合することができる、それが、「自由」ということだと思うんです。人間にとっての「自由」だと。それは、日本国民とか、あるいは電力会社の社員とか、そういう立場を離れて、人間という場所でものを見られるかどうか、ものを判断できるかどうかということ、それが人間、僕らにとっての自由、あるいは主体性ということだと思うんです。
文学というのはそういうものを目指していると僕は思っています。だから、悪いことする奴とか、卑しい奴とかいろんな登場人物が出てくるわけですけど、そういう錯倒した人間の難しさを通して、できるだけ広く人間を捉え、一つの価値観、一つの善悪観、あるいは倫理観、あるいは国家利害とか個人の利害とか感情とか、もちろん一人一人あるんですが、それを離れたところでもう一回、人間というものを捉えることができる、あるいは歴史とか世界というのを考えることができるし、そういう場所を目指しているというのが、僕は文学だと、大きく漠然というと、そういうことだと思います。
そうしますと、核エネルギーというのは、そういう文学のあり方、文学が目指しているものを否定するといいますか、文学と真っ向から対立するようなところがあるわけです。例えば、放射性廃棄物の問題にしても、人間的環境から隔離して数万年とか数十万年とか管理保管しなければならないといわれていますけども、要するに自分たちで処理できないものを未来に押し付けるということですよね。未来の人間に押し付けるということだろうと思います。
あるいは、地球環境とか資源の問題でもそうですが、例えば二酸化炭素の排出基準をめぐって、いま欧米とか日本のような先進国だけで合意を作って他の国々に押し付けようとしていますけども、考えてみるとたった半世紀ほどの間に、日本なんかまさにそうですけども、半世紀ほどの間に繁栄を謳歌した国で、しかも地球上のごく一部の人間がそういうルール、合意を作って、それを世界に押し付ける。結局、押し付けるといっても、その負担を引き受けるのは、未来の人たちだし、未来に生まれる人たちですから、負担を未来に押し付けている。自分たちのツケを未来に回しているということだと思うんですね。そういう問題というのが、原発や核エネルギーにはあると思うんです。
それをもっと広くいうと、人間の持つ技術というものをどう考えるかということですけれども、人間の技術に関して、最も本質的な考察をしているのはハイデガーという哲学者だと思うんです。これはドイツの哲学者ですけれども、彼が繰り返し言っていることは、技術というのは、人間には制御できないものなんだと、何かそういう難しさを持っているものなんだと、彼は繰り返し言っています。つまり、人間は技術に対して決して超越的に振る舞うことができないといいますか、人間が技術をコントロールすることができないということですね。コントロールするということは同時に、技術からコントロールされているということなんだと。
それは放射性廃棄物の問題から考えてみてもわかることですけども、原子力発電という一つの技術を採用するということは、そこから核燃料を取り出すという一つの大きな技術とされていますけども、それは同時に放射性廃棄物という形で、この先、数万年、数十万年にわたって、人間が技術からコントロールされるということですね。その放射性廃棄物を管理し続けなければならないという形で、技術に縛り付けられてしまうという、そういう相互性というか双方向性を、人間の技術というのは必ず持ってしまうということを、ハイデガーは「ゲシュテル」という言葉を使って盛んに言っているわけです。
たとえば、水力発電とか火力発電がかつてあったわけですけども、それに代わって原子力発電というのが新しい技術として登場する。それは、技術的にみれば、あるいは産業の歴史としてみると、進歩とか発展ということになるのかもしれないんですけども、それは同時に、原発を厳重な管理のもとに運営、運転するということでもあるし、一歩間違うと、今回のように取り返しのつかない放射能災害を引き起こすという、そういう、よりストレスフルな技術との関係にとらわれるということを意味しているわけです。水車を回したりとか、風車を回したりという段階は、それは過酷な技術災害というのは考えられなかったんだけど、技術が発展する、進歩するということは、余計にシビアな状況、シビアな関係を技術と持ち続けなければならないという、そういうことになるわけです。
ですから、仮に、原発推進派の人たちが言っているように、将来原発を、核エネルギーをめぐる技術体系が完成し、人間に害を与えないような原発をマネージメントできるようになったとしても、そこに、より大きな、あるいはより深刻な技術的弊害だとか、あるいは破壊性が待ち受けているというのは、もうその技術の本質からして避けられないことなんです。それらも技術の本質なんだと考えた方がいいと思うんです。
したがって、原子力発電を選択するということは、そういう、より技術的な未来を選択するということだし、非常にストレスフルな技術に拘束される、拘束されざるを得ない人たちを未来に生み出してしまうということになります。そこにも、未来と現在の他者に対する、現在からの規定とか拘束というのがあるわけです。ですから、こういうように核エネルギーを容認する、選択するということは、未来の人たちが人間として本来持つべき自由を限定するといいますか、歪曲するといいますか、そして彼らが主体的に生きる可能性を奪って、非常に狭い技術的な場所に縛り付けることになってしまう、そういうふうに彼らの自由とか主体性というのを奪うことになってしまうんだというふうに思います。それが、先程の意見陳述の中で「核エネルギーの問題を容認する、放置するということは、自分のやっている文学を否定することになるんだ」というように申し上げたのは、そういう意味なんですけども。
これで、「原発をやめる」というのと「未来を」というのは、ちょっとつながらなかったような気がするんですが、あとは「愛ある日々」ですね。ちょっとこれもわかりませんけども、このあとどういう話をさせていただくかという問題があるんですけども。
ちょっと僕の話を少しさせてもらおうと思うんですけども。僕はプロフィールにもありましたけど、宇和島の出身で、高校まで宇和島にいまして、そのあと大学は九州大学という福岡の方にあるんですけども、そっちの方に移り住みまして、いまもずっと福岡に住んでるんですけども、大学は僕は農学部という所にいたんです。農学部は一応理系ですから、そのころはどちらかというと国語や英語よりも数学とか理科の方がちょっと得意だったと思います。
だから、高校時代までは僕は、文学的な顔とはほとんど無縁な生活をしていまして、ではどういうふうにして文学と出会ったのかと、文学に興味を持ったのかということなんですけども、大学に入って、大学の教養課程で国文学を取ったんです。その国文学の先生が夏目漱石の研究者だったんです。授業で漱石を題材として使われていて、そういうきっかけで夏目漱石を初めて読んだという感じなんですけども。
一通りめぼしい漱石の作品を読んで、違う人を読もうかなと思って、例えば森鴎外なら森鴎外を読むとします。そうすると、非常に古めかしいというか、古風な印象を受けたんです。漱石をたくさん読んだあと、例えば鴎外の作品を読むと、古い感じを受けたんです。それは、「舞姫」なんかは、もちろん文体は文語体で書いてありますし、雅文調(がぶんちょう)というんですかね、雅文調で書いてあって、文調そのものが、古風な感じがするんですけど、そういう作品だけではなく、例えば「雁」(がん)という作品がありますけども、現代小説と言い換えてもいいような作品です。
しかし、そういうものを読んでも、やっぱり古くさいというか、古めかしい感じがしたんです。もちろん、「雁」というのは非常にいい小説です。僕も好きな作品なんですけど、漱石の例えば「それから」とか「門」(もん)とか「こころ」なんかに比べると、一時代前の作品という印象を受けるんです。年齢が鷗外の方が多分、五つぐらい上だと思いますけど、それ以上に世代差があるんじゃないかという感じがします。つまり、とても同時代の作品とは思えない、一つ昔の時代のような作品という印象を受けるんです。
「雁」とはどういうお話かといいますと、時代設定は明治13年と、これは作品の冒頭に「明治13年の話である」と出てくるのではっきりしてまして、主人公は岡田という大学生なんですね。当時の大学制ですから、東京帝国大学の学生さんということになりますけど、あともう一人、女性、「お玉」という女性が出てくるんですけども、このお玉という人は、いろいろ事情があって、いまは高利貸しの妾(めかけ)になっているんですね。女中さんを一人置いて生活をしていると。そういう岡田という学生と、お玉という女性との淡い恋というか、恋のすれ違いみたいなのを描いた作品なんですけど。一応、恋愛小説ということになると思います。しかし、恋愛小説なんですけれども、やはり描かれている世界が特殊だというのが一つあると思うんです。要するに妾の世界ですから、妾というか、そういうふうにお金で買われた女性たちの世界ですから、僕らからみると、古い感じがするんでしょうね。
そういう世界を、鴎外はうまく描いていまして、鴎外の作品というのは雁に限らず、遊女とか、いわゆる玄人筋の女性をよく描いているし、うまいんですね、それが。それは鴎外だけではなくて、谷崎潤一郎とか、永井荷風(かふう)なんかもそうですけどね。つまり彼らは多分、実生活でもそういう世界を知っていたんだと思いますね。つまり、吉原とか柳橋とか向島とか、いわゆる江戸時代の名残を残した場所というのを、彼らをよく知っていて、そういう遊女たちとの粋な遊びの世界といいますか、そういうものに結構触れていた、日常的に触れていたんだろうと思います。そういう感じを受けます。
江戸時代の恋愛というのがどういうものだったかというと、人情本にしても近松の浄瑠璃にしても、舞台はだいたい吉原などの遊郭が舞台なんですね。ですから、そこで描かれるのは主に既婚の男性と、それから、花柳界(かりゅうかい)の女性との色恋沙汰みたいな物語になるわけです。たとえば、商家の旦那が遊女に惚れて、そこに金銭問題が絡んで心中したとか、あるいは女の人を殺してしまったとか、そういう話が多いんですけど、近松門左衛門なんかは、そういう実際にあったこと、いまでいうニュースの三面記事とかゴシップを巧みに取り入れて、浄瑠璃の台本にしていたようですけども。それがヒットしたということは、それが当時の庶民に支持されていたというか、共感をもって読まれていたということでしょう。
その頃は、もちろん自由な恋愛というのがありませんし、結婚しても家同士の結びつきというような面が強かったんだろうと思います。だから、男、男性は家の外で、そういう玄人の女性を相手にするというのが普通だったわけです。ですから、鷗外とか谷崎とか永井荷風なんかの作品は、江戸時代の男女の色恋の面影をよく伝えているというか、残しているというか、そういうことでもあるだろうと思うんです。それが、僕が学生の頃、読んだときに感じた、古めかしさ、古風さということだと思うんですけどね。
それに比べると、漱石の小説に描かれる恋愛というのは、すごくモダンです。つまり、お金を介在させたプロの女性たちとの色恋ではなくて、割と教養のある中産階級の男女の普通の恋愛といいますか、もっと対等な恋愛というのを漱石は書いてます。だいたい、漱石というのは堅物といいますか、非常に真面目な人ですから、あまり知らなかったのだと思いますね。何というか、プロの女性たちの世界を知らなかったし、あまり興味もなかったんでしょうね。どちらかというと道後温泉に入ったりだとか、そういうほうが性(しょう)に合っていた人なんでしょうけれども。
ですから、そういう漱石の小説の中に出てくるのは、いわゆる新興ブルジョアジーといいますか、明治維新以降に財をなしたような人たちがだいたい出てきます。そういう、漱石自身の言葉でいうと「高等遊民」と言っていますけど、そういう人たちの恋愛を描いているわけです。さらに、漱石の特徴的なところですけども、そういう男女の関係というのを、非常にニュートラルと描いているといいますか、一人の人間と人間としての関係として、男女の恋愛というのを描こうとしているようなところがあります。
漱石の小説で非常にしばしば取り上げられるテーマというのは、男女の三角関係といいますか、一種の不倫関係のようなもので、それを何回も何回も漱石は取り上げていますけれども、明治の社会において、そういう男女の不倫というのは、非常にバッシングされただろうと思うんですね。親から勘当されたり、親戚から絶縁されたりとか、あるいは世間的には爪弾き(つまはじき)にされたり、そういう状況だったと思うんです。だから、そういう当時の社会道徳とか社会制度とは、真っ向から衝突してしまうような、そういう関係に立ち至ってしまった男女が主人公なわけです。で、彼らがどういうふうに生きていくか、特に男のほうはそういう場合、女性をどの扱うかというのが、漱石の非常に大きなテーマになっていきます。だから、僕らから読んでも、普通に読めるといいますか、現代の男女の恋愛としても共感をもって読めるということだと思います。
それに比べると、鷗外などの女性の描き方というのは、描き方というか扱い方というのは、非常に古風です。やはり、お金で仲良くなったり、都合が悪くなったらお金で関係を清算したりとか、当時はそれが普通だっただろうし、別にやましいことでも悪いことでもなくて、ただそういう社会があって、男の地位が圧倒的に強くて、女性の地位が弱かったということだったんだろうと思います。だから、鷗外だけが特別ひどい男だったというわけではなくて、むしろ漱石の方がものすごく先進的だったんですね。非常にモダンな問題意識を持っていたということだと思います。
で、この問題を、もう少し考えてみたいんですけども、漱石の同時代の人に、北村透谷(とうこく)という人がいます。この人は非常に早熟な人で、あまり早熟過ぎて、二十代半ばぐらいで自殺してしまうんですけども、一応、詩人ということで名が通っていると思いますけれど、思想家と言ってもいいと思います。文学史的には、恋愛至上主義のはしりみたいに位置づけられ方をする人です。島崎藤村に影響を与えたとか、そういう説明がだいたい出てくるんですけども。この北村透谷というのは、短い人生の割にはいろいろ、割といろんなことをやっていまして、早稲田大学の学生さんだったんです。
学生時代に、当時の自由民権運動というものに参加しているんです。その自由民権運動に参加して挫折して、キリスト教の洗礼を受けたりとか、そのあとに結婚したりとかもしているわけです。彼が書いた評論に、「厭世詩家と女性」という評論があるんです。「恋愛は人世の秘やくなり」という有名な書き出しではじまる評論なんですけど、厭世詩家というのは、「厭世的になった詩人」という意味です。厭世詩家とは、つまり、透谷自身のことを言っているんだろうと思います。つまり、そういうふうに自由民権運動に参加して挫折して、絶望して、厭世的になったということだと思うんですけど、そういう自分にとって、最後のよりどころが女性だと言っているわけですね。女性との恋愛が最後のよりどころだと透谷は言っているわけです。何も面と向かって論評しなくてもいいと思うんですけど、何か、そう言わざるを得なかったものが透谷の中にはあったんだろうと思います。
ですから、この場合に、透谷が女性だというのは、単に女性に慰安を求めたということではないと思うんです。もっと積極的な意味が込められているはずなんですね。それは、僕の言葉でいうと、「自己意識の問題」になると思うんですけど、つまり学生時代に透谷というのは、自由民権運動という形で、現実の政治運動、社会運動に参加していきます。ですから、その中で現実的に、社会現実的に、自由とか理想というのを追い求めたと思うんです。しかし、現実の壁に跳ね返されたというか、現実に挫折して、絶望したときに、改めて、自分の生きる意味といいますか、どういうところで自分を支えるのか、あるいは、どういうふうに挫折して絶望した自我を救済するのかとか、あるいは、どこに自分が自分であることの根拠を見出すのかとか、そういうことを考えたはずなんです。
それに対して、透谷が出した答えが、女性という、女性との関係であると言っているわけです。すると、この場合の恋愛ということには、言ってみれば、透谷の自己がすべて、多分、賭けられている、大げさにいうと、そういうふうに言ってもいいと思うんです。どういうことかというと、自由民権運動に参加して、いろいろあって、現実の近代化の運動には失敗する、挫折するわけです。そのときに、透谷の中で、自己というもの、あるいは自分という意識の近代化といいますか、自我の近代化、そういうことが考えられたんだろうと思います。で、それを女性との関係に求める、女性との恋愛に求めたというのが、透谷の新しさというか、独創的なところだと言えると思います。
これは、先に話した、漱石の一連の作品にも通じるテーマなんですけども、漱石の非常に強い影響を受けた芥川龍之介とか、そのあとの有島武郎なんかにも引き継がれていく、そういう意味でいうと、日本の近代文学にとって非常に大きなテーマだというふうにいえます。つまり、近代というものと恋愛とを結びつけて考えたということが、非常に特徴的なんです。彼らにとって恋愛というのは、そういう意味を持っていたということだと思います。
つまり、近代とは何かということを、自我とか自己意識のレベルで問うたときに、そのほとんど唯一の答えとして、恋愛というのが出てきているというふうに言えると思います。それは、日本の特殊な事情というのは多分あったと思うんですけども、透谷もそうですけども、芥川にしても有島武郎にしても、キリスト教の非常に強い影響を受けています。田山花袋(たやまかたい)とか、あるいは島崎藤村とか国木田独歩なんかも、やはり若い時期にキリスト教の感化を受けているんですね。彼らがなぜ、キリスト教に引きつけられたんだろうと考えますと、おそらくキリスト教の中にある博愛とか、あるいは隣人愛というような考え方、それが、他者との新しい関係の可能性を開示するというか、示してくれる、そういうものとして、彼らは引きつけられていったんじゃないかと思います。
つまり、キリスト教がそこで何を教えているのかというのを、僕なりに解釈すると、「他者を公正に扱え」ということを多分教えていたんだと思います。そういうメッセージを彼らは受け取ったんじゃないかと思います。つまり、その「他者を公正に扱え」ということは、本当は社会の中で実現すべきなんでしょうけども、それを実現しようとして、自由民権運動とか社会主義運動に関わっていったのかもしれません。しかし、実際、有島武郎なんかは、社会主義にのめりこんでいくというか、傾倒していきまして、最晩年には、彼は大農場を持っていましたが、北海道の有島武郎の自分の農場を、小作人に分与する、分け与えるというか、解放するというか、そういうこともやってるんですね。だから、彼は本気でそういうことを考えた人だと思うんですけども。
しかし、当時の日本の社会は、一般的には、日本の社会の現実として、自由とか平等というものが社会的に実現する可能性というのはほとんどなかったというように思うんです。ですから、北村透谷のように、そういう社会的現実に挫折し、敗北したときに、唯一の活路を見出した場所が、女性との関係、女性との恋愛だったんじゃないかと思います。つまり、そういう場所で、いかに女性を対等に扱うというか、人間らしく扱うかというところに、彼らの近代的な自我、近代という意味が掛けられていたと言えるんじゃないかと思います。つまり、後発の近代国家というか、要するにヨーロッパ、欧米の列強から押し入られて開国した日本ですから、後進的な近代国家である日本において、近代的自我というのは、どういうものなのかを問うたときに、そういう黎明期の文学者たちというのは、それを女性との関係、女性との恋愛というところに求めたというか、つまり自由で対等な恋愛というところに求めたように思います。
ですから、いわゆる江戸時代の因習的な男女関係とは断絶したところですね、家柄とか財力とか社会的地位とか、そういう制度的なものを抜きにして、一人の女性との間に純粋で自然な愛情による関係というのが成立するかどうかとか、相手の女性をそういうふうに人間として対等に扱うことが、彼らにとって近代あるいは近代的な自我とか自己ということに対応していたんだろうと思います。
では、そういう意志というのは、どこからやって来るのかを考えてみたいんですけど。明治時代の女性の地位というのは、僕たちからすると想像できないぐらい弱いものだったと思うんです。そういう女性に対して、強権的に振舞わない、あるいは庇護者として振舞わないというか、そういう弱い立場に付け入らずに、できるだけ公平に扱う、人間らしく対等に対処するという、なぜそんなことを彼らはしたのかというと、別に誰かから命令されたわけではないと思うんです。つまり、彼らはキリスト教の感化を受けたといって、神様から命じられたというわけではないと思うんですね。何かそういう、強いられて、義務的にそうしたわけではない。あるいは、何か超越的な規範とか掟のようなものがあったわけではない。
では、なぜ彼らはそんなことをやったんだろうか。そうすると、「やりたかったから、やった」「そうしたかったから、そうした」という以外に、僕は理由がない気がするんです。つまり、もう少しいうと、そうすることが嫌じゃなかった、むしろ、快・不快でいえば快というように感じられたんだろうと思うんですね。もう少し理屈っぽくいいますと、主体的であるとか、自由であるというふうに感じられたんだろうと思います。つまり、相手の女性を対等に、一人の人間として公正に扱うということが、彼らにとっては主体的に振舞うことであるし、自由であるということだと感じられたんだと思うんです。
自由にしても主体性にしてもそうですけども、自分一人だけのものではないですね。必ず、関係性というか、他人との関係の中で、自由とか主体性が成り立つわけです。ですから、他人を自由な存在として認めなければ、自分も自由と自覚できないでしょうし、相手の主体性を認めなければ、自分の主体性も実感されないという、そういう相互規定的なものだと思うんです。
で、こういう自由とか主体性の中には、例えば自分の欲望を抑制して、相手の欲望を優先させるということが含まれているというように思います。これは、誰でも彼でも普通にやっていることで、例えば自分の欲しいものを我慢して、好きな人のプレゼントを買うとか、それは普通に誰でもやっていることだと思うんです。では、なぜそんなことをするのかというと、自分の欲しいものを買うよりも、それを我慢して誰かに贈り物をすることによって得られる喜びとか、あるいは満足感のほうが大きいからですね。そこが、人間と動物の大きな違いだと思うんです。
普通に考えて、動物たちにとっての快・不快というのは、言ってみれば、生命活動と一つのものというか、例えば、餌を食べられることが快であり、飢えることは不快であるとか、それははっきりしてると思うんです。もちろん、親が子のために自分の餌を子に与えることは、そういうことは動物でもするかもしれませんけども、それは本能としてやっているんだろうと思うんですね。それに対して、人間の場合は、自分の空腹を代償にして、相手の、例えば空腹を満たすことによって、より大きな価値をつくり出すことができるという、あるいは自分の欲望を抑制して、相手の欲望を優先させることを心地よいと感じることができる、そこが人間と動物の決定的な違いといいますか、人間が持っている非常に大きな可能性だと思うんです。
僕は、よく「おいしい」という感覚は、どうやって生まれたのかなとよく考えるんですけど、例えば夫婦でも険悪なときに一緒に飯食ってもおいしくないですよね。何食ってるかわからないというか、いくらおいしいものを食べさせても、店の雰囲気が悪いとおいしくないとかですね。ですから、そういう関係の中で生まれてくるものだというふうに思うんです、おいしいとかおいしくないとかですね。そうすると、僕の空想ですけども、例えば、自分が食べるつもりだった食べ物を誰か相手にあげて、その相手がそれを食べて、にこっと笑ったときに、多分「おいしい」という感覚が生まれたんじゃないかと思うんですね。あるいはその相手の笑顔を、自分のものとして味わったときに、例えば「幸せ」ということを実感されたんじゃないかというふうに、そういうふうに空想するわけです。
で、そういうことを、じゃぁ、原発についてもやればいいじゃないかと。ちょっと飛躍しますけど、そういうふうに僕は考えます。つまり、未来に生まれる人たちに安心して暮らせる、放射能のない安全な環境をプレゼントして、「幸せ」と思えばいいじゃないかと、僕なんか考えるわけです。冗談っぽく聞こえるかもしれませんけども、本気で割とそういうことをちゃんと考えようと思っているんです。まだまだ、そういう冗談ぽくしかいえないんですけども、人間というのは、本当はそういうことがやりたくてしょうがない動物だと僕は思っているんです。
つまり、電力がほしい、しかし、そういう自分たちの欲望を抑制して、未来の人たちに、放射能に汚染されていない国土をプレゼントする、あるいは、自分たちの不利益を受け入れることで、未来に生まれる人たちを公正に扱う、あるいは彼らとの間に健全な関係を築いていこうとする。それは自己のあり方として、僕たちはそれを喜ばしいもの、快いもの、心地よいものというふうに感じることができるはずなんですね。それを、いまお話ししてきた近代文学の文学者たちが追求したテーマを現代に応用すると、そういうふうなことが言えるんじゃないかと思います。
最後に、今度出る本の宣伝を少ししようと思うんですけど、今度7月にNHK出版というところから、「死を見つめ、生をひらく」という本が出るんです。NHK出版新書という新書がありまして、黄色いカバーの新書のシリーズなんですけど、そこから7月10日ぐらいだと思いますが、「死を見つめ、生をひらく」というタイトルの本が出ます。で、この本の中で問いかけたかったのは、現在、僕たちはどういう自己、自分を生きているんだろうかということです。そうした自分に耐えられるんだろうか。例えば、自分というものを問題化する、積極的に問題化してみて、そういう自分から、離脱するといいますか、自分の生き方を変えるとか、考え方を変えるとか、あるいはいま生きている社会を変えるとかいうことにつながっていくと思うんですけど、そういうことを問いかけたいと思ったわけです。
いろいろ論点があるんですけど、例えば、いまの首相でもそうですが、経済成長みたいなスローガンを、いまだに掲げる人がいますけど、しかし経済的に豊かになることで、果たして僕たちは幸せになれるんだろうかということを、僕らの間でよく考えます。もう経済的に豊かになるということでは、僕たちは幸せになれないんじゃないかという気がします。もう僕らの実感からいいますと、飽き飽きしているというか、結構飽きているところもありますし、疲れているというところもあるような気がします。日本のGDPというのは、数年前に中国に抜かれましたけども、それでも世界第三位ですね。それだけの経済力を持っていながら、日本の国民の多くは、豊かさや幸せも実感していない。それはどういうことなんだろう。だから、もっと、さらなる経済成長が必要だという理屈になるのかもしれないですけど、それは何か目指しているものが間違っていると思いますね。そういうことじゃないと思います。
例えば、いま何がリアルかということを考えてみますと、例えば原発を稼働させないと日本の経済が行き詰まって、国が不幸になってしまう、そういうことが本当にリアルなんだろうか。あるいは国防軍を作って防衛力を強化しないと、どこかの国が日本を侵略する、そんなことが本当にリアルなんだろうか。全然違いますよね。為政者の言ってることは全然見当外れじゃないかというふうに僕なんかは思います。そんなところにリアリティなんか全然ないんですよ。僕らが感じているリアリティって、例えば経済格差みたいなのをテコにして、大量消費を続けている、そのことの不快感といいますか、そのことで目に見えないところで誰かを虐げてるんじゃないかとか、誰かのものをかすめ取ってるんじゃないかとか、あるいは自然とか環境を損なっているんじゃないかとか、そういう形の、何か自分から不当で不正なことに関わっている、それは意識的にやってるんじゃなくて、生きること自体が、そういうシステムの中に巻き込まれてしまって、取り込まれてしまっている、そのことの不快感とか嫌悪感のほうが、よほどリアルだと思います。それは、僕はリアリティだと思います。
そうすると、僕らが幸せとか豊かさを実感できないというのは、そういうことが原因なんじゃないかというように思うんです。つまり、何か不正なこととか不安なことに自分が生きているということが結びついている、そういう意識が、漠然とあると思うんですね。あるいは、意識下で現在や未来の他者を公正に扱ってないことが、そういう、うまくいいがたい思いというのがあって、そういう「やましさ」というのが、何か形のない不安感のようなものとして、いまの日本の社会を覆っているような気がするわけです。
そうすると、僕たちが目指すべきことというのは、経済成長とか軍備増強ということではなくて、現在や未来の他者というのを公正に扱うことじゃないかと思います。その一つの契機として、脱原発ということを考えていけばいいというふうに思うわけです。だから、原発から離脱するということは、なんとなく不正で不当なことをやっている自分から離脱するということだと思います。あるいは、そういう自分の生き方から離れる、少しでも離れようとする、そういうことだと思うんです。
だから、経済成長とか軍備増強とか、そんなもの、いい加減、あるいは大量消費とか、いい加減切り上げて、これからは僕たちは、あるいい方をすると、みんなで豊かに幸せに貧しくなっていく、そういうものの考えをするべきじゃないかと思います。それが、僕たちの本当の幸せとか、あるいは豊かさという実感につながってくるような気がするんですね。そのことで、現在と未来の他者を公正に扱うというか、それは十分に僕らが生きている、生きるモチーフになるというふうに思うんです。誰もが、そういう生き方を望んでいるはずなんです。それはなぜかというと、恋愛と同じモチーフといいますか、恋愛と同じ情動がそこには流れているからですね、だから、みんな本当はやりたくてしょうがないはずなんです。誰だって、原発から離脱することに夢中になるというふうに僕は思っています。
ちょっと考え方を変えれば、それはみんな気付けることなんじゃないかと思います。そこには恋愛なんかと同じ喜びとか充実感があるはずなんです。しかも、恋愛と違って賞味期限がないというか、80になっても90になってもそういうことがやれるわけだから、そういうふうに僕は脱原発の問題というのを考えていきたいというふうに思います。
もう一つ、憲法9条の問題があるんですけども、僕は最近に憲法の勉強をはじめて、まだきちんと考え尽くせてないところがあるんですけども、いま考えていることを少しお話ししていきたいと思うんですけど。多くの人が言っていることですけども、現在の国際政治の流れというのは、武力行使を禁止するというのは、もう主流になってますよね。国際法上も、武力行使というのは違法なんだという考え方が趨勢を占めるようになってきていると思います。
そうすると、平和主義というのは、ほとんどの国が平和主義を標榜しているわけですね。実際、憲法学者らが言っていることを読むと、国の憲法の中に平和条項を持っている憲法はたくさんあるんだそうです。だから、日本の9条だけが、そういう意味でいうと特別なものではないということになるんですけども。そういうのがいまの国際社会の流れなんですね。最近勉強したところによると。だから、それに逆行しているのは、アメリカと北朝鮮ぐらいじゃないかというように僕は思うんですけれども。それでも、戦争というのが絶えない。どこかで戦争とか紛争が起こっている。それはなぜかというと、平和主義では戦争が回避できないということだと思いますね。つまり、自衛という考え方が認められているからだと思うんです。つまり、自衛という形で、いろんな戦争とか紛争が絶えず起こっている。そうすると、自衛でない戦争というのはないんじゃないか、あらゆる戦争は自衛戦争じゃないかと言ってもいいように思います。
そうすると、僕らが考えなければいけないことというのは、自衛という考え方をいかに乗り越えるか、あるいは自衛権を否定するというふうに考えていかないと、戦争を回避する、戦争をなくすというふうにはならないと思いますね。そういう道筋を現実的につけている唯一の憲法ということでいうと、日本国憲法の9条、特に第2項の戦力の不保持と交戦権の否認を規定した、いわゆる非戦条項といわれているものがそれに当たるんじゃないかと思います。
ですから単純に考えて、この非戦条項の、日本の9条、憲法が持っている非戦条項を否定する人間というのは、世界に一人もいないはずですよね。それは、人間として誰もが望んでいることですから。じゃあ、憲法9条を変えて、非戦条項を変えようとしている人たちは、なぜそんなことを考えるのかというと、人間として考えていないからですよね。どこか、人間という場所に立てずに、もっと狭まったところで、諸島とかそういう場所で物事を考えるから、そういう考え方が出てくるわけで、人間という場所に立てば、世界中の誰だって合意することだと思います。
最初の話に戻りますけども、人間というのは自由を欲する生き物ですし、どこまでも主体的に生きることを望む動物だというふうに思うんですけども、しかし、現実には、僕らは日本国とか、どこかの国とか、文化に帰属して生きているわけです。そういう制約のもとで生きているわけです。しかし、日本国憲法の9条の非戦条項というのは、そういうどこかの国とかどこかの文化を超越してるというふうに言えると思います。つまり、特定の国家の利害とか共同体の利害とか、あるいは宗教的・民族的な違いを超えたところで、戦力の不保持と交戦権の否認が言われているわけです。だから、それは地球上の全ての人間が共有できるものだし、僕たちが人間とか人類という普遍的な立場を取りうる、現実的には唯一の場所なんじゃないか。つまり僕たちが最も自由に、主体的に生きることのできる場所というのが、憲法9条の非戦条項に象徴されているんじゃないかというふうに僕なんかは思うわけです。
で、まだ、ここの辺は、まだ僕の中でもうまく考えが整理できていないんですけど、次にお目にかかれるときには、もう少し説得力のある話ができるようにしておきたいと思います。今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
(文中一部敬称略)