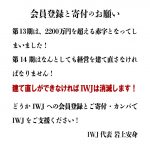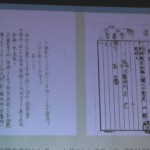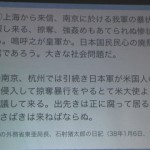2015年2月15日の『産経新聞』が一面トップで南京事件否定論(注1)を展開したことに驚かされた人は少なくなかったようで、ツイッターの私のタイムラインでも盛んに話題になっていました。しかし南京事件否定論は「慰安婦」問題否認論よりもはるかに長い歴史をもっています。みなさんが驚かれたとすれば、それは2000年代の後半に下った2つの判決によって、南京事件否定論がやや勢いを失っていたからです。
その訴訟とは、南京事件の生存者(家族を殺された遺族でもある)夏淑琴(シア・シュウチン)さんが東中野修道・亜細亜大学教授とその著書『南京虐殺の徹底検証』の版元展転社を訴えたもの(夏淑琴さん訴訟)と、南京攻略戦のさなか「百人斬り」(注2)を行ったとして戦後の戦犯裁判で死刑になった2人の将校の遺族が、『朝日新聞』『毎日新聞』やジャーナリストの本多勝一氏らを訴えたものです(百人斬り訴訟)。
夏淑琴さん訴訟では『南京虐殺の徹底検証』における夏さんについての記述に対して「学問研究の成果というに値しない」(東京地裁判決)など極めて厳しい評価が下り、被告に400万円の損害賠償が命じられました(2009年に判決が確定)。東中野教授はその後右派論壇から事実上引退しています。
百人斬り訴訟では原告の請求が退けられただけではなく、2人の将校について「当時としては、『百人斬り』競争として新聞報道されることに違和感を持たない競争をした事実自体を否定することはできず」(東京高裁判決)とし、戦争犯罪の事実がより一層はっきりするという“やぶへび”な結果となりました(2006年に判決が確定)。
ところが、『朝日新聞』が昨年、過去の「慰安婦」報道の一部を撤回したことで勢いを得た日本の右派は、南京事件についても否定しようとする姿勢を再び示しはじめたのです。月刊誌『WiLL』の14年10月超特大号では藤岡信勝・新しい歴史教科書をつくる会理事が「次に取り消すのは『南京大虐殺』だ」と題する記事を寄稿し、稲田朋美・自民党政調会長は14年10月27日の『産経』に掲載されたインタビューで「百人斬り」について「朝日にはぜひもう一度再精査をお願いしたい」などと語っていました(ちなみに、百人斬り訴訟で原告代理人を務めたのが他ならぬ稲田氏ですので、随分と虫のいい主張と言わざるを得ません)。
『産経』の連載「歴史戦」でも昨年12月24日に始まった第8部がすでに南京事件否定論をとりあげていました。ですから、15日の一面トップ記事は規定路線だったわけです。
「見なかった」という証言の限界
15日から始まった「歴史戦 第9部」は南京攻略戦に従軍した元軍人の「虐殺は見なかった」「城内は平穏だった」などといった証言を紹介しています。あらかじめお断りいたしますが、ここで私はこれらの証言の信憑性について細かく検証するつもりはありません。後で述べるように、その必要がないからです。必要もないのに、90歳を超えた方々の証言の信憑性を云々することはあまり品位ある振る舞いとは言えないでしょう。
他方で、元「慰安婦」の方々の証言については徹底的に粗探しをしようとした『産経』が、元軍人らの証言を記事にするにあたってどれだけ綿密な裏づけ取材をしたのか、は問われるべき問題でしょう。
「受けてもいない性暴力被害をでっちあげて証言する」ことと「自分が行った、あるいは仲間が行った虐殺を否定する証言をすること」を比べた時、一般論としてどちらがよりありそうなことでしょうか? 今日ですら、性暴力の被害を訴えたひとは偏見にさらされ、しばしば「隙があったからじゃないか」「露出の多い服装をしていたからだ」などと非難されることすらあります。まして性暴力の被害を受けることを「恥」とするような価値観が強固な時代に生まれ育った人たちなら、嘘の被害を申し立てることで得られるかもしれない“利益”にくらべて“損害”の方がずっと大きく感じるのが一般的でしょう。 これに対して、自分自身や自分の仲間たちが行った加害行為を隠蔽したい、あるいは小さく見積もりたいと思うのは、誰にでも思い当たる心理です。
さて、なぜこれらの証言の信憑性を吟味する必要がないのでしょうか? 一人の人間が見聞できることには限りがあり、どの証言者も南京市のごく一部を、限られた期間行動したに過ぎないからです。だから「見なかった」という証言を断片的に集めてもほとんど意味はないのです。歴史学者の秦郁彦氏は次のようなたとえを用いて説明しています。
筆者は東京・目黒区の一角に住んでいるが、朝刊を開いて、前夜、近所で火事や犯罪が起きているのを知り、びっくりすることが多い。新聞がなければ、聞かれても「知らない」「見ていない」と答える事例がほとんどであろう。その種の証言を苦労して山ほど積みあげても、火事の確実な目撃者が二人現れたら、シロの主張は潰れてしまうに決まっている。
(『昭和史の謎を追う』、文春文庫、上巻183-184ページ)
15日の記事は南京城(注3)の大きさについて「JR山手線が囲む面積の3分の2程度」としていますが、市街は城外にも広がっていました(さらにその周囲には広大な農村地帯があります)。JR山手線の内側を思い浮かべてみてください。当時の日本軍の基本的な移動手段は徒歩です。この範囲を数日歩き回ったとして、東京の都心で起きる出来事のどれほどを目撃できるか、想像してみてください。
そもそも、15日の記事(産経新聞=「城内空っぽ。誰もいなかった」「虐殺あるはずない…」)に登場する元軍人は「場内は空っぽ」だったとしているのに対して、翌日の16日の記事(産経新聞=「誠に和やかに尽きる…」 城内に露店建ち並ぶ「平和な進駐」)に登場する元軍人は「日常生活を営む住民」「露店が立ち」と証言しています(※1)。目撃した時期と場所が異なれば、このように正反対の証言が出てくるわけです。
※編集部注1――2月16日付の産経新聞は、「旧日本軍が…中国・南京を攻略した後の一時期を、城内で過ごした元海軍第12航空隊の3等航空兵曹の原田要(98)」氏の証言を「南京は誠に和やかに尽きる、という印象でした」と紹介。さらに、「陥落後に城内の飛行場に降り立った原田の印象に残るのは、日常生活を営む住民らの姿だった。露店が立ち、住民らは日本兵を相手に商売を始めていた」などとも記載していた。
現場にいた人物の「なかった」「見なかった」という証言を並べればいかにももっともらしい記事ができあがりますが、「一人の人間が見聞できることはごく限られている」ことをしっかりふまえるなら、『産経』の一連の記事が「虐殺はなかった」ことの根拠になどまったくならないことがわかるでしょう。
虐殺の大半は城外で起こった ~ 域内に焦点をずらす虐殺否定論者のトリック
17日の記事(産経新聞=「婦女子に手をかけてはいけないと厳命されていた」 憲兵配置…略奪・強姦ありえない)で『産経』は「こうした『不法行為』の多くが行われたという城内の『安全区』」(注4)と書いていますが、これは誤りです。
南京にある大虐殺紀念館の展示でも、日本の研究者の見解でも、虐殺の大半は城外で行われたとされています。典型的な殺害方法は城外を流れる揚子江岸に連れ出して射殺したり銃剣で刺殺したりするというものでしたが、その理由はもちろん遺体の処理が容易だったからです(※2)。したがって「城内で虐殺は見なかった」という証言があるのも不思議はないのです。これは南京事件否定論がしばしば用いるトリックですので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。
※編集部注2――詳細は2014年2月28日に行った
を参照。
15日の記事で「城内は空っぽ」などと証言していた元軍人が所属していた第6師団の戦史(『熊本兵団戦史』、熊本日日新聞社)にも「城外」での非戦闘員の殺害が記述されています。
(……)南京攻略戦では南京城西側・長江河岸間は敵の退路に当たり、敗兵と難民がごっちゃになって第六師団の眼前を壊走した。師団の歩砲兵は任務上当然追撃の銃砲弾を浴びせ、このため一帯の沼沢は死屍で埋められたという。
これが戦争犯罪であるかどうかは議論のあるところでしょうが、非戦闘員(「難民」)に犠牲が出ることを承知で攻撃したことは間違いありません。
「無抵抗の民間人を殺すことだけが虐殺だ」という手前勝手な理屈 ~ 捕虜の殺害は戦時国際法違反であり、「虐殺」
また、実際には虐殺を目撃していながらそれを「虐殺」として認識していない、というのも「なかった」という証言が出てくる理由の一つです。15日の記事の元軍人は「無抵抗の民間人を殺すのが虐殺」と語っていますが、もちろんこれは常識に反する手前勝手な定義です。捕虜の殺害はれっきとした戦時国際法違反の戦争犯罪であり、「虐殺」だと言われても当然です。
17日の記事には「軍服を脱ぎ捨てて民間人になりすました便衣兵の掃討が、南京城陥落直後の昭和12年12月14日から始まり」とありますが、これまた南京事件否定論がしばしば用いる論法です。「便衣」とは軍服ではない通常の衣服を指す言葉で、「便衣兵」とはいまで言うゲリラのことです。
日本軍は戦意を喪失して軍服や武器を捨てた中国軍将兵を狩り出して殺害しましたが、その際日本軍はいい加減な基準で民間人と軍人の判別を行い、少なくない民間人が巻き添えになったとされるのに加え、法的手続き(裁判)抜きで殺害してしまいました。兵士が軍服を脱ぎ捨てただけではもちろん戦争犯罪ではなく、平服で戦闘行為を行って初めて(当時の戦時国際法では)戦争犯罪となります。しかしその場合ですら、あくまで裁判を通じて処罰を決めるのが戦時国際法の定めるところでした。たとえ日本軍の主観では「便衣兵の処刑」であったとしても、客観的には国際法違反の戦争犯罪に他なりません。
大本営参謀から戦後、空将までつとめた人物が目撃した「南京虐殺」