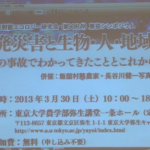2013年5月25日(土)13時30分、京都市下京区のキャンパスプラザ京都において、「見えない放射能とたたかう 『サイレント ウォー』」と題した講演会が開かれた。この講演会は、市民団体の使い捨て時代を考える会が、設立40周年を記念して、連続企画の第1弾として開催したもの。この日は、京都大学原子炉実験所助教の今中哲二氏を講師として招いた。今中氏は「放射能汚染への向き合い方」とのテーマで、福島第一原発事故による放射能汚染と向き合わざるを得ない現実の中で、どのように対処していくのがよいのか、持論を述べた。
- 13:37~ 主催者あいさつ 津田君江氏(使い捨て時代を考える会 代表理事、安全農産供給センター 代表)
- 13:42~ 講演 今中哲二氏(京都大学原子炉実験所 助教)「放射能汚染への向き合い方」
- 15:22~ トークセッション
- 16:19~ 「おだやかな日常」上映会案内
- 16:21~ 閉会あいさつ 山田晴美氏(使い捨て時代を考える会 代表理事)
冒頭、今中氏は「無視できないレベルの放射能汚染が、特に、東京から北の本州・太平洋側にもたらされた」と語った。また、「福島の陸上汚染で、長期間にわたって問題となるのは、半減期30年のセシウム137である」と述べた。さらに、「2011年3月15日、枝野幸男官房長官(当時)が記者会見で『(福島第一原発)2号機の格納容器が損傷した』と言った時に、福島はチェルノブイリぐらいの事故になった、と確信を持った」と振り返った。
続いて、原発事故後に頻繁に出てくるようになった、Sv(シーベルト)とBq(ベクレル)という単位の違いについて説明したほか、原子力の専門家として今中氏が考える、「1時間あたりの被曝線量に対する問題意識」について説明した。この中で今中氏は、0.1μSv(マイクロシーベルト)は「ほとんど気にしない」、1μSvでは「8時間ぐらいなら作業をする」、10μSvでは「長居をしない」、100μSvでは「せいぜい5分程度」、1000μSvでは「べらぼうな線量。逃げ出す」と表現した。その上で、自身が浴びた、時間あたりの最大被曝線量は、「チェルノブイリ原発の、石棺内部にあるポンプ室を調査した際の、約1000μSvである」とした。
「1日あたりの被曝線量に対する問題意識」についても見解を述べた。これによると、1μSvでは「気にしない。自然放射線による外部被曝は1日で約1μSv」、10μSvでは「ちょっと浴びたなぁという感覚。胸部レントゲン検査1回で50μSv」、100μSvでは「かなり浴びたなぁという感覚。ヨーロッパへの飛行機往復で50~100μSv」、1000μSvでは「大変だ。始末書だ、という感覚」と表現した。
急性放射線障害や晩発性放射線障害についても、その違いを説明した。これに関連し、今中氏は「枝野(官房長官・当時)さんが言っていたように、福島第一原発周辺住民の被曝は、すぐには健康に影響がないだろう」としながらも、「問題は、あとあとになって現れる晩発性障害だ」と憂慮の念を示した。また、現地で適切な初動対応を行わなかった、原子力安全・保安院の担当者について、「(彼らの思考や行動は)メルトダウン状態だった。(彼らのせいで、住民に)浴びる必要のない、無駄な被曝をさせてしまった」と厳しく批判した。
「放射線被曝の影響は、被曝線量に比例する」との見解も述べ、がんの発生過程についても、「DNAらせん構造の2重鎖の切断が起きることが問題」などの説明を行った。チェルノブイリ事故後に、実際に発生している健康被害については、ウクライナの子どもの甲状腺がん発症数が急増しているグラフを示し、事故直後に拡散した揮発性の放射性ヨウ素や、放射性セシウムによる影響ではないか、との見解を示した。
また、福島第一原発事故のあとに、福島県の子ども1000人を対象とした甲状腺検査が行われたことについて、「先日会ったロシアの学者に、『何で、1000人しかやらないんだ』と指摘された」と明かし、「ソ連は40万人を対象に検査を実施した。ウクライナで15万人、ベラルーシで20万人、ロシアで5万人の甲状腺チェックを行い、その後も、被曝調査などを実施している」と述べた。さらに、「日本では、事故発生直後、測定器を持って現地入りした弘前大学の専門家に対し、福島県が『人心の不安を煽るようなことをやめろ』と言って止めた」と語り、「(真実に)フタをしようとしているのではないか」と批判した。
低線量被曝による影響については、米国科学アカデミーの「BEIR-VII報告(2005年)」を「しっかりしている」と紹介し、この報告が、発がんに対する線量・因果関係は「しきい値なし直線である」と規定していることや、「集団の平均として、1mSvの被曝によって、後にがんが発生する確率は、集団全体の1万分の1程度である」と分析していることなどを説明した。
学者としての心構えについても語った。サイエンス(科学)を思考する上で、「確か・確かかどうかはっきりしない・あり得ない」という事柄について、「確かかどうかはっきりしない、というグレーな部分が抜け落ちてしまいがちである」とし、「本来、すべてを疑うのがサイエンスの基本である」との持論を示した。
これに関連し、今中氏は、チェルノブイリ事故後の健康被害を扱ったドキュメンタリー映画『チェルノブイリ・ハート』について、「つまらん」と斬り捨てた。その理由として、「観た人は必ずショックを受ける内容だが、障害を持った子どもたちと、チェルノブイリ事故の放射線被曝の影響(との関連性)を具体的に示すものは何もない」と語った。さらに、「(映画に登場する)医師が、『ベラルーシで生まれる子どもの8割ぐらいは病気持ちだ、障害がある』と言うが、そんなことはないと私は思った」と述べた。その上で、チェルノブイリ事故が起きる前からベラルーシで調査がなされている、「流産した胎児の先天性障害を調べたデータ」を提示し、原発事故との関連性が、「はっきりとはわからない」とした。
福島第一原発事故による放射性物質の拡散という現実の中、どこまでの被曝なら我慢するのかについては、「一般的な答えはない」としながらも、「年あたり1mSvが、我慢を考える際のスタートラインだ」とした上で、「子どもは感受性が強い。将来を考えると、子どもの被曝は極力少なくすべき」との見解も合わせて示した。
特に、「子どもたちを守るために最低限すべきこと」として、「(検査のために)子どもを登録する制度をつくり、被曝量を測定する。特に、事故の後にどれぐらい被曝したのかを見積もる必要がある」と述べたほか、「定期的な健康診断の実施」や、汚染のある地域と汚染の少ない地域とを集団ごとに比較するために、「汚染の少ない地域を含めた、健康状態を追跡調査する仕組みを作る」こと、さらに、「被曝量にかかわらず、原発事故に関連する健康被害のケアを、法律で制度化する」ことが必要であるとした。
講演の終盤、今中氏は「福島の汚染は、あくまで東京電力と日本政府が起こした不始末である」と批判した上で、「1ベクレルでも嫌だという権利が、私たちにはある。ただ、今現在のように、実際に汚染された時に、どうするか。私は、個人的には、折り合いをつけていかざるを得ないのではないかと思う」と述べ、放射能に囲まれた現実と向き合い、用心しながら生活していくという現実解を示した。