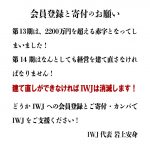2013年6月29日(土)13時30分、京都市東山区の東山いきいき市民活動センターにおいて、「6・29シンポジウム 革新は生き残れるか -新しい変革主体を考える(Part2)」と題したシンポジウムが開かれた。まもなく公示される参議院選挙では、憲法改正の発議に必要な3分の2の議席を、改憲勢力が占める懸念が現実味を帯びている。
一方で、護憲を掲げる革新勢力は、近年伸び悩みが続く。今回のシンポジウムでは、なぜ現在のような政治状況になってしまったのかを問い直すべく、望田幸男氏(同志社大学名誉教授)と、碓井敏正氏(京都橘大学名誉教授)が講演(問題提起)を行った。また、講演終了後には、憲法を守り国民の暮らしを豊かにしていく、「革新勢力の主体づくり」に寄与していくために何をなすべきなのか、聴講者も交えて活発な意見交換を行った。
- 問題提起
望田幸男氏(同志社大学名誉教授)「人々はなぜ民主主義より独裁を選んだのか―ナチスに至らない道はあり得たか」
碓井敏正氏(京都橘大学名誉教授)「護憲運動と革新組織の再生―運動の拡大のために何が求められているのか」()
- 15:00~ 会場との議論
- 日時 2013年6月29日(土)13:30~
- 場所 東山いきいき市民活動センター(京都府京都市)
- 主催 「革新は生き残れるか―新しい変革主体を考える」実行委員会
望田幸男氏(同志社大学名誉教授)の講演要旨
望田氏は「人々は、なぜ民主主義より独裁を選んだのか」というテーマで、戦前のドイツにおいて、どのようにしてナチスが政権を獲得するに至ったのか、ナチスに至らない道はあり得たのかについて、熱弁を振るった。
望田氏は、ワイマール期(1919~1933年)を経てナチスが政権を獲得するに至った経緯を、「食えない民主主義より、食える独裁を選んだ」と表現した。ワイマール期においては、世界屈指の民主憲法が施行されていたにもかかわらず、複数連立政権の平均寿命が7ヶ月という政局混乱による、「決められない政治」に加え、極度のインフレや世界大恐慌による経済混乱も加わり、国民の不満が高まっていた実情を説明した。
一方、1951年に西ドイツで行われた世論調査において、「どの時代がよかったか」という問いに対し、「第一次世界大戦前」が45%、「戦前ナチス期(1933~1938年)」が42%、「ワイマール期」が7%、「西ドイツ期」が2%、「戦中ナチス期」が0%という結果になったことを紹介した。また、それ以降も、定期的に行われた世論調査では、経済発展を遂げて国民が豊かになったことから、「西ドイツ期」がトップになったものの、「戦前ナチス期」の高評価は変わらず、「ワイマール期」への評価はますます減っていったことを紹介した。望田氏は、そのひとつの要因として、ワイマール期の終盤には失業者数が500万人にも達していたものが、戦前ナチス期には経済政策や再軍備による経済効果で、失業がほぼ解消されたことを挙げた。
続いて、望田氏は、連立政権の短命が続き、政局が混乱していたワイマール期において、ナチスが国会で勢力を拡大していった経緯を解説した。ナチスは1928年の総選挙で、初めて国会で議席を獲得(12議席・得票率2.6%)し、以後、1930年に107議席(得票率18.3%)、総選挙が2度行われた1932年には、前半は230議席(37.4%)、後半は196議席(33.1%)を獲得して第一党に躍り出たこと、さらに、最後の総選挙となった1933年には288議席(43.9%)に達したことを紹介した。その勢力拡大の過程において、ナチスが政権を獲ってから最初の数年間は、人気取りの政策を行いつつ、次第に他党勢力に対する弾圧を強めていったことや、弾圧の中においても、ドイツ社会民主党(社民党)やドイツ共産党への国民の支持が堅調で、ナチスは一度も過半数を獲れなかったことを紹介し、「逆の言い方をすれば、ドイツ国民の過半数は、ナチスを選んでいなかったということだ」と述べた。
「なぜ、ナチスが政権を獲り得たか」について、望田氏は「ファシズム研究においては、『下からの大衆運動』と『上からの保守との結合』という2つの側面から見る」と語った。これに関連し、「国家社会主義ドイツ労働者党」というナチスの正式党名の通り、ナチスが社会民主主義や労働運動に協調していた事例として、1930年に共産党が主導して実施した市電のストライキに、党幹部が協力していたことを挙げた上で、その姿勢を一変し、1932年に第一党になる前年(1931年)から「反共産主義」を前面に出すようになったことを説明した。また、その背景として、当時はロシア革命から間もない時期であり、国民や資本家らに、共産主義への危機感があったことなどを解説した。
望田氏は、ナチスが保守派のヒンデンブルク大統領をはじめ、既存保守政党に接近し、議会第一党だが過半数でないという状況を、保守派との連合によって補い、ヒトラー首班内閣が発足した経緯を語ったほか、この内閣でナチスから3人、保守系から8人という構成にし、保守派を尊重するというポーズを取ったことを説明した。さらに、「保守派は、ナチスを左派に立ち向かわせる『番犬』とする算段だったが、ほどなく、保守政党も含めて、ナチス以外は一切禁止とされてしまった」とも解説した。
ワイマール期における連立政権を担った、左派中道勢力についても詳しく解説した。当時の政治勢力の中心は社民党であり、共産党と一線を画す意味でも、保守政党に対し安心感を持たせて長年政権を担ってきたが、失業保険問題などでの対立により、連立政権に入れなくなったと解説した。一方、左派と右派の間に位置した「カトリック中央党」(中央党)について、望田氏は「日本で言うところの公明党。結構根強い。そんなにも(支持が)増えないが、減ることもない。本当に似ている」と評した。この中央党の動きについて、ワイマール期の末期には、社民党ではなく中央党が与党連合をまとめるという流れになり、ヒトラー政権ができる際には、「保守勢力がナチスと連携するかどうか」のカギを握っていた中央党が、結局はナチスの側につき、ヒトラー内閣成立が実現してしまったことを述べた。
最後に、望田氏は、ナチスが政権を獲得する道を作った要因として、「社共(社民党・共産党)の連合戦線ができなかったからだ」と一般的に言われていることについて、「大ざっぱ過ぎる」と述べ、下(大衆)によるナチスへの不安の高まりから、社共連合が地域によっては存在したことなどを紹介した。その上で、「ナチスはまったくの新しい勢力だった。社共連合戦線が『ナチスをどう見るか』という点がぶれてしまい、ナチスへの評価が定まらなかった」ことが、ナチス独裁を防げなかった要因であると分析した。
碓井敏正氏(京都橘大学名誉教授)の講演要旨
碓井氏は「護憲運動と革新組織の再生」というテーマで、護憲を掲げる革新勢力が抱える運動の問題点と、その打開には何が必要なのかを提起した。講演の冒頭、自民党の改憲草案について、「復古主義的な前近代的な中身で、戦後の憲法体制を破壊するもの」と酷評した上で、「そうはならないと思っている。戦前のワイマール期と違い、戦後の自由民主主義や市場経済の秩序が変更困難なものであり、自民党の右派勢力が、戦後の秩序を覆すような憲法草案を通すのは、はじめから難しい話だろう」と語った。
戦後の資本主義について、碓井氏は「かつてのように、植民地を獲得し、そこから利益を取るというような仕組みではなくなっている」とし、「資本主義が浸透し、相互依存関係を深めるなど、各国が何らかの協調体制を組んでいる。『統合資本主義』が世界の趨勢であり、これは否定しがたい」と述べた。
また、戦後に出てきた傾向として、「自由民主主義や市場価値の枠組みにそぐわない動きは支持されない」とした上で、「かつて、公明党は王仏冥合(おうぶつみょうごう)を掲げ、国立戒壇(こくりつかいだん)を造ると主張したが、権力へのアクセスを強める上で、それらを放棄せざるを得なかった」ことなど、日本での実例を紹介し、「戦後の価値規範の中では、どこかで妥協しないと生き残っていけない」と続けた。さらに、ヨーロッパでの実例として、極右勢力とされるフランス国民戦線の例を挙げ、「もともと過激な排外主義を展開していたが、権力獲得を視野に入れてからは、リベラル化している」と解説した。
自民党改憲草案については、「立憲主義を否定し、人権を否定、さらに、個を否定し、『種(民族)の論理』や道徳倫理を、国民に押し付けるもの」と指摘した。さらに、前文についても、天皇制や和の精神、助け合いの精神や「種の論理」を規定していることについて、「一定の、民族固有の道徳観や価値観を持ち出し、近代リベラル国家で主流となっている、『個人の道徳観の中立性』を毀損(きそん)するものだ」「日本の国柄に従えと強制し、基本的権利を侵害するものだ」と厳しく批判した。
碓井氏は、このような中身の自民党改憲草案がなぜ作られたのかという点について、改憲草案の中身が決まったのが昨年4月、つまり野党時代であることから、「野党であるがゆえに、書きたいことを書いて本音が出たのだろう」と分析した。また、「自民党は2005年にも改憲草案を作ったが、その際には立憲主義の立場を採っていた。象徴天皇制もそのままであり、国防軍ではなく『自衛軍』という呼び方をするなど、現在の改憲草案とは、かなり違う中身だった。これは、当時、政権与党だったことと関係している」とも語った。
「護憲運動の成功のために何をなすべきか」という命題については、憲法96条を改正して憲法を改正しやすくしようとする動きに対し、「96条は権力者を縛ることを規定しているのに、権力者側から規定を弱くすることを国民に提案するのは、けしからん」といった異論や、「君が代・日の丸は好きだが、憲法で規定するのはおかしい」といった意見が右翼サイドからも噴出していることを紹介した。その上で、「96条問題は、『右』や『左』の問題ではなく、『国家』対『市民』の問題である。市民レベルの運動として採り上げるべきだ」と持論を述べた。また、「平和主義と立憲主義は密接に関連している」とし、その例として、自民党改憲草案第9章で規定している緊急事態宣言規定によって、人権が簡単に脅かされてしまうことに警鐘を鳴らした。
安倍晋三首相への評価については、安倍首相の著書『新しい国へ』の内容を、「オリンピックで日本選手が活躍し、日の丸が揚がれば嬉しいじゃないか、そういうレベルの話だ」と評した上で、「著書には基本的なところが欠けている。かつての日本の歴史に触れているが、日本が行った侵略について、謝罪が一切ない」と述べ、「悪いことをしたのに謝らないのは、大人の精神ではない。子どもの精神だ」と斬り捨てた。さらに、「戦後の基本的な価値である、自由民主主義や市場経済の価値に立脚しようとする限りは、過去の日本の侵略に対し、反省や謝罪をすることは大前提になる。謝罪がない限り、現在の価値を言っても本物ではない」と述べた。
これに関連し、ドイツにおいて、「ナチスは問題を起こしたが、罪の意識をいつまでも引きずらなくてもいいのではないか」といった歴史修正主義の論争が起きた際、ドイツの哲学者・ハーバーマスが、「憲法愛国主義」によって、現在の憲法下での価値観を大切にすべきだと説いたことを紹介した。その上で、「日本は、戦後の価値観に乗っかっている以上、安倍流のナショナリズムは、ジレンマを抱えている」と語った。
勢いを失ってしまった革新組織をどう再生していくかという命題については、野党の統一戦線を組む際に、「重要課題を中心に据え、個々の組織の利害は二の次にするのが当然だ」と述べた。また、戦前のドイツにおいて、コミンテルン(共産主義インターナショナル)の指示や、社民党の規定などが足かせとなり、社共統一が実現しなかった例を挙げ、「(日本において)そういう発想が現在もないのかというと、ないとはいえない」とし、「自らの考え方を絶対化し、そういう立場から物事を見ていくという傾向はある」との自己批判的な見解を披露した。
その上で、社会が不安定化し、人々の不安が高まっている現状においては、政党が市民社会との連携強化を図ることが重要であるとし、「党内構造の柔軟化や、一般党員制とは違う斬新な発想、市民社会の知恵や活力を党が吸収し反映することが必要だ」とした。
革新組織の改革についても言及した。ワイマール期のドイツにおいて、社民党が、党員の多くを中年以上が占めて高年齢化していたのに比べ、ナチスは党員が若かったこと、さらに、共産党は党員が若かったものの、4割を失業者が占めていた実態などを解説した。また、当時のドイツにおいて、共産党はコミンテルンの指導を受け、鉄の掟による上意下達組織であったことを紹介した上で、「現在の(日本の)革新組織は、高齢化している。上意下達もドイツと似たようなところがないか。ドイツの共産党の悪いところが日本にもないか」と語り、市民社会に開かれた組織への転換を大胆に行うべきとした。
当時のドイツにおける社民党についても、組織の問題点を指摘した上で、「いまの革新政党もそのまま(同じ)だ。変わりがたい部分があるのだろう」とし、「結局、組織は少数者が多数者を支配する構造。専従のエリートが、一般党員を指導し、専従は独自の利害を持つ」と述べた。さらに、「専従は党員とイコールでないし、階級ともイコールでない」とした上で、「組織は、柔軟な構造に変えるべきだし、組織内の民主主義は必要だ。もちろん、組織にはある程度の集権制は必要だが、上が下を支配する構造になってはいけない」と持論を展開した。